音楽が聞こえる本ブックガイド BOOKMARK11号 村上春樹による『バット・ビューティフル』紹介文もあり
前回、次は山本文緒の『なぎさ』の感想を書くといいましたが、BOOKMARK 11号 "Listen to Books" を読んだところ、勝手に便乗して、音楽が聞こえる本を選びたくなりました。
そう、なんといっても村上春樹が巻頭エッセイを書いていることが話題になっている、今回のBOOKMARKですが、村上春樹が訳したジェフ・ダイヤーの『バット・ビューティフル』は、BOOKMARKを編集している金原さんも『サリンジャーに、マティーニを教わった』のなかで紹介しています。
デューク・エリントンやセロニアス・モンクといった、伝説的なジャズ・ミュージシャンについて、「客観的(歴史的)事実から、自分の想像をまじえた『物語』」を紡いだ、「ドキュメンタリーでもない、かといって純粋な小説でもない」本(by 村上春樹)とのことで、正直、ジャズはほとんど聞いたことのない私も読んでみたくなった。おふたりがこれだけオススメしているのだから、まちがいなくおもしろいのでしょう。
で、音楽が聞こえる本として、私が思いついたのは、ニック・ホーンビィの『アバウト・ア・ボーイ』。
映画もヒットしたので、あらすじをご存じの方も多いでしょうが、父の印税でお気楽に暮らす男が、シングル・マザーをひっかけようと下心を抱いたことがきっかけで、12歳の男の子と出会う物語。
なのですが、小説の後半部分では、ニルヴァーナのカート・コバーンが重要な存在となっている。映画ではこのくだりはなかったような記憶があるけれど、そのかわり、ヒュー・グラントが例のごとく無責任男にめちゃくちゃはまっていて、映画は映画でよかった。
ニック・ホーンビィといえば、レコード屋で働くさえない男を主人公にした『ハイ・フィディリティ』も、小説と映画のどちらもおもしろかった。最近の作品も読んでみようかな。
ボストン・テランの『その犬の歩むところ』にも音楽が印象的なシーンがあるのですが、それについてはこないだ書いたので省略。
あと、同じく少し前に紹介した、ミック・ヘロンの『放たれた虎』では、シャーリーがマーカスの車のなかで、アーケイド・ファイアの海賊版のCDを発見し、マーカスにしては気のきいたCDを持ってるじゃないか、どうせ子どものものだろうと、さくっとパクるが、そのCDがあとで意外にも役にたったりする。いや、CD盤としてであり、「音楽を聞く」わけではないですが。
あと、少し前に洋書で読んだ、Eve Chaseの『The Wildling Sisters』は、ケイト・モートンの推薦文や、『レベッカ』を想起させるなどの評からうかがえるように、イギリスの田舎のお屋敷に住む妻を主人公とし、過去と現在の語りが交錯するミステリーだった。
で、その妻が、亡くなった前妻の思い出から逃れるため(このあたりが『レベッカ』要素)、ロンドンから田舎に移住することを提案するのだが、引っ越しのときに、夫がブラーの「Country Life」を聞いて、前妻との思い出にひたっているのを見てショックを受けるというシーンがあるのだが、ブラーもすっかり懐メロ扱いか……と、こちらもしみじみしてしまった。
いや、私が学生時代に流行っていたので、当然懐メロなのですが。ブラーのライブは見たことないけど、オアシスは大阪城ホールに見に行ったな、、、リアムが途中で帰らないか心配だった。(と、懐メロにひたる)あ、上記の春樹氏は、ブラーのデーモンがやっているゴリラズが好きだと、以前エッセイで書かれてましたね。
というか、春樹氏は、世界中がご存じのとおり、翻訳書やエッセイだけでなく、小説にもいっぱい音楽が出てくる。『ノルウェイの森』や多崎つくるなどもありますが、やはり印象深いのは、『海辺のカフカ』でしょうか。プリンスとレイディオヘッドを愛する少年。
カフカくん同様、私も当時レディオヘッド(どうしてもこう書いてしまう)が大好きで、大阪市立中央体育館に来たときは二日間とも見に行ったりしたので感慨深い。
しかし、いまちらっと読み直すと、レイディオヘッドという表記より、それを聞くのがMDウォークマンというところに、懐かしさを感じる。カセットは意外にまだ生き残っているけれど、MDは絶滅したな……(でもまだMDコンポ持ってるけど)
あと、音楽が聞こえる本で外せないのは、松浦理英子の『ナチュラル・ウーマン』。
もちろんタイトルどおりの曲ですが、この本ではアレサ・フランクリンが歌っているけれど、私の頭のなかでは、キャロル・キングの歌になってしまう。
ほかにも、松浦理英子の小説ではブラック・ミュージックが頻繁に使われており、『裏ヴァージョン』では、かつての同級生が集まってカラオケに行き、Shirellsの「Will You Love Me Tomorrow」を歌いあげるシーンも印象的だった。
また、最新作の『最愛の子ども』では、高校生が文化祭でキーシャ・コールとパフ・ディディの「ラストナイト」を歌ったり、女性ロックバンドのランナウェイズによってある事実があかされたりする。
日本の作家というと、こないだ夏フェス情報を見ていたら、福島のオハラ☆ブレイクというフェスに伊坂幸太郎が出演するとなっていた。
いったいなにをするのだろう? たしか、伊坂幸太郎は以前にも斉藤和義とコラボレーションしていたので、せっちゃんも出演するのかな。ミュージシャンもめちゃ豪華なので(私の好みから)、関西ならぜひ行きたかった。
そういえば、今年のフジロックは、ノーベル文学賞のボブ・ディランが来るらしい。人生で一度は行きたいフジロック(←川柳風)ですが、やはり関西から遠い……
読書もいいけど、音楽もいい、なので、それが融合されたら(だいたいの場合)もっといい、って当たり前過ぎる結論が導かれつつありますが、BOOKMARK11号のエッセイで、金原さんがカート・ヴォネガット『国のない男』から引用している言葉が、すべてをあらわしていると思います。
彼にとって、神が存在することの証明は音楽ひとつで十分であった。
自分で自分の人生を選び取ることは可能なのか? 『ジャンプ』(佐藤正午 著)
あのときああしてさえいれば、ちがう人生になっていたかも――
あのときああしてさえいれば、ちがうひとと寄り添っていたのかも――
なんて思ったりすることはあるでしょうか?
いや、「やれたかも委員会」の話ではなく、佐藤正午の『鳩の撃退法』を読むまえに、まずは旧作の『ジャンプ』を読んでみたところ、まさに上に書いたようなことがテーマになっているので、こんなことが頭をよぎりました。
ごく普通の会社員である主人公「僕」(三谷)には、半年前からつきあいはじめたガールフレンド南雲みはるがいる。
三谷は出張の前日、羽田空港の近くに住むみはるのマンションに泊めてもらうことにするが、みはるの行きつけのバーで飲み過ぎて泥酔してしまう。そんな三谷を介抱しつつ、家まで連れてきたみはるは、「コンビニでりんご買ってくる」といって、そのまま姿を消す……
と、ミステリーの定番ネタともいえる失踪を扱った小説である。
といっても、それから殺人や誘拐などの事件がおきるわけではなく、三谷はみはるの姉と協力して探しはじめ、まずは警察にむかうが、警察は自発的な失踪者の捜索には消極的だ。なので、自分たちで聞きこみを行って、コンビニにむかってからのみはるの足取りをたどる。
みはるを追っていくうちに、中退した大学での友人たちや、生き別れになっていた父親にまで行きつく。みはるのことをなんにも知らなかったことを、三谷は痛感する。
それでも、いったいどこに行ったのか、どうして姿を消したのかはわからないまま、時間が過ぎる。
三谷は悩む。翌朝、酔いがさめて目を覚まし、みはるが部屋にいないことに気づいたときに、そのまま出張へむかうのではなく、出張を遅らせてでも、いっそキャンセルしてでもすぐに探していたら、みはるは僕のもとを去らなかったのではないか? と。
しかし、時すでに遅く、気づいたときには、みはるの勤務先には休職届が出されており、三谷はみはるを失う。いったいなにが運命の歯車を狂わせたのか?
一杯のカクテルがときには人の運命を変えることもある。
しかも皮肉なことに、カクテルを飲んだ本人ではなく、そばにいる人のほうの運命を大きく変えてしまう。
これは『格言』ではなく、個人的な教訓だ。
あるいはもっと控え目に、僕自身のいまの正直な思いだと言い替えてもいい。
この小説は、「自分で自分の人生を選び取る」「女性の意志」を描いたというキャッチコピーがつけられているが、まさにそのとおりだ。
先にも書いたように、みはるが姿を消したというだけで、ほかに事件らしいものはおきない。それなのに、主人公三谷の語りで長編をぐいぐいひっぱり、その語りに謎を――みはるが失踪したヒント――うまく潜ませ、最後の最後で「女性の意志」がなんだったのか判明するという仕掛けになっている。
ミステリーでは「信用できない語り手」という手法がよく使われるが、三谷が「信用できない男」だというのは読み進めるとすぐにわかるのだが、それがみはるの失踪とどう結びつくのかが肝となっている。
「自分で自分の人生を選び取る」ということは、どこまで可能なのだろうか?
主人公三谷は、最後の最後で、運命の歯車がくいちがっていたことに気づき愕然とするが、そもそも自分の意志だと思っていたことは、ほんとうに自分の意志なのだろうか? 自分で選択したと思っていたことは、ほんとうに自分で選択したのだろうか? そんなことを考えさせられる小説である。
気がついたときには女に去られていく男――という意味では、村上春樹の『女のいない男たち』に通じるものがあるのかもしれない。結局相手のことを、いや、自分のこともわかっていなかったゆえに、大切な(つもりだった)相手に去られてしまう男たち。
この文庫では、山本文緒が北上次郎の書評を引用しつつ解説を書いていて、それもまた読みごたえがある。
この物語を読んで、多くの男性読者が身につまされたり、反発を覚えたりしたようだ。
笑い事にしてはいけないが、やはりにんまりと笑いが漏れる。
平凡で優柔不断で鈍感な男を書いたら、今、佐藤正午が日本一ではないかと私は思っている。
「平凡で優柔不断で鈍感な」主人公三谷には共感できない、という読者も多いようだが、山本文緒は「自分で自分の人生を選び取った実感」をしっかり抱いているにもかかわらず、三谷にはつい共感してしまうと書いている。
というのも、自分の身のまわりにも失踪者がいるからだと、さらっと驚きの事実をあかしている。しかも、遠い知りあいなどではなく、前の夫らしい。前の夫は、山本文緒をはじめ、それまでの人生の知りあいと一切の連絡を絶って姿を消したとのこと。そんなことってあるんですね……
で、山本文緒の小説も昔から好きだったので、ひさびさに近作の『なぎさ』を読んでみたところ、これがまたおもしろかった――ってまた長くなりそうなので、『なぎさ』については次回に書きます。
不条理とユーモア、そして生と死が融合するエドガル・ケレットの世界 『あの素晴らしき七年』(秋元孝文 訳)『突然ノックの音が』(母袋夏生 訳)
自己嫌悪としてのユダヤ人としてのわが息子……
「もう十分じゃないかしら?」妻がぼくの妄想に割り込む。「可愛い可愛いあなたのボクちゃんに向けるヒステリックな非難を夢想するかわりに、なにか役に立つことをしたら? おむつを替えるとか」
「オッケー」とぼくは答える。「ちょうど終わりにしようとしてたところだから」
以前に紹介した『コドモノセカイ』で、エドガル・ケレットの『ブタを割る』『靴』を読んで、ほかの作品も読んでみたいと思っていたところ、『あの素晴らしき七年』の読書会が開かれたので参加してきました。
読書会には訳者の秋元孝文さんも参加され(イスラエルから帰ってこられたところだった)、ケレット愛あふれるお話をたっぷり聞かせてくださったので、たいへん充実した会になりました。
※まず最初に、このブログの文章については、本の感想はもちろん、読書会での意見にしても、すべて私の主観でまとめていることを明記しておきます。
エドガル・ケレットはイスラエルの人気作家であり、その掌編や短編小説は多くの国で翻訳されている。
『あの素晴らしき七年』は子どもが生まれてから、父親が癌で死ぬまでの七年を綴ったエッセイであるが、エッセイといっても、子育てほのぼのものでもなく、涙の闘病記でもなく、ふだんの日常に垣間見える違和感や不条理、ちょっとした喜びや悲しみ、家族や友人、まわりのひとたちとの関わりを軽妙に綴ったもので、短編小説と同じような味わいがある。
タクシーの運転手と大人げなく言いあいをして息子にとがめられたり、9/11後の混乱する飛行機でオーバーブッキングにあい、降りるようにいわれて思わず泣いてしまったり、しょっちゅう妻に叱られたりと、情けない自分の姿も隠すことなく、ときには自虐的なユーモアをまじえて描いていて、どの作品もたいへん親しみやすく身近に感じられるが、一方で、どの作品にも、いつテロや空襲にあうかわからない、常に戦時下にあるイスラエルの日常が反映されている。
「ちょっと聞いてもいい?」と三歳のロンの母親オーリットが何食わぬ顔で聞いてきた。「レヴ(作者の息子の名前)は大きくなったら兵役に就くのかしら?」
読書会でも、国家としてのイスラエルの政策には賛同できないという声もあった。
私は中東情勢について正しい知識を持っている自信はないけれど、たしかに報道を見る限り、イスラエルという国は、ユダヤ人がこれまで長く受けてきた迫害を、周囲の国に、民間人を含めた周囲の民族に、やり返しているような印象を受ける。
ただ、訳者の秋元さんがおっしゃっていた、「国家と個人は別」「どんな国でもそこでふつうに暮らしているひとたちがいる」というのは真実だと思う。
また、ケレット自身はイスラエルでは左派であり、イスラエルで左派であるということは、日本などの国で左派であることより、何倍もの勇気を要するらしい。
この本のあとがきでも、イスラエルのガザ侵攻で犠牲になったパレスチナの子どもに、ケレット夫妻が哀悼の意を示したため、自国民からバッシングされ脅迫まで受けたことが書かれている。
イスラエルにミサイルが落とされて、作者はこう書く、
ぼくらはもう一度、日々民間人を攻撃せざるを得ない占領国ではなく、自分たちの命のために戦う、敵国に囲まれた小さな国となれたのだ。
そしてこの本も、英訳版が決定版であり、「今現在はちょっと怖いしあまりに個人的」なため、イスラエルでヘブライ語版は出版されていない。
自国で出せないという事情は、ちょうど前々回紹介した、イラクのハサーン・ブラーシムの『死体展覧会』と重なる。
どちらも短編でありながら、戦争や死が身近にある日常が濃厚に描かれているというのも共通点だ。ヒューマニティの存在を疑うブラーシムと、あくまでヒューマニティに依拠するケレットとは、作風はまったく異なるけれども。でも、読むぶんにはどちらもおもしろいというのが、文学の不思議なところだ。
そして、この『あの素晴らしき七年』に書かれた、ケレットの家族の人生もたいへん興味深い。
準主役といえる妻(映像作家として活躍中)と息子のほかにも、作者にとってずっとヒーロー的存在だった兄は、反体制を貫いて、ついにはイスラエルを脱出してタイで活動家になり、姉は「亡き姉」として書かれるが、実際に死んだわけではなく、信仰に目覚め、正統派ユダヤ教徒として生きている。
両親はホロコーストの生き残りであり、ポーランドで生まれた母は、戦争で母親と弟を、ポーランド反乱で父親を亡くすが、ナチスに負けず、一家でひとりでも生き延びろという父親の遺言に従って、ポーランドの孤児院から、フランス、イスラエルへと渡る。
母のくだりでは、ちょうど先日読んだ、『父さんの手紙はぜんぶおぼえた』(タミ・シェム=トヴ 母袋夏生訳)を思いだした。
ナチスに侵攻されたオランダを舞台としたユダヤ人一家の物語で、高名な学者である父は、娘の名前をリーネケに変え(オランダ人らしい名前とのこと)、一家はばらばらになって協力者のもとに身を寄せる。見知らぬ土地でリーネケは、時おり届く父親からの絵入りの手紙を待ち続ける。
実話がもとになっており、本に挿入されている手紙もほんもので、びっくりするくらい上手で可愛らしいイラスト入りの文章から、父親の娘への深い愛情がうかがえる。
この一家はつらい思いをしながらも協力者に恵まれていたが、もっと悲惨な体験をしたユダヤ人が多くいることはいうまでもない。そしていま、先に書いたように、中東では紛争が続いている。悲惨の連鎖を終わらせることの困難さを思い知らされる。
しかし、こうやって書いていくと、どうしても深刻な話題に触れてしまうのだけど、ケレットの作品は、この『あの素晴らしき七年』にしても、短編作品集である『突然ノックの音が』にしても、戦争や死を背景にしながらも軽妙で、重苦しいものをまったく感じさせない。
『突然ノックの音が』には、銃口をつきつけられながら「話をしてくれ」と迫られる表題作や、嘘でいったことがほんとうに存在してしまう『嘘の国』といった、不条理、かつユーモラスな、ついひきこまれてしまう短編がたくさん収録されている。ぜひとも実際に読んで、独特の世界を味わってほしい。
「居場所もなかった」自分が「生命の喜び」を感じるまで 『猫道 単身転々小説集』(笙野頼子 著)
猫と出会ってこそ人間になった。人が家族のために頑張ることを理解し、人間がひとつ屋根の下で眠る事さえも、単なる不可解、不気味とは思わなくなった。猫といてこそ緊張があり、欲望が湧き、しかも常に夢中でなおかつ、闘争の根拠、実体を得た。
という前書きとタイトルにひかれて、笙野頼子の作品集『猫道 単身転々小説集』を手に取った。
十代から二十代にかけて、笙野頼子の作品をいくつか読んでいて、そのなかでも、この作品集にもおさめられている『居場所もなかった』と、『なにもしてない』(下の『三冠小説集』に収録されています)は強く印象に残っている。
『なにもしてない』は、社会から取り残され、まさに「なにもしてない」主人公が、「なにもしてない」のに手が腫れあがり七転八倒する物語で、ただそれだけといえばそれだけの話なのだけど、あふれだす過剰な自意識と、それを俯瞰して滑稽なまでに描いているのがなんだか痛快に思えた。
『居場所もなかった』では、主人公は家を探すがまったく受けいれられず、なんとか見つかったと思っても、保証人や印鑑証明といった高い壁が立ちはだかる。
ただひたすらに閉じこもるためにオートロックの家を望むが、単身でお金もなく、しかも勤め人でもない主人公には、オートロックとかの選択の余地などないのは言うまでもなく、ふつうに家を借りることすら困難なのだった。
そこまで難渋したのは、おそらくその時の私がひとつの病に取り憑かれていたからである。どこにも住みたくない。いや、どこも住みたくない。どこにも、の、に、を発音する余裕もないくらいに、まったく、どこも住みたくなかった。どこかに消えてしまいたいと思っていた。どこに行っても自分の居場所もなかったから。
若かりし頃の私は、これからちゃんと社会に出て働けるのだろうか? といった自分の不安やよるべなさと重ねあわせて、これらの小説を読んでいたのだろう。
そしていま『居場所もなかった』を読み返し、当時の自分が感じていた不安など、しょせん頭のなかの絵空事だったなとつくづく思いしらされた。いや、当時の自分が感じていた不安やよるべなさはリアルなものではあったけれど、なんせ自分で家を探したこともまったくなかったのだから、家を探す苦労などまったくの空想の産物だった。
物凄い世界の中に私は放り出されていた。不動産ワールド、と呼ぶべきだろうか、部屋探し地獄と言ったらいいのか。
「不動産ワールド」「部屋探し地獄」、よくわかる。
不動産屋に一歩足を踏み入れるやいなや、元気よく挨拶され、椅子とお茶を出されて、にこやかに「お探しの条件」について聞かれる。
どうしても値踏みされているような気になり、つい「こんな(高収入でもない)自分があれこれ条件をつけていいのだろうか……」と卑屈になる。
内見したらしたで、一目見たとたん「うわ~この家ないな」と内心思っても、即座に態度に出しては悪い気がして、「たしかに値段のわりに広いですね」など必死で「いいこと探し」をして、借りる気あるんだかないんだか曖昧な態度をとってしまう(私だけ?)。
しまいには、単身で保証人も両親しかいない自分の存在意義についてまで思いをはせてしまう。
が、しかし、喉元過ぎればなのか、引っ越して一年、いやほんの数か月程度でも、次こそはこういうところに住みたいなーと、性懲りもなく次の引っ越し先について考えはじめる。鳥頭というか、なにか脳の病なのでしょうか。
しかし、「なにもしてない」「居場所もなかった」、よるべない生活にも終わりがくる。作者にとっても、そして私にとっても。
冒頭の引用にあるとおり、「猫と出会ってこそ人間になった」のである。
あの時、何の「真意」もなく、「居場所もなかった」において私は言ってのけた。「そろそろ猫を飼おう」と言って引っ越したのだ。
(といっても、猫と暮らすために千葉で家を購入した作者とちがい、私の場合は「不動産ワールド」での彷徨は終わる気配はない、というか悪化しているが……こないだの引っ越しのときも、どれだけ「猫OKのマンションは、ほんと少ないんですよねー」と不動産屋に言われたことか)
まあ私のことはさておき、この本に収録されているのは「いわゆる猫話」――猫との暮らしはこんなに楽しい! とか、猫との生活を綴ったほのぼのエッセイ――などではなく、どれも切ないエピソードばかりである。
『こんな仕事はこれで終りにする』は、行方不明になった猫を必死で探す話であり、解説にもあるように、内田百閒の『ノラや』(全文引用したいくらいの、猫について語るには外せない本ですが)を想起させる。
『モイラの事』では、愛猫モイラの死について書いている。
郷里の法事も往復十時間で日帰りしていた。夜は一月に一、二回外出するだけだ。昼も仕事柄殆ど家にいた。…… 親にも友達にもろくに会わなかった。しかし私はモイラの死に目に会えなかった。
そう、猫(犬でもなんでも)と暮らすと、旅行は自由にできなくなるし、外出もままならない。そのうえ、往々にして別れは突然やってくる。
猫がよるべなく漂っていた自分をこの世につなぎとめていたはずなのに、あっさりと姿を消す。
動物と暮らすと、否が応でも、生きることや死ぬことについて幾度も直視せざるを得ない。それでも、作者が書いているように、この本は「猫といる幸福の本」なのである。
猫はただその本体自体が価値ある事を示し、生命の喜びに溢れてみせる。その事で人間を、人間性まるごとを徹底擁護する。
2018/02/18 柴田元幸×藤井光「死者たち」朗読&トーク@恵文社『死体展覧会』(ハサン・ブラーシム 著 藤井光 訳)
さて、先日京都の恵文社で行われたイベント、柴田元幸&藤井光「死者たち」のレポートを書いておきたいと思います。といっても、おふたりの話がちゃんと理解できたか、固有名詞などまちがえてないか、ちょっと心もとないですが、ご了承のほどお願いします。
第一部は朗読から。藤井さんが現在新訳しているという、スティーヴン・クレインの『The Red Badge of Courage』から。『世界文学大図鑑』(さまざまな小説を網羅していて、ほんと便利だ)から「赤い武功章』(1895年)スティーヴン・クレイン」の項を参照すると
アメリカ南北戦争を舞台として書いたものである。主人公ヘンリー・フレミングは北部連邦軍の若い二等兵だ。武功をあげることを夢見ていたが、実際の戦場で容赦のない戦闘の現実に直面したとき、南部連合軍の進軍を前に逃亡する
という物語。逃げた兵士を描くことで、戦争とはなにか、勇敢であるとはどういうことかを問うている。新訳はどこから出るんだろう? それにしても、レアード・ハントの『ネバー・ホーム』など、最近また南北戦争を描いた文学がブームですね。
そして柴田さんが朗読したのは、シリ・ハストヴェットの『食卓の幽霊たち』。シリ・ハストヴェットはポール・オースターの妻であり、自らも小説を書いていて、『目かくし』などの作品がある。

- 作者: シリハストヴェット,Siri Hustvedt,斎藤英治
- 出版社/メーカー: 白水社
- 発売日: 2000/04
- メディア: 単行本
- 購入: 2人 クリック: 28回
- この商品を含むブログ (6件) を見る
私も以前なにかのエッセイだったかを読んだことがあり、たしか男性につきまとわれるような内容で、作品世界の繊細さに強い印象を受けつつ、美人はたいへんやな~みたいな感想を抱いてしまった記憶がある。
今回の『食卓の幽霊たち』は、そういう話ではまったくなく、静物画をテーマにしたエッセイで、「不在の人間たち」――ひとはみな死ぬということ――について考察するものだった。
次は藤井さんによる、レベッカ・マカーイの『歌う女たち』の朗読。レベッカ・マカーイはハンガリー動乱の際にアメリカに移民してきた作家であり、この作品は、独裁者によって弾圧される世界で、死者たちの名前を口にして「嘆きと絶望の歌を歌う女たち」を描いている……のだが、寓話として語ることに語り手が疑問を呈するという構造になっている。
最後はまた、藤井さんによる朗読で、インド系作家カニシュク・タルーアによる『イスカンダルの鏡』。イスカンダル、つまりアレキサンドロス大王を描いた物語で(アレキサンドロス大王を描くのは塩野七生だけではないのだ)、不老不死を求めてアリストテレスに尋ねるアレキサンドロス大王に周囲が右往左往させられるという、なかなかユーモラスな話だった。
そのあとは、おふたりによるトーク。まずは柴田さんが、藤井さんが朗読した三作について質問。
共通項のようなものとして言えるのは、三作ともその主題と距離をおいて描いているということだった。
スティーヴン・クレインは南北戦争のあとに生まれているので、戦争体験はまったくなく、戦争自体も、功をあげようと思いつつ臆病な主人公の内面における自己正当化も突き放して描いているとのこと。
マカーイも、語り手が顔を出すことによって客観性が生じている。
タルーワは、アメリカでもインドでもないアレクサンドロス大王をテーマにするのも唐突な感じがあるが、宇宙ステーションを題材にしている作品すらあるらしく、いま住んでいる「アメリカ」を描くわけでもなく、かといって自分のルーツがある土地に重きをおくわけでもない感覚が、少し前までの移民系作家(ジュノ・ディアスなど)と異なる点とのこと。"ホーム"が抽象的なものに変化しつつある、と。
それから、今回のイベントの主題でもある、藤井さんが訳したハサン・ブラーシムの『死体展覧会』について。
この本の解説によると、ブラーシムはイラクのバグダッド生まれで映像作家で働いていたが、政府の圧力によって身の危険を感じ、2000年に出国し、現在はスウェーデンで創作活動を行っているとのこと。
私もいまこの本を読んでいるけれど、タイトルからわかるように、死や暴力が非常に生々しく描かれている。そのため、アラビア語圏では、ブラーシムの作品は発禁扱いとなっている。この日の話によると、アラビア語圏の文学界では、いまだ美しい韻文調の作品が主流らしく、ミステリーやSFですらめったに見られないらしい。
湾岸戦争後の自国でのおそろしい弾圧を目の当たりにしたブラーシムの作品は、人間であることの意味やヒューマニティの存在を根源から疑うものである、とのこと。
そしてもちろん、「アメリカ」についての話も続きました。「9・11のあとで戦争を描くとはどういうことか」と『闇の中の男』『プロット・アゲンスト・アメリカ』をあげ、『プロット~』はブッシュ政権への怒りがテーマになっているが、いまはそれよりも悪い政権だしね……という柴田さんの嘆き。
ポーや、ホーソーン、メルヴィルの時代から現代まで、戦争、そして生者と死者についての「当事者性」の問題や、「生と死の境界線はあるのか?」ということについてトークが展開しました。もちろん、どの観点についても、ポー、ホーソーンとメルヴィル、そしてフォークナーと、作家によってそれぞれ立ち位置はちがうのですが。
あと、「どうして最近(のアメリカ文学)は家族の話ばっかりになったんだろうね?」という疑問も興味深かった。
たしかに、以前に紹介した『コレクションズ』なんて典型的だが、たしかに、最近のアメリカ文学は家族病に憑かれている傾向があるように思える。藤井さんは「(先程の話から続いて)いわゆる”ホーム”と呼べる場所が失われ、家族だけが”ホーム”になったからではないか」と言われていました。
と、文学についてならいくらでも語ることがある……という感じで、あっという間に時間が過ぎていきました。またどこかでお話を伺いたいものです。
名古屋で犬三昧 『その犬の歩むところ』『約束』読書会&はしもとみお『木彫り動物美術館』
というと、なんだか犬を食したようですが、そうではなく、以前紹介した『その犬の歩むところ』といった”犬本”をテーマにした読書会が名古屋で開かれたので、日帰りで参加してきました。
まずは、読書会の前にも犬を補給しようと、新栄のヤマザキマザック美術館に行き、はしもとみおの『木彫り動物美術館』展を鑑賞。何号か前のTVブロスで、山内マリコが紹介していて気になっていました。


はしもとさんは三重県在住の彫刻家で、写真のとおり動物を題材に制作していて、愛犬月くんや、ここ数年通っている相島の野良猫たちや、動物園のゴリラ、砂漠のラクダなどが、ほんとうにいきいきと愛情深く彫られていた。動物も美術も好き!という方は必見。といっても、今週末までのようですが。
そして、名古屋駅でさまよいながらもなんとか読書会に到着。
”犬本”として『その犬の歩むところ』と『約束』の二冊が課題書となっていて、どちらかの班に参加するシステム。私は『その犬の歩むところ』班に参加。
『その犬の歩むところ』は、アメリカの片田舎のモーテルで生まれたギヴという犬の歩みに、現在のアメリカが映し出される物語である。
レジュメとして、ギヴや登場人物たちの旅路が記されたアメリカの地図が用意されていて、ギヴも登場人物たちもあの広いアメリカを大移動していることが、あらためて理解できた。
とくに、ギヴをモーテルから盗む兄弟がシアトル出身で、その弟イアンとギヴを介して出会うルーシーがフロリダ出身ということから、アメリカの端と端をギヴという犬でつなぐ構造にしているのだとわかった。
この物語では、カトリーナに9・11、イラク戦争が登場人物たちの運命を大きく変え、随所にケネディ暗殺やミシシッピ川~ハックルベリー・フィンなどに言及しており、アメリカを描くことを作者が強く意識していたのはあきらかだが、もちろん単純なアメリカ礼賛の物語ではない。
この本でもハリケーン・カトリーナでの大統領の無策ぶりをあてこすっていたり、作者ボストン・テランは覆面作家なので、ジョイス・キャロル・オーツのように激しく発言しているわけではないが、きっといまは現大統領を支持している側ではないだろう。
それでもなお、ルーシーがギヴを乗せてドライブしていて出会う、ビーチ・ボーイズの『ファン、ファン、ファン』の女性バンドのカバー(担当編集の方によると、ジョーン・ジェットによるカバーとのこと)をガンガンにかけながらハーレーに乗る女性ライダー軍団の姿に象徴される、「よきアメリカ」――いまは失われつつあるのかもしれない――を、あえてこの時代に描こうとしたのだと思った。
ひととおり班での討議が終わったあとは、『約束』班へのプレゼン大会へ。
ちなみに、『約束』はまだ読み終えていないけれど、前作『容疑者』は、マクドナルドでポテトを食べながら(時おり無性に食べたくなる)冒頭のシーンを読んで、思わず泣いてしまった。
こっちの犬マギーは海兵隊で優秀に働いていたが、中東の戦争でパートナーを失い(ここが『容疑者』の冒頭のシーン)、同じくパートナーを失ったばかりの警察官スコットのもとに引き取られる。
プレゼン大会では、「野良の子のギヴとちがって、マギーは海兵隊のエリート」とか「いや、犬がしゃべるなんて邪道だ」(マギーは内面の語りがあるのです)とディスリあい(もちろん冗談です)がありながらも、どちらも「よきアメリカ」を取り戻そうとする話だと結論がまとまった。
あと、それぞれがオススメの ”犬ミステリー” を紹介するという企画もあった。私は『容疑者』の解説で紹介されていた『さらば甘き口づけ』を紹介した。
私立探偵スルーが、アル中作家トラハーンを探すようトラハーンの元妻から依頼され、ようやく酒場で見つけたら、今度はその酒場の女主人から行方不明になった娘を探してほしいと頼まれ……という物語。
スルーとトラハーンがアメリカ西部を動き回るロードムービーの要素もあり、女優志望の若い女が失踪するというのは、以前紹介した『ハティの最期の舞台』にも共通する思春期ものの定番でもあり、そしてチャンドラーから流れる悪女(ファム・ファタール)ものでもあり、とお得な一冊(?)だと言ってみました。
それにしても、スルーもトラハーンも、そしてお供の犬ファイアボールもずうっと酔っぱらっているのだ。ギヴもビールが好きだし、犬ってそんなにビールが好きなのか?
ほかには『BUTTER』が紹介されていて、木嶋佳苗事件がモチーフらしいので以前から気になっていたが、犬が出ていたとは知らなかった……いや、たしか木嶋佳苗はブリーダーに関わっていたはずなので意外ではないか。
『野生の呼び声』など、そんなにミステリーっぽくないものも紹介されていたので、それなら前に書いた『おやすみ、リリー』とか『ティモレオン』とか、再読しようと思っている『ティンブクトゥ』でもよかったかもしれない。

- 作者: ポールオースター,Paul Auster,柴田元幸
- 出版社/メーカー: 新潮社
- 発売日: 2010/06/29
- メディア: 文庫
- 購入: 2人 クリック: 24回
- この商品を含むブログ (16件) を見る
そんなわけで、名古屋日帰り旅、充実した一日を過ごせました。またどこかに行きたいな。
ほんとうは自分のためのブックガイド 『10代のためのYAブックガイド150! 2』(監修:金原瑞人/ひこ・田中)トークショー
『10代のためのYAブックガイド150! 2』の出版記念トークショー(梅田のMARUZEN&ジュンク堂)に行ってきました。

今すぐ読みたい! 10代のためのYAブックガイド150! 2
- 作者: 金原瑞人,ひこ・田中
- 出版社/メーカー: ポプラ社
- 発売日: 2017/11/16
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る
といっても、もちろん10代ではないし、子どもがいるわけでもない。きょうだいがいないので甥や姪もなく、子どもと接する機会は皆無。
しかも、ふだんは殺したり殺されたりする物騒な本を読むことが多く、はてはアルツハイマーの殺人犯だとか落ちこぼれのスパイだとか言い出す始末。なので、「お呼びでない」とうすうす感じつつも、でも聞くんだよ!(←根本敬)と参加して参りました。
この『10代のためのYAブックガイド150!2』では、監修者である翻訳家の金原瑞人さんと、児童文学作家のひこ・田中さんを筆頭に、書評家の豊崎由美さんや瀧井朝世さんなど、総勢27人の多彩な「本のプロ」が、10代にぜひ読んでほしい本を紹介している。
すべて2011年以降に出版されたフレッシュな本から選ばれていて、以前にここで紹介した『エレナーとパーク』、『ペーパーボーイ』『こびとが打ち上げた小さなボール』も入っている。
この日のトークショーは、監修のおふたりのほかに、選者である書店員の兼森理恵さん、社会学者の佐倉智美さん、大阪国際児童文学館の土居安子さん、学校図書館司書の右田ユミさん、大学准教授の目黒強さんも登壇され、まずは全員が自分が選んだ本のなかから、とっておきの「イチオシ本」を紹介。
トップバッターのひこ・田中さんが、ヤングアダルトとは ”じたばた”する世代だと、冒頭からヤングアダルトの肝を語り、『シタとロット ふたりの秘密』を紹介した。
スペインを舞台に、シタとロットというふたりの14歳の女の子が、女らしくなっていく身体に戸惑い、理性では抑えられない恋愛に直面し、セックスに悩むという物語とのこと。やはり向こうの女子は大人やな~とつい遠い目になってしまうが、自分の中学時代を思い出しても、14歳というのは、いわゆる「おとなの階段」を登りはじめる子と、足踏みをしてしまう子と差がついて、それまで仲良かった友達同士の関係も変わってしまう時期である。
金原瑞人さんは、三秋縋の『恋する寄生虫』。読みはじめたら止まらなくなり、その日のうちに三秋縋の作品を一気に四冊読んでしまったとのこと。
主人公の高坂賢吾は「他人に触れられただけで拒絶反応を起こす重度の潔癖症」の27歳の引きこもりで、ひょんなことから一回り年下の佐藤ひじりという「金髪、ピアス、タバコ、寄生虫疾患の本好き」で「人と目を合わせることができない視線恐怖症」の少女と出会う。やがてふたりは惹かれ合う……と、これだけでもじゅうぶん物語が成立するように思うが、ここから意外な方向へ進む。
ふたりの体内には同じ寄生虫が宿っていて、そのせいで惹かれ合っていることが判明するのだ。駆除しないと命が奪われるが、駆除すると恋が終わるかもしれない。この想像を絶する展開の先が非常に気になるので、ぜひとも読んでみたい。
ほかにとくに気になったのは、佐倉智美さんが紹介した、武田綾乃の『響け! ユーフォニアム』。
私は知らなかったけれど、アニメにもなっている大人気作品のようなので、ご存じの方も多いのではないでしょうか。
京都の北宇治高校で吹奏楽にうちこむ、黄前久美子と高坂麗奈というふたりの少女の青春物語。と書くと、ものすごくベタでありがちな話のように感じてしまうけれど、
物語の主軸は、それ(異性との恋愛)と両立する形で久美子と麗奈の二人の間に紡がれていく深くも強い親密性のほうに置かれている。女どうしの絆と異性愛、どちらかが優越するという発想はそこにない。互いの存在が互いを変えて世界を広げる。
だいいち「異性」か「同性」か、「恋愛」か「友情」か、その区分がそんなにも「好き」にとって大事なのか、そもそも区分できるのか
とあり、先日紹介した松浦理英子の『最愛の子ども』にも通じる物語のようで、かなり読んでみたくなった。吹奏楽部を舞台にしているが、昔ながらのスポ根(吹奏楽だけど)ものでもなく、昨今話題の「ブラック部活」問題も視野に入れているとのこと。
あと、土居安子さんが紹介した絵本『夏のルール』。ひと夏の兄と弟の物語。
土居さんもおっしゃっていたように、ショーン・タンというと、『アライバル』のような静謐な世界という印象が強いけれど、こんなに色鮮やかで心躍る絵本も描いていたのだ。
そう、子どものころは、夏休みは特別な時間だった。日常とは異なるルールに支配される時間。……まあもちろん、会社に行っている現在も、有休というとても大事な特別な時間なのですが。
イチオシ本の紹介が終わると、YA世代に本を薦めることについてのトークがはじまった。「中学生は忙しい」問題(一日六時間の授業、強制的に加入させられる部活、それから塾)は、心の底から納得した。勉強のために、「本断ち」せざるを得ないこともあるらしい。
また、目黒強さんが、”ナロー小説”と発言されたとき、narrow?? と思ったが、そうではなくて、「小説家になろう」というサイトがあって、そこから生まれる「なろう小説」が人気とのことだった……って、こんな説明不要でしょう。きっと私以外の全員が知っているはず。
たしかに、YA世代である10代が、このブックガイドをきっかけにさまざまな本を読みはじめたら、ほんとうにすばらしい。そうあってほしいと願う。
けれども、正直なところ、身近に子どものいない私にとっては、この本は見も知らぬ子どものためのものではなくて、自分のためのブックガイドだとあらためて感じた。できることなら、いまの私から、10代の頃の私に渡せてあげたら一番いいと思う。
当時は「ヤングアダルト」という分類はなかったけれど(しかし、「ヤングアダルト招待席」の連載が1987年からということは、あったのだろうか?)、氷室冴子の小説や、いくえみ綾のマンガに夢中になっていた自分に(映画『プリンシパル』は少し気になっています)。
でも考えてみると、いまも当時となにひとつ変わっていない。図書館に通っていた10代の私は、いまも自分のなかにいる。
そこで、そんな私が上記にあげた本以外に、このブックガイドでとくに気になった本をあげてみると――
『堆塵館』や『あたらしい名前』など、以前から「読まねばリスト」に入っているものは除外して、また、山下賢二『ガケ書房の頃』や、文月悠光『洗礼ダイアリー』など、以前からエッセイを読んでおもしろいと思っていたものも除外して
(けど、『洗礼ダイアリー』の推薦文にも書かれていますが、「若い女性詩人」に対するおっさんたちの視線が香ばしいですな)、
まずは阿川せんりの『厭世マニュアル』。
小学校の頃に「口裂け女」とからかわれ、人前でマスクが外せなくなった22歳女子の物語。
というと、なにか心温まる出会いとか恋愛をきっかけに、マスクを外して他人と接することができるようになる、というのが常套の展開だと思うが、推薦文を読むと、そうではなさそうなところに興味をもった。他人と協調することって、ほんとうに必要なの? と追究しているらしい。読んでみたい。
次はオーストラリアの小説『わたしはイザベル』。 親に虐げられて育った少女の物語。
作者エイミー・ウィッティングがこの話を書きあげたのは1979年らしいが、「実の子どもにこんなにつらく当たる母親がいるはずがない」と刊行されなかったらしい。まだ母親神話が強固な時代だったのだろう。
それから十年後に出版されると、たちまちベストセラーになったとのこと。「残念なことに」こういう話は珍しいものではないと判明したのだ。そして、毒親という言葉が当たり前になったいま、まさに読まれるべき本ではないだろうか。
最後は、佐野洋子の『親愛なるミスタ崔』。

親愛なるミスタ崔: 隣の国の友への手紙 (日韓同時代人の対話シリーズ)
- 作者: 佐野洋子,崔禎鎬,吉川凪
- 出版社/メーカー: クオン
- 発売日: 2017/03/20
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る
『100万回生きたねこ』や『おじさんのかさ』といった絵本や、ちょっと辛辣でユーモラスなエッセイは読んでいたけれど、こんな手紙を集めた本があるとは知らなかった。
それもただの書簡集ではない。長年にわたって送り続けた、熱烈なラブレターなのだ。「憧れの人に自分を知ってほしい(過去も現在も未来も全部)という女の子の気持ちがぎゅうぎゅうに詰まっている」本とのこと。たしかに「おもしろくないはずがない」だろう。
と、この本は、だれにとっても、何歳のひとであっても、自分のためのブックガイドとして使うことができると思うので(本来の意図に反するかもしれないが)、10代でなくても、YA世代となんの関係がなくても、手に取って、気になった本を読むと、あの頃の自分に出会えるかもしれません。



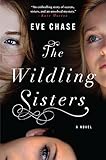






















![響け!ユーフォニアム(宝島社文庫)1-4巻 セット [文庫] [May 25, 2015] 武田 綾乃 [文庫] [May 25, 2015] 武田 綾乃... [文庫] [May 25, 2015] 武田 綾乃 [文庫] [May 25, 2015] 武田 綾乃 響け!ユーフォニアム(宝島社文庫)1-4巻 セット [文庫] [May 25, 2015] 武田 綾乃 [文庫] [May 25, 2015] 武田 綾乃... [文庫] [May 25, 2015] 武田 綾乃 [文庫] [May 25, 2015] 武田 綾乃](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/515TT7FssTL._SL160_.jpg)


