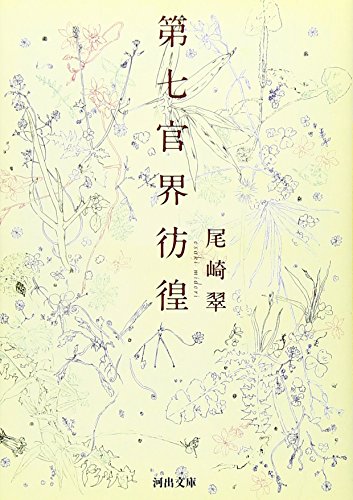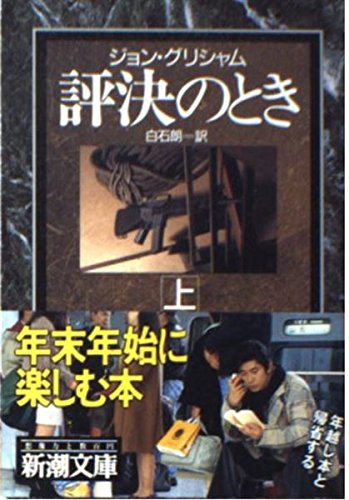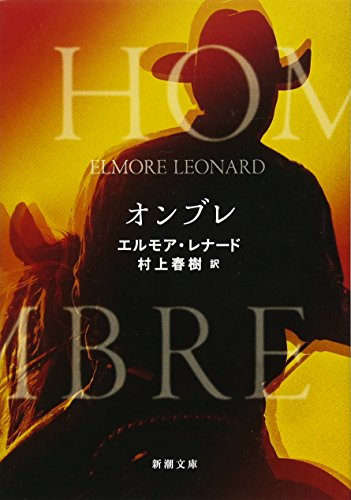三十年経ったいま、不思議な軽やかさを持ったフェミニズム小説として読めた『後宮小説』(酒見賢一)
『後宮小説』は、1989年に日本ファンタジーノベル大賞第一回受賞作品に選ばれて大きな話題となり、のちに『雲のように風のように』という題でアニメ化もされている。小説は読んでいなくても、アニメは見たことあるという方も多いのではないでしょうか。
このときの日本ファンタジーノベル大賞の選考委員は、荒俣宏、安野光雅、井上ひさし、高橋源一郎、矢川澄子という豪華な顔ぶれで(ほんとうは手塚治虫も入っていたが、急逝したため、残りの5人で審査したらしい)、井上ひさしによる「シンデレラと三国志と金瓶梅とラストエンペラー」という評のとおり、中国をモデルにしたと思われる架空の王国でくり広げられる壮大な艶笑法螺話だ。恩田陸がこの小説を読んで作家になることを決めたというのも、有名な逸話らしい。
念のため、後宮とは何かというと、「天子の宮中の奥深い部分の意味で、江戸の大奥、イスラム世界のハレムに類似する」(日本大百科全書(ニッポニカ)より)で、つまりは皇帝の世継ぎを生むための女たち(夫人)が待機しているところ、である(たぶん)。
言うまでもなく、後宮にしろ大奥にしろハレムにしろ、フェミニズムの視点を持つ現代の読者に受け入れてもらうためには、なんらかの仕掛けを必要とする。(よしながふみの『大奥』がいい例ですが)
では、このバブル真っ盛りの時代に書かれた『後宮小説』は、どのように描いているのかというと……という観点から、以下のように書評を書きました。
**************************************
(題)子宮からの解放
『後宮小説』は、田舎育ちの少女銀河が素乾城の後宮に入るところからはじまる。銀河は後宮がどういうところかもほとんど理解していないにもかかわらず、後宮へ続くトンネルを通るとき――狭くて暗く、膣口を連想させる――自分でも理由がわからないほどに取り乱す。そして同じく宮女候補である高慢なセシャーミン、やたらと無口な江葉とともに、角先生による「女大学」の講義を受ける。
この講義で印象深いのは、真理とは何か? という問いだ。角先生は、すべての真理は子宮から生まれてくると論じる。子宮を模した後宮に「女大学」、さらに真理は子宮に宿るといった論調は、現代のフェミニズムの視点で考えると違和感を覚える。
銀河は皇帝双槐樹の正妃に選ばれるが、すぐさま素乾城が危機に陥る。角先生の弟子である菊凶の陰謀のもと、幻影達率いる幻軍が襲ってきたのだ。銀河は後宮軍隊を設立し、つねに冷静沈着な江葉を将軍に命じる。江葉はめざましい軍才を発揮し、意外なことにセシャーミンまでもが軍隊に志願する。女たちが生きのびるために連帯して、敵と戦う。ここで『後宮小説』は、突如としてシスターフッド小説に変貌する。
「呆れるほど楽しそう」に戦う銀河や江葉と比べて、男たちはいとも簡単に死んでいく。菊凶はあっさり斬られ、角先生は馬車の中で息を引き取り、双槐樹すらも銀河に子を孕ませるやいなや毒杯で命を落とす。まるで昆虫のようだ。冒頭から房事に焦点をあてていたにもかかわらず、肝心の銀河と双槐樹の交わりの場面はいともあっけなく終わる。それよりも銀河が自ら江葉に接吻をするときの方が、甘やかな官能性が感じられる。
素乾朝と素乾後宮は滅びる。『後宮小説』とは、後宮が滅びる物語であったのだ。つまりこの小説は、女たちが子宮を模した後宮から解放される物語だとも言える。前半で生じた違和感がここで解消される。
後日談として記されている、銀河が初期の女権論者であるリヒトシトリ侯爵夫人であるという説からも、フェミニズムを意識していることがわかる。後宮を滅ぼす糸を引いた菊凶が、真理は子宮に宿るという後宮哲学を唱えた角先生の愛弟子であることも象徴的だ。後宮に入るときにあれだけ脅えた銀河が、後宮を出てから各地を飛び回って伝説を作る。たしかに真理は子宮に宿るのかもしれないが、子宮から解放されるときに真理が目覚めるのではないだろうか。
*************************************
こう書いたあとで気づいたけれど、「子宮からの解放」というテーマ、というか結論になってしまったのは、松浦理英子『優しい去勢のために』で書かれていた「性器からの解放」が念頭にあったのかもしれない。
しかし上のような評を読むと、『後宮小説』は、最近多いフェミニズム小説の先駆けだったのかという印象を抱くかもしれないが、『後宮小説』の大きな魅力は、どこまで嘘か誠かわからない法螺話を大仰に語る、人を喰った語り口のおもしろさだと思う。この物語の冒頭を引用すると――
腹上死であった、と記載されている。
腹英三十四年、現代の暦で見れば一六〇七年のことである。
歴史書というものは当時の人間が書くものではなく、後代の人間が書くものである。更に言えば次の王朝の士官が書くのが通例である。よって、この歴史書の筆者は王の腹上死を実際に目撃したわけではないし、直接に調査し得たわけでもない。
と、語り手が歴史書を参照しながら語るスタイルになっていて、谷崎潤一郎『春琴抄』を引きあいに出した書評を書いた人もいた。でっちあげの歴史書という点では、たしかに似ている。
しかし奇妙な愛憎劇を描いた『春琴抄』とはちがい、擬史という技法をふんだんに活かして荒唐無稽な架空の国を作り上げて、最後に爽快にぶっ壊し、後日談やあとがきすらも読者を翻弄させる文体を徹底した『後宮小説』には、高橋源一郎が「重力の軛を逃れて浮遊している」「軽さ」と評しているとおり、不思議な軽やかさがある。
そこが三十年経ったいまでも楽しく読める秘訣でもあり、たしかに新人のデビュー作としては破格のものであっただろうと、今回はじめて読んでつくづく感じた。
人生に勝者や敗者なんて存在するのか? デイヴィッド・ベニオフ『25時』~『99999』(田口俊樹訳)
デイヴィッド・ベニオフの短編集『99999』(ナインズ)を読みました。
デイヴィッド・ベニオフは、第二次世界大戦時のロシアで生きのびようとする青年たちを描いた『卵をめぐる祖父の戦争』で高く評価され、さらに小説のみならず、『ゲーム・オブ・スローンズ』の脚本家としても華々しい成功をおさめ、まさに現代を代表する才人と言っても過言ではない。
この短編集『99999』は、生まれ故郷ニューヨークを舞台としたデビュー作『25時』と『卵をめぐる祖父の戦争』のあいだに発表された短編集であり、この二作の橋渡しとなる一冊だ。
デイヴィッド・ベニオフの小説では、「現実をうまく生き抜いている者」と「不器用で失敗ばかりしている者」が対照的に描かれている。何もかも手に入れた前者が「勝ち組」で、何ひとつ手に入れられない後者が「負け組」なのだろうが、勝ち負けは絶対的なものではなく、その時々で入れかわる。そこがベニオフの小説が持つ独特の哀感である。
『25時』の主人公のモンティは、だれからも愛されるハンサムな白人男性であり、軽い気持ちで手を染めた麻薬売買で莫大な金を手に入れ、可愛い恋人と優雅に暮らしている。一方、その友人ジェイコブは冴えない高校教師で、金にも恋愛にも恵まれず、教え子に対してつい妄想を抱いてしまう自分を心の中で罰している。もうひとりの友人スラッタリ―は金融業で成功をおさめているが、かなわぬ思いを胸に秘めている。
そんなモンティがついに警察に捕まり、刑務所に送られる前日を追っているのが、この『25時』である。「だれからも愛されるハンサムな白人男性」という手札は、刑務所であっても有効だ。つまり、刑務所でモンティを待ち受けているものは……といっても、モンティがどうやってこの危機から脱出するのかを描いたサスペンス小説ではない。(モンティを陥れた人物は明かされるが)
収監の日を前にしたモンティとスラッタリー、そしてジェイコブの心情に焦点が置かれている。どうしてこんなことになってしまったのか受けいれられない――北上次郎さんの解説では「青春の悔悟」と表現されている――モンティ、これまで華やかな中心人物だったモンティの運命が一変して、どうふるまったらいいのか戸惑うジェイコブとスラッタリー。三人が最後に示す「友情の証」とは……?
ちなみに、この小説はおもに主人公モンティの視点から描かれているが、ジェイコブを中心にしたパートの方が読んでいておもしろく、ジェイコブの教え子の女子高生や教師仲間の姿がいきいきと描写されている。
作者も「イケてる」人物より、悶々とした「イケてない」人物に語らせる方に手ごたえを感じたのはないだろうか。『卵をめぐる祖父の戦争』では、女の子への妄想で頭がいっぱいのレフを語り手とすることで、戦争の悲惨さを容赦なく暴きつつも、人間という存在を愛すべきものとして捉えることに成功している。
そして、この短編集『99999』の表題作「99999」は、インディーズのロックシーンを舞台とし、シビアな音楽業界を生き抜いてきた敏腕スカウトマンのタバシュニクと、ニューヨーク郊外で両親や仲間と暮らし、愛犬の名前をタトゥーにするパンクロッカー〝サッドジョー〟が対照的に描かれている。どちらが「勝ち組」で、どちらが「負け組」なのかは言うまでもない。
少年院に入れられた仲間と一緒になるために、シェルのガソリンスタンドのSの字を撃つような人間がもしいるとしたら、サッドジョーがそれだ、と。
けれども「99999」でも、『25時』での三人のぶつかり合いと同様に、タバシュニクとサッドジョーが対峙したあと、タバシュニクがほんとうに勝ったのだろうか? という逡巡と、ほろ苦い「悔悟」が胸を襲う。人生において、勝者なんてほんとうに存在するのだろうか? このやるせなさが短編集『99999』を貫くトーンだ。
どこまでが現実で、どこまでが語り手の妄想なのか判別しがたい「獣化妄想」も、対照が効果的に使われている。
ライオンをもやっつける(比喩ではない)屈強なハンターである父のもとで暮らす主人公「ぼく」は、ライオンになる夢想を頭のなかで思いめぐらせながら、フリック美術館に通う日々を送っている。そんなある日、いつものようにフリック美術館で聖フランシスの彫像に見入っている主人公の前に、「すべての女の恋人(ラヴァ―)」と名乗る男プチコがあらわれ、ふたりは美術館をうろつくライオンを目撃する……。
永遠に清らかな聖フランシスに自らを重ね合わせる内向的な主人公が抱く獣性への憧憬が、ライオン、そしてプチコという形をとったと考えられる。
〝逡巡と悔悟〟というテーマがもっとも強くあらわれているのが、「幸せの裸足の少女」だ。
フットボール選手であった16歳の主人公は、気まぐれに友人の父親の車を勝手に乗り回して、ニュージャージーからペンシルヴェニアに向かう。えんえんと続く緑の畑のなか、裸足で自転車に乗る少女に出会う。彼女を助手席に乗せ、たわいもない話をして、一緒にチョコレートを食べる。たったそれだけの話。
私にとっては人生で初めてのいいキスだった。彼女の唇はチョコレートの味がし、キスしおえると、彼女はショートパンツの尻のポケットからたたんだキャンディ・バーの包み紙を取り出して、私に手渡した。開くと、中に彼女の名前と電話番号が書いてあった。
けれども、その後主人公は彼女に電話をすることができなかった。あの幸せだった午後の思い出を壊してしまうことが怖かったのだ。
14年後、フットボールから心が離れてしまった主人公は、もうひとつ大事にしていたものを取り戻そうと、あの時と同じようにクラッシュの「ロンドン・コーリング」を聞きながら、彼女を探しに車を走らせるが……
「悪魔がオレホヴォにやってくる」は、チェチェン戦争に駆り出されたロシア兵を主人公とし、『卵をめぐる祖父の戦争』につながる作品である。
新米兵士である主人公レクシは、ふたりの古参兵とともにチェチェンへの雪深い山道を進んでいる。軍隊に入ることは昔からの憧れだった。まわりの女の子たちもみんな、銃を持って制服を着た兵士たちに夢中になっていた。
ところが、こうして見渡すかぎり雪だらけの道を歩いていると、こんなことに意味があるのか? と疑問がわいてくる。古参兵ニコライはこんなことを言う。
おれたちがやってることにはなんの意味もないんだよ。これはゲームさ。ほんとうのこと知りたいか? モスクワにしてみりゃ、おれたちが死んだほうがいいのさ。
古参兵たちは〝モスクワ〟という言葉にありったけの悪意と呪詛をこめて発音する。
そして三人は小屋に隠れていたひとりの老婆を見つける。古参兵たちはレクシにその老婆を撃つように命じる――
とくに印象深かった短編3つを紹介したが、そのほかにも、世界の終わりをアイロニーたっぷりに描いた「分・解」、〝ノー〟と拒絶され続けてきた女優志望の主人公が最後に手にした〝イエス〟とは? が明かされる「ノーの庭」、主人公が別れた恋人の父親の遺灰とともに赤いレーシング・カーを走らせる「ネヴァーシンク貯水池」など、突飛な状況でありながら、登場人物の心情に思わず寄り添ってしまう物語が綴られている。
主人公が飛行機のなかで大便を垂れ流す場面からはじまる「幸運の排泄物」も、突飛な状況という点においては屈指と言えるだろう。奇跡のような美しい肉体を持つダンサーであるヘクターと絵描きの「ぼく」の恋愛が、どうして大便、排泄物に至るのか?
「ぼく」が本番を前にしたヘクターに「幸運を祈る」と言うと、ヘクターはダンサーにはそんな言葉は不要だと告げ、かわりに〝排泄物〟(Merde)と言うように頼む。〝排泄物〟は幸運と表裏一体のものなのだろうか?〝排泄物〟は美しい恋愛と過酷な現実を結びつけるものでもあり、象徴するものでもある。ベニオフの得意とする対照が究極の形であらわれている。
……それにしても、冒頭の場面の飛行機には乗り合わせたくないものだと、思わずにはいられなかったが。
さて、『ゲーム・オブ・スローンズ』の次は『三体』のドラマ化に取り掛かっているらしい(Wikipedia情報)デイヴィッド・ベニオフですが、小説の次作はいつになるのか? これだけ多才な人物なので、まだまだ先になるかもしれないけれど、首を長くして待ち続けようと思います。
「人種」というありもしないもので選別される命 梁英聖『レイシズムとは何か』
さて、800字書評講座の今月の課題書は、梁英聖『レイシズムとは何か』でした。
『レイシズムとは何か』では、まず冒頭の章で「レイシズム」の歴史を振り返り、近代以前からあった異民族への嫌悪や忌避と、近代以降の「人種」差別がどう異なるのかを考察している。
この本では、16世紀の異端審問期のスペインにおいて、ユダヤ民族を差別するために成立した純血法が、近代以降の「人種」差別の起点になったと考えている。17世紀後半には、北米で奴隷制とレイシズムが結びついて黒人も差別される対象となり、18世紀には、「分類学の父」として有名なリンネがヒトを4つに分類したことで、「人種」というものがはじめて科学に持ちこまれた。
19世紀以降、帝国主義と資本主義の発展にともなって、「人種」差別が世界中に広がり、ナチスのホロコーストという悲劇を生んだにもかかわらず、なおも「人種」差別は根絶することはなく、いまもなおBLM(ブラック・ライブズ・マター)運動が続いている。
では、いったい「人種」とは何なのだろうか? 「レイシズム」の定義とは? そして、「日本に人種差別はない」のだろうか?
――について、まず私が提出した800字書評を転載します。
************************************
題:「人種差別を許してはいけないとあらためて思いました」?
『レイシズムとは何か』の書評を書くのは非常に難しい。
この本では、レイシズムとは「ありもしない人種をつくりだし」、つまり「人種化」することで、「生きるべき者/死ぬべき者」を分けるものだと定義している。その選別によって、レイシズムは単なる差別や偏見にとどまらず、ジェノサイド(大量殺戮)となることを明確に示している。
なかでもひときわ説得力を発揮しているのが、欧米諸国と異なり、日本には反レイシズムという歯止めがないことを指摘しているくだりだ。日本の反差別は、「何が差別で何がそうでないのかという真理の基準」を定めることなく、マイノリティの告発や証言に依存してきた。
その結果、「差別を撤廃しないといけない」という前提すら共有されず、被害者に寄り添うのと同時に加害者と対話することも重視し、本来なら「言論の自由」を守るためにレイシズムと闘わなければならないのに、「言論の自由」と差別禁止が対立する特殊な構造に陥ってしまった。
では、レイシズムの現状を見事に解析したこの本について、なぜ書評が書きづらいのか? 書評の対象として扱われることを拒否している本だからである。
体よくまとめて、「人種差別を許してはいけないとあらためて思いました」などの感想を述べて終わるなんてことは断じて許されない。それでは、マイノリティの告発や証言に依存してきたこれまでと何ひとつ変わらない。命を選別される側にとっては、「寄り添い」も「対話」もなんの意味もないということを、私たちひとりひとりに突きつけてくる本だからである。
「もうこれ以上、マイノリティの被害と歴史を消費してほしくない」と、作者はあとがきで綴っている。マイノリティの体験談に心を痛め、自分は差別的な人間ではないと自己満足する「消費」を止めて、自らが主体となって具体的な行動へ踏み出さなければならない。
差別を煽動する者に反対の声をあげ、ヘイト本を売る出版社や書店をボイコットし、いまだ国籍や性別で社員を選別する企業の商品は購入せず、さらに個人の心がけのみならず、差別を禁止する明確な法整備を求める……これらはマイノリティに「寄り添う」ための行動ではない。フレドリック・ダグラスが言う「自由」を、自分の手に取り戻すための行動なのだ。命が選別される世の中では、だれひとりとして、けっして自由になれないのだから。
************************************
と、書評で書いたように、この本はレイシズムとは何かを解説しているだけではなく、どうして日本では差別やヘイトスピーチがはびこっているのかを深く分析している。さらに、「被害者の声を聞け」という日本型反差別が被害者を沈黙へ追いこんでしまう構造や、日本の入管法が明確なレイシズム政策であることを指摘している。
ニュースや本で「被害者の声」を聞いて同情し、差別なんて許してはいけないとひとりで頷きながら、結局何もしない私のような人間も加害者であると痛烈に突きつけてくる本である。
上の書評では、「差別を煽動する者に反対の声をあげ」ないといけない、なんて勇ましく書いているが、実のところ、差別的な発言を行う職場の上の人に、自分がクビになるかもしれないという覚悟のもとで、「それは差別だ!」と言えるのかというと、正直難しい。
ならば、いったいどうしたらいいのか? 自分にできることはあるのか? とあらためて問うてみると、言葉を失って沈黙してしまうが、でもやはり、どんなささやかなことでも無意味ではないと信じて行動するしかないのだろう。
書評の最後にフレドリック(フレデリックという方が一般的ですが、この本ではフレドリックでした)・ダグラスが唐突に出てきているが、フレドリック・ダグラスは南北戦争より以前から奴隷廃止運動を展開した「公民権運動の父」と呼ばれる人物である。
『レイシズムとは何か』では、この言葉を引用している。
自由がいいとは口では言いながら社会的な運動を軽視する者は、土地を耕さずに収穫をほしがる者である。雷鳴や稲妻を嫌いながら雨が欲しいと言うのである。(略)権力は求められずに譲歩などしない。そんなことは過去にもなかったし今後もあり得ない。
まさにそのとおり、この気持ちを忘れてはならないとつくづく思った……いや、「思った」では、やはりこれまでと同じやないか~~~と考えさせられる本なので、興味のある方はぜひ読んでみて下さい。
国際女性デーに 女性の連帯から何かがはじまる――『99%のためのフェミニズム宣言』(ナンシー・フレイザーほか(著), 菊地夏野(解説), 惠愛由 (翻訳))
前回に続き、800字書評(正確には、批評講座だけど)ですが、今回のお題は本ではなく、森喜朗氏の例の発言について評論するというものでした。
正直なところ、例の発言とそれをめぐる報道については、「またこの人か……」と思った程度で、それほど注目してなかったのですが、あらためて考えながら、以下のように書きました。
※※マーガレット・アトウッド『誓願』のネタバレがあるので、ご注意を※※
-----------------------------------------------------------------------
題)1%と99%が手を結ぶとき
今回の発言に関する報道を聞いてまず感じたのは、そもそもそういう会議に出席できるのはどういう女性なのだろう? という疑問だった。
先日放映されたNHKスペシャル「コロナ危機 女性にいま何が」では、コロナによって職場を奪われた女性たちが取材されていた。ある女性は子どもを抱えて困り果て、またある女性は公的扶助を申請しても却下され、なかには風俗の仕事をはじめても思うように稼げない女性もいた。この現状に目を向けると、オリンピック組織委員会とやらが悪い冗談のようにも思えてくる。
もちろん、発言の機会を持つ女性が増えることによって、女性全体の地位向上が進むというのは事実だろう。だが一方で、男性社会に入りこむことで、男性社会に都合のいい価値観を身につける女性も増えているのではないかと危惧してしまう。
今回の発言は男性が発したものだが、去年「女性はいくらでも嘘をつける」と語ったのは女性だった。結局、社会の枠組みが変わらないかぎり、男性が通った道を女性も通ってしまうだけなのではないか――女性のあいだで分断が広がり、彼女たちの内面に能力主義や自己責任論が刻みつけられる――とも思えてくる。
『99%のためのフェミニズム宣言』(人文書院 2020年)では、男性社会の「内側に入りこむ(リーン・イン)」ことができる1%の女性のためではなく、残りの99%の女性を対象としたフェミニズムを志向している。自分たちが求めるのは、「職場での搾取と社会全体における抑圧」から得られる利益を、支配者層の男女に平等に分担する「支配の機会均等」ではなく、支配を終わらせることだと定義している。
かつて『侍女の物語』(早川書房 2001年)で、女性が徹底的に抑圧される架空の共和国を描いたマーガレット・アトウッドは、2019年に続編『誓願』(早川書房 2020年)を発表した。そこでは、共和国で実権を握るリディア小母が、共和国内で抑圧を受けながら育った少女と、共和国を脱出した女性が生み落とした少女と手を結ぶ。リディア小母が共和国の価値観を身につけ、女性でありながら支配者となったのは、そうしなければ生きのびることができなかったからだ。1%としての痛みを存分に味わったリディア小母が、共和国の支配に終焉をもたらすために少女たちと結託し、新しい世界を生きる若い女性たちに語りかける。
現実の世界でそのようなことが起こりうるのだろうか? 女性たちがつながることは可能なのだろうか?
-----------------------------------------------------------------------
さて、上でも紹介している『99%のためのフェミニズム宣言』は、男性社会の「内側に入りこむ(リーン・イン)」フェミニズム――政府が推進する〝女性活躍社会〟のようなフェミニズム――を「資本主義の侍女」と批判する、たいへん刺激的な本だった。
たとえば〝セクハラ〟にしても、異性への単なる性的嫌がらせではなく、権力関係に基づいたものであり、多くの場合、仕事の実権を握る者が、自分に逆らえば生計を立てられなくなる相手に対して行うものであることを考えると、ジェンダーと権力、資本主義が深く結びついていることがわかる。
貧しい女性たちであり、労働者階級の女性たちであり、人種化された女性たちであり、移民の女性たちであり、クイアやトランスジェンダーの女性たちであり、障害を持つ女性たちであり、資本に搾取されているにも関わらず、「中産階級」(ミドルクラス)の自負を抱くよう促されてきた女性たち
この本では、こういった女性たちの要求と権利を擁護すると書かれている。最後の「資本に搾取されているにも関わらず、「中産階級」(ミドルクラス)の自負を抱くよう促されてきた女性たち」というのが、多くの高学歴女性たち、高学歴でありながら、同じような学歴の男性とはまったく異なる給料体系や立場(非正規など)で働いている女性たちに刺さる言葉ではないだろうか。
いや、この本で再三書かれているように、いまや搾取する側も男性ばかりではない。資本主義のヒエラルキーの高い地位に立つ女性も増えてきている。「能力があれば」女性でも高い地位につくことができる。
けれど、能力で人間を分断するのは正しいことだろうか? 森氏の発言を題材にした講座では、そもそもオリンピックそのものが「競争と優勝劣敗思想をあおる」ものだと批判した方もいた。
とはいえもちろん、どれだけ成果をあげても、いくら頑張ろうとも、そうでない場合とまったく差がつかず、なんの見返りもない社会が正しいとも思えない。
資本主義や能力主義が99%の男女を押しつぶしつつあるのは事実でも、それに代わるものを具体的に構想できるわけではない(少なくとも私は)。独自で自給自足のコミュニティを作るとかいった代替案を実践している人もいるのかもしれないが、そういうコミュニティ思想にも一歩引いてしまう自分がいる。
上の評で「社会の枠組みが変わらないかぎり、男性が通った道を女性も通ってしまうだけなのではないか」と書いたけれど、では、どうやって社会の枠組みを変えるのか? と考えると、やはりクォータ制のようなものを取り入れて、社会の中枢部での女性の割合を増やすしかないのか……しかし、それはつまり「支配の機会均等」なのではないか? とも思え、頭の中でぐるぐると疑問が渦巻く。
と、ジェンダーと資本主義の問題については、まったく答えは見つからない。けれども、いまのような社会では、1%の女性も99%の女性もどちらも追いつめられ、多大な痛みを被ってしまうのはまちがいない。
自己責任論や内面化された能力主義に傷ついている人や、いくら働いても生活が楽にならない現状に疑問を抱いている人、あるいは、〝飲み会を一切断らずに〟高い地位についた女性なども、『99%のためのフェミニズム宣言』のような本を読んで問題を可視化するだけでも、社会全体が変わるきっかけになるのかもしれない。
さて、今日3月8日は「国際女性デー」です。こういう〇〇デーとは、行政主導の単なるかけ声のように思ってしまうけれど、この本の解説によると、起源は20世紀初めの社会主義運動に根ざしているらしい。
1908年のこの日、1万5000人の衣料品産業の女性労働者たちが賃上げや労働時間短縮、参政権を求めてマンハッタンの中心を行進した。その多数は移民女性だった。その翌年、織物労働者の移民女性たちがストライキを行い、警察や経営者の弾圧にあった。
そして1910年に「国際女性労働者デー」の組織化が行われた。
110年前、いやもっと昔から、女性の連帯は続いてきたのだろう。明確な解決策があるのかどうかはわからなくても、痛みに気づいた女性たちが連帯するだけでも、何かが変わり、何かがはじまるのかもしれない。
【800字書評に挑戦】「健康」な恋愛への「不健康」なためらい――尾崎翠「第七官界彷徨」
さて、先日とある講座を受けたところ、800字の書評を書くという課題を出されました。
800字というと、400字詰め原稿用紙2枚。短いので、なんとかなるかな……と思いきや、短い字数であらすじをまとめ、さらに考察も入れるとはなんとも難しいとつくづく感じた。
しかも課題書は、尾崎翠「第七官界彷徨」。
大学のときにはじめて読んでから、ずっと大好きな物語ではあるのだけれど、読んだことのある方はおわかりでしょうが、その魅力を語るのはきわめて困難だ。
「第七官界彷徨」の第七官界とは、人間の感覚である五官、さらに霊感とも言われる第六感の次の感覚を指していて、主人公である小野町子が「人間の第七官にひびくような詩を書いてやりましょう」という思いを心に抱くところから取られている。この小説自体が第七官界にひびくものであり、感覚の極北で綴られた物語とも言える。
私が持っている筑摩書房版の解説で、矢川澄子は尾崎翠のドッペルゲンガーへのこだわりをひいて(「第七官界彷徨」では『ドッペル何とか』と書かれている)、「尾崎翠はもしかして二人いたのではなかろうか」と書き、こんなふうに続けている。
ひとは彼女の語りの「異常なまでの明るさ」に目をみはり、その文章の「悲痛な軽やかさ」に心打たれる。
「異常なまでの明るさ」と「悲痛な軽やかさ」とはまさに言いえて妙で、尾崎翠の魅力について語ろうとしても、白夜のような明るさに私たちは目がくらみ、蘚(コケ)の花粉のような軽やかさは私たちの手をすり抜けてしまう。
悲痛というのは、文学の志を抱いて鳥取から上京し、昭和初期のモダニズムの時代に斬新な文章で注目を集め、同じく新人作家であった林芙美子に敬慕されるほどの才気を発揮したにもかかわらず、さまざまな事情が重なって地元へ戻り、そのまま文壇から忘れ去られてしまったという尾崎翠の生涯を重ね合わせているのかもしれないが、たしかに、彼女の愛したチャップリンのような物悲しさが物語の片隅に漂っている。
こんなふうに考えていくと、やはり800字で書くなんて無理だと思ったりもしたけれど、とりあえず提出したので、「第七官界彷徨」の冒頭に続けて載せておきます。(なお、800字と言ってますが、課題は800字から1000字のあいだという指定でした)
よほど遠い過去のこと、秋から冬にかけての短い期間を、私は、変な家庭の一員としてすごした。そしてそのあいだに私はひとつの恋をしたようである。
************************************
題:「健康」な恋愛への「不健康」なためらい
『第七官界彷徨』では、蘚の恋愛と人間の恋愛が並行して語られる。
「我ハ曾ツテ一人ノ殊に可憐ナル少女に眷恋シタルコトアリ」と論文の冒頭に綴る小野二助は、失恋したことをきっかけに植物の恋愛の研究に没頭するようになる。蘚の恋愛はこやしによって触発されるため、物語の主人公である町子が兄の一助と二助、そして従兄の三五郎とともに暮らす家には常にこやしの匂いが漂い、恋情をそそられて花をひらけた蘚の花粉が舞い散っている。「植物の恋愛がかえって人間を啓発してくれる」と三五郎が町子に言うとおり、蘚の花粉を吸いこんだ住人たちもそれぞれ恋に落ちる。
ところが、蘚とくらべると人間の恋愛はどうにもあやふやだ。二助が恋した少女には、二助のほかに「深ク想エル人間」がいた。病院に勤務する精神科医の一助は入院患者に恋をするが、もうひとりの医者との三角関係に悩まされる。音楽を勉強する受験生である三五郎は、町子を慈しんでいたにもかかわらず、隣の家の少女も気にかかる。そんな三五郎を見て泪を流していた町子も、束の間の恋に落ちる。どういうわけだか人間は、蘚のように「健康な、一途な恋愛」をすることができず、一助の言うところの「分裂心理」に陥ってしまう。恋心はあてもなく空回り、「誰を恋愛しているのか」すらも解らなくなる。
どうして蘚のように「健康な、一途な恋愛」ができないのだろう? 蘚はあんこのように煮たてた熱いこやしを養分として、大量の花粉を放出し、再生産へ邁進する。一方、一助や三五郎は浜納豆やすっぱい蜜柑をつまんで、三角関係に悩む。町子は短い恋の相手の家で塩せんべいとどら焼きを食べて、睡気を覚える。二助は蘚が開花せずにためらっているのに気づき、「分裂病ニ陥レルニ非ズヤ」と心配する。結局それはこやしが中温度であったからだと判明するのだが、焦った二助は栗とチョコレートを取り違える。
生命力にあふれた「健康」な蘚と比べると、栄養分に乏しい食物ばかり口にして、「分裂心理」に陥る人間の「不健康」さが際立つ。蘚の花粉によって恋心を刺激されても、住人たちは足踏みをするばかりで、恋の成就に向けて踏み出すことができない。再生産にはほど遠い。その「不健康」なためらいこそが、現在においてもこの作品がまったく古びず、共感を得る理由なのだと思う。
なぜ村上春樹はこの作品を訳したのか? ジョン・グリシャム『「グレート・ギャツビー」を追え』(村上春樹訳)
彼が注意深く箱を開けると、図書館が入れた目録ページがあり、そこには「F・スコット・フィッツジェラルド著『美しく呪われしもの』オリジナル原稿直筆」と書かれていた。
「やったぜ」とデニーが静かに言った。彼は同じ形をしたボックスを二つ、五つ目の抽斗から取り出し、細長いテーブルの上にそっと置いた。中には『夜はやさし』と『ラスト・タイクーン』のオリジナル原稿が収められていた。
ジョン・グリシャム『「グレート・ギャツビー」を追え』(村上春樹訳)を課題書として、大阪翻訳ミステリー読書会を開催しました。
なぜアメリカのベストセラー作家であるグリシャム作品を村上春樹が翻訳したのか? グリシャムといえばリーガル・サスペンスの名手なのに、弁護士が出てこないってどういうこと? と話題を呼んだ小説です。
プリンストン大学の図書館に厳重に保存されていた、時価2500万ドルものフィッツジェラルドの直筆原稿を窃盗団が奪い、FBIが原稿の行方を追いかけると、意外な人物が浮上する……というストーリー。
物語の冒頭から窃盗団がプリンストン大学に忍びこみ、見事なチームプレーで強奪に成功する。ページ数でいうと、たったの30ページ。
こんなに簡単に盗めるものなのだと感心していると、たったひとつ、ほんの些細な証拠からあっという間に窃盗団のひとりの身元が判明する。やはり世の中はそんなに甘くなかった。FBIは窃盗団を追いつめて主要メンバーを捕まえるが、性急に事を進め過ぎてしまったのか、残りのメンバーが原稿を持って姿をくらましてしまう――
そんなこんなで第三章になってようやく、この物語の主人公であるマーサー・マンが登場する。マーサー・マンは将来を嘱望された新進気鋭の女性作家であり――いや、「であった」と言った方が正確かもしれない。
現在31歳のマーサーは、24歳のときに長編小説と短編小説集を一冊ずつ出版した。どちらも高い評価を受けたものの、とうに絶版になり、執筆と両立するはずだった教職は契約が打ち切られ、肝心の執筆もまったく進んでいなかった。
つまり、金もなく、仕事もなく、さらに住む場所も失ってしまった。しかも、学資ローンの借金はまだ残っている。小説で得たわずかな印税を学資ローンの利息の支払いにあてたが、元金を返せる額ではなかった。
そんな彼女の前に、イレインという謎の女があらわれる。
奪われたフィッツジェラルドの原稿を取り戻すために、フロリダのカミーノ・アイランドにある書店を偵察してほしいとマーサーに依頼する。その書店は稀覯本も扱っており、ときに盗まれた書籍の取引にも手を染めているらしい。
作家であるマーサーなら、疑われることなく書店の店主と仲良くなり、内部に忍びこめるはずだというのだ。しかも、その店主は若い女性作家にはとりわけ親切なので、いろんな面で交流できるのではないかとほのめかす。
もちろん、マーサーはそんな怪しい依頼を即座に断ろうとするが、マーサーが置かれている苦境も調べ抜いていたイレインは、高額の報酬をちらつかせる。学資ローンという長年の悪夢から解放される。そう考えただけで圧倒されたマーサーは、ついに依頼を引き受けてしまう。
イレインがマーサーに目をつけた理由は、金に困っているからだけではなかった。カミーノ・アイランドには祖母テッサが住んでいて、幼い頃、マーサーはそこでテッサとともに夏を過ごしていた。けれど、テッサが海で事故死してからは遠ざかっていた。依頼を引き受けたものの、テッサとの思い出が色濃く残る島に戻って、そんなスパイまがいの任務を果たせるのか、どうしようもなく不安に陥るマーサーだった……
奪われた原稿を追いかけるという筋立てから、FBIと窃盗団のだまし合いといったハラハラするサスペンスかと思うかもしれないが(読書会では、ジェフリー・アーチャー『百万ドルをとり返せ!』みたいな話かと思っていたら、全然ちがったという声もあった)、サスペンス要素は控えめで、それよりも書店ベイ・ブックスの店主ブルース・ケーブルを中心としたカミーノ・アイランドの人間模様が、この小説の読みどころである。
先のあらすじ紹介ではあえて省いたが、ブルースがベイ・ブックスを立ちあげて、最近流行りの「独立系書店」として成功をおさめるくだりは、本や書店に興味がある人や、自分でも店やビジネスをやってみたい人にとっては、非常に興味深い。
また、ブルースの人となりも捻りがきいている。フロリダの陽光に焼けた肌にクールなスーツをまとい、絶対に靴下をはかない男(昔の石田純一をどうしても思い出すが)というと、気取ったいけすかないやつに思えるが、一方で、だれよりも勤勉で心から書物を愛する人間でもある。
ブルースをとりまくカミーノ・アイランドの作家たち――純文学を書いていたがまったく売れず、やけくそでロマンス小説を書いたら大当たりしたマイラとリー、ヴァンパイア小説で売れっ子になったエミリー、商業的には成功していないが(していない故に?)一目置かれている詩人のジェイ、警部物で人気作家となったがアルコールの問題を抱えているアンディー、連邦刑務所に入った自らの経験を基に産業スパイ小説を書くボブ……
と小説好きの読者であれば、それぞれモデルがいるのかな? なんて考えながら、この面々のやりとりを読んでいるだけでも楽しめる。
さらにこの物語は、フィッツジェラルド作品のみならず、40作近くもの小説について言及している。
稀覯本として高値がついている作品(ジェームズ・リー・バーク『受刑囚』やコーマック・マッカーシー『ブラッド・メリディアン』など)や、「亡くなった白人男性作家」の作品を避けているマーサーが最近読んだ三冊(さて、なんでしょう?)も、本についてのトリビアを得られるうえに、登場人物の心情やキャラクターを知る手掛かりとなる。
なかでも、私が一番心をうたれたのは、エミリー・ディッキンソン『名詩撰』の使われ方だった。本筋とは関係ない場面だが、そういった細部の描き方が物語の豊かさを左右するのだとあらためて感じた。
冒頭の疑問に戻ると、リーガル・サスペンスの名手であるグリシャムが、どうしてこういう小説を書いたのか? と考えながら、グリシャムのデビュー作『評決のとき』を読んでみた。
『「グレート・ギャツビー」を追え』と同様に、『評決のとき』も犯行現場からはじまる。もたもたせずに一気に読者をつかむ、というのはグリシャムの小説技法のひとつなのかもしれない(ちなみに、『「グレート・ギャツビー」を追え』では、「いかにして小説を書くか、ブルースの十箇条」が披露される)。
しかし、凄惨さはまったく異なる。黒人の幼い少女をふたりの白人の男がレイプして痛めつける冒頭は、汚い表現だが「胸糞悪い」というのがぴったりだ。
犯人に復讐した被害者家族をめぐるこの法廷劇を読み、ものすごく今さらなのかもしれないが、リーガル・サスペンスとは人間ドラマなのだなと腑に落ちた。
正義は必ず悪にうち勝つといった単純な話ではなく、さまざまな思惑や駆け引きが絡みあう。弁護士や検事といった登場人物も曲者ぞろいで、完全な善人や悪人は存在しない(レイプ犯は悪人と言えると思うが)。
そのあたりが、『「グレート・ギャツビー」を追え』での個性の強い作家たちの人間模様や、善人か悪人か一概に言い切れないブルースのキャラクターと重なった。
次に、なぜ村上春樹がこの本を訳したのか? という疑問だが、この物語のストーリーは『グレート・ギャツビー』とは関係がない。よって、フィッツジェラルド作品を読んだことがなくとも、この小説をじゅうぶん楽しめる。
読後感としては、村上春樹訳の作品の中では『グレート・ギャツビー』より、エルモア・レナード『オンブレ』に近いものを感じた。
村上春樹が好きな小説と語っている、レナードの『ラブラバ』も同様であるが、知恵と胆力に恵まれた者が相手を出し抜き、危険な状況に陥っても見事にその場を制するさまが痛快に描かれた小説、と言えばいいだろうか。主人公は「正義の人」とは言いきれないが、自らの中に倫理を抱いている。チャンドラーのフィリップ・マーロウにも共通しているかもしれない。そういった系統にある作品として、この小説を訳したのだろうと考えた。
この小説には続編〝Camino Winds〟も出版されていて、訳者あとがきによると、カミーノ・アイランド在住の作家が殺害され、ブルースが捜査に乗り出すというミステリーらしく、こちらも翻訳刊行が決まっているとのこと。いったいだれが殺されるのか、次の邦題も春樹氏の訳書名がフィーチャーされるのではないかなど、読書会ではあれこれ勝手に妄想して盛りあがりました。
↓の紹介を見ると、〝bestselling author Mercer Mann〟 という意外な事態になっているらしいのも気になる。
さて、次回の読書会は春以降になる予定で、おそらくオンライン開催になると思いますので、全国のどこからでもご参加できます。ご興味のある方は下記のサイトをチェック頂き、お気軽にご連絡ください。
立派な実験動物として生きるために 『韓国フェミニズム作品集 ヒョンナムオッパへ』(チョ・ナムジュほか著 斎藤真理子訳)
『韓国フェミニズム作品集 ヒョンナムオッパへ』を読みました。
タイトルからもわかるように、「フェミニズム」をテーマに韓国の女性作家七人が書き下ろした短編集……というコピーから思い浮かぶ枠をはるかに超えて、リアリズム小説からノワールやSFまで多彩な物語が収められている。
表題作の「ヒョンナムオッパへ」は、ベストセラーとなった『82年生まれ、キム・ジヨン』のチョ・ナムジュによる作品である。
「オッパ」とは韓国語で「兄」という意味を持ち、恋人など親しい年上の男性への呼びかけに使用される言葉とのことで、「ダーリン」みたいなニュアンスなのかもしれない。
「キム・ジヨン」と同様に、ここで描かれるヒョンナムオッパの姿に女性読者はあるある!と眩暈がするくらいの既視感を覚えるにちがいない。
自分がヒョンナムオッパみたいな男と絶対につきあうことはなく、関わることすら避けて生きてきたとしても、かならずと言っていいほど、この手の男は友達の彼氏や夫の中にひとりは存在する。
女同士で遊びや旅行に行く計画を立てているときに、「彼氏を置いて遊びに行くと機嫌が悪くなる」とか、「夜出かけるときには、ごはんを用意しておかないといけない」とか耳にして、(お留守番もできへんの? 夫は小学生なん? いや、小学生でもコンビニでおにぎりくらい買えるで)と苛立った経験がある女性は少なくないのではないだろうか。そういうタイプの女性は、物語内のジウンのように、オッパに毛嫌いされるのだろうが。
しかもこのオッパは日常生活のみならず、将来の進路まで平気で指図するので驚かされるが、オッパがうざければうざいほど、目覚めた主人公が手に入れた解放感が際立ち、最後の「ケジャシガ」(本文では日本語ですが)という罵倒語が痛快に響く。
しかしその一方で、こんなことも思う。
どうして主人公はこのヒョンナムオッパのような男に魅かれてしまったのか? どうして私たちはときにつまらない男を好きになってしまうのか? 好きになった相手をすぐに断ち切ることができるのか? 自分より強く見える男に守ってもらいたいという気持ちを完全に捨て去ることができるのか?
この狭間でぐるぐるする「フェミニズム小説」は成立するのだろうか?
次の「あなたの平和」(チェ・ウニュン)と、「更年」(キム・イソル)も同様に、日常生活に潜む抑圧を描いている。
「あなたの平和」は、息子の結婚相手ソニョンを迎える母親ジョンスンの姿を、娘ユジンの視点から描いた作品である。
苦労して育ち、母を喜ばせるために安定した家に嫁いだジョンスンの長年の葛藤が、息子の結婚によって顕在化される。結婚相手のソニョンは早くに両親を失い、家だけが遺されたため、息子がソニョンの家に入ることになる。
つまり、息子夫婦はジョンスンとまったく正反対の生き方を選んだのだ。嫁ぎ先で義理の母と夫にひたすら尽くして生きてきたジョンスンは、どうしてもそのことが受け入れられない。そんなジョンスンに娘ユジンはこんな言葉を投げかける。
「おばあちゃんがお母さんにやったことを、ソニョンさんにやろうとしないでよ……誰にもそんなふうに、ほかの人を苦しめる資格はないんだから」
「両親もいない子を受け入れてやったのに」……
「そんなふうだと、お母さんのそばには誰もいなくなるよ。そんな醜い考え方する人、顔も見たくないし、話もしたくない、帰るわよ」
ユジンが幼いころ、ジョンスンが倒れて救急車で運ばれても、ユジンの祖母や父親は気にも留めなかった。家にとって、嫁のジョンスンは取るに足らない存在だったのだ。やせ細った身体でキムチを漬けるジョンスンを、ユジンは子どもながらに少しでも助けようとした。
そんなユジンが上記の台詞をジョンスンに言わなければならなかったとき、どれほどつらかったかを想像すると、こちらまで胸が引き裂かれそうになる。
「更年」も息子を持つ母親が主人公であり、同様に息子の行いによって、自分の人生はいったいなんだったのか? と、これまでの選択を振り返る物語である。
この小説では、世界を放浪する妹ジナが主人公とまったく反対の生き方を選択する存在として登場し、ジナと連絡をとった娘がアイドルの話題で盛りあがる場面で風穴があき、爽快な空気が流れる。
結婚しなければ寂しいだろうと、なぜあんなにうっかり信じ込んでしまったのか。多数が選ばない別の生き方もあるということをなぜ、認められなかったのか。結局、私もジナも同じだ。それぞれ、自分が考えて選択した人生なのだし、その選択の責任を負って生きているだけだ
というのは、この物語内ではなく作家ノートで書かれている文章だが(推敲時に本文から消したとのこと)、この小説全体を貫く思想だと感じられた。
「すべてを元の位置へ」(チェ・ジョンファ)からの短編は、先の三篇とは異なり、いわゆる「フェミニズム小説」というより、新しい角度から切り取ったジャンル小説としての趣きが強い。
「すべてを元の位置へ」の主人公は、L市に建ち並ぶ廃墟や廃屋に入って内部の映像を撮影する仕事をはじめる。題から連想される、Radioheadの“Everything In Its Right Place”に似つかわしいシチュエーションだ。(といっても、韓国語の原題はわからないけれど)
解説によると、ソウルの大規模都市再開発による立ち退きが背景となっているらしく、追い出された人が残したスカートを拾った「私」はどうしたのか、そして「私」の身に何が起きたのか……と、ある種の寓話として描かれている。
「異邦人」(ソン・ボミ)は、警察の捜査局から追い出されて身を隠していた「彼女」のもとを、後輩の「彼」が足繁く通って捜査復帰を懇願するところからはじまる。人工の雨が降る近未来を舞台とした、ノワール風のハードボイルドだ。
ヴァーチャル自殺が流行る世の中で、「死人は傷ついた心より重い」とフィリップ・マーロウの台詞を口にしていた「彼女」だが、物語が進むにつれて、はたして死人と傷ついた心のどちらが重いのか? と問いかける。男と女という軸、現実とヴァーチャルという軸を入れ替えた試みが興味深い作品だった。
「ハルピュイアと祭りの夜」(ク・ビョンモ)では、とある島で開かれた女装コンテストに、友人ハンの代わりに出場したピョがとんでもないことに巻きこまれる。
女装コンテストで賞金五千万ウォン? そんなことあるのか? ピョが訝りつつも、ハンが提示した謝礼三百万ウォンにつられて引き受けるくだりはユーモラスだが、島に着いてからは血も凍るような陰惨な事態がくり広げられていく。
女性が男性を罰するという勧善懲悪を描いた作品とも言えるが、三百万ウォンで身代わりとなったピョの不条理な運命を考えると、現実の事件においても痛い目に遭うのは末端の小悪党で、巨悪は他人を身代わりに送りこみ、永遠に罰せられることがないという皮肉もこめられているのかもしれない。
最後の「火星の子」(キム・ソンジュン)は、宇宙船で打ちあげられた「私」が語り手となる。
宇宙船の中で眠りから覚めた「私」は、右腕と左腕、さらに二本の足を動かしているところから人間らしい形状をしていると思われるが、人間ではない。無数の実験動物のデータを集めて作ったクローンだ。
そんな「私」を待ち受けていたのは、一匹のシベリアンハスキーだった。私の名前はライカだよ、と英語で自己紹介をする。
そう、あのスプートニク二号に乗せられたライカ犬だった。宇宙の藻屑となったあと、星から星へと永遠にさまよい歩く存在となったのだ。ペットのノミに宇宙飛行士の名前をつけ、デヴィッド・ボウイの「スペイス・オデッセイ」を口ずさみ、ときにはダンテの煉獄を引用したりと恐ろしく博識で、無知な人間に容赦のないライカ。
軽々しくふれられることを嫌いながらも、「私」に抱きしめられるとすぐに「私」が妊娠していることに気づく。記憶を消された「私」は、実験によって妊娠させられたこともすっかり忘れていたのに。
ライカは妊娠した私を、自分の娘にでもなったみたいに世話してくれる。火星の空のような、本音のわからない犬だったけど、あれ以来ライカが私に注いでくれたまごころを思うと、誰かが私のために送り込んでくれた存在ではないかとも思えた。
ライカと探査ロボットたちに見守られ、「私」は夢を見る。
夢の中では、枯れはてた赤い惑星であるはずの火星に白い波が打ち寄せ、生まれたばかりの子どもが魚のように泳ぐ。目を覚まして夢だと気づく。そこにある火星はやはり水のない乾いた惑星だけど、ライカとロボットは臨月の「私」を見守っている……
解説にもあるとおり、「ほのかな希望」が漂う作品であり、また一方で、実験動物となって宇宙の果てまで行かないと、安らぎの空間は得られないのだろうか? なんて考えさせられたが、この短編集で一番心に残った。
ライカは「実験動物になるための二つの必須条件」として、「賢くて健康なこと、主人がいないこと」を挙げている。
このふたつの条件は、自立して生きていくための必須条件ではないだろうか?
新しい生き方を模索することは、つまり「実験動物」として生きることなのかもしれない。なんとかこの条件をクリアして、立派な実験動物として生きていきたいものだと年頭から心に誓った。