黒人社会の厳しい現実と甘いラブ・ストーリーの融合 映画『ムーンライト』
アカデミー賞で話題になった映画『ムーンライト』を見てきました。
トランプ政権への映画界からのアンチテーゼとも評されたように、黒人社会の厳しい現実を描いた映画……と思っていたら、それはたしかにそうなんだけど、それ以上に、まぎれもない純愛映画でした。
以下は、ネタバレになりますが――
まずはマイアミの黒人の貧困地域を舞台として、主人公シャロンの子供時代が描かれる。小柄で内気なシャロンは学校ではいじめられ、家でもドラッグ中毒の母親からしばしば邪魔者扱いされ、どこにいっても居場所がない。そんなシャロンの父親代わりになり、手を差し伸べてくれたのがファンだった。しかし、そのファンが母親にドラッグを売っている張本人だった……
次はシャロンの高校生時代が描かれる。シャロンは相変わらず学校ではいじめられっ子のままであり、ドラッグ中毒の母親は心身ともにボロボロになっている。そんなシャロンが密かに思いを寄せるのは、幼なじみの同級生ケヴィンである。恋心は一瞬通じあったように思えたが、そんなふたりを引き裂く事件が起きる……
そして、最後は大人になったシャロンが描かれる、といったストーリーで、とくに大きな事件が起きることもなく、物語は淡々と進む。けれども、非常に繊細に、そして丁寧にシャロンの心の動きを追っているため、ちっとも退屈しなかった。不安定なカメラワークもたいへん美しく、心情をうまく反映していた。(が、正直なところ、少し酔いそうになりましたが)
ふつう、子役が演じる子供時代はかったるくなることが多いけれど(私だけか?)、子役の演技がすごく自然で、ほんとうにいじらしくて見入ってしまった。
考えたら、黒人だからといって、みんながみんなfunkyでノリがよく、いかつい身体をしているわけではないのは当然だ。でもそういう一般的なイメージ、おそらく本人たちも内面化しているマッチョイズムにより、シャロンのような華奢でシャイな男の子は黒人社会に馴染めず(高校生のシャロンが、「なんでそんな細いジーンズはいているんだ?」と言われるシーンは少し笑えた)、言うまでもなく白人社会には混じれない――というより、この映画では白人社会など出てこない。いつもドラマや映画で目にする、東海岸や西海岸の白人社会など完全な別世界だ。それが現実なのだろう。
このひょろひょろのシャロンを見ていると、昔読んだ――それこそ高校生くらいのときなのでほんとうに大昔だが――山田詠美の『ジェシーの背骨』を思い出した。詳しい内容は覚えていないけれど、主人公の女と、その恋人の子供ジェシーとの心の葛藤を描いた物語だった。実の親の恋人に複雑な感情を抱くのは、どこの国の人間であろうと当然なのだけど、「黒人」としても「子供」としてもステレオタイプに描かれていないジェシーが当時の私には新鮮だった。
あとは、前も取りあげた、ゾラ・ニール・ハーストンの『彼らの目は神を見ていた』。前にも同じようなことを書いたけれど、ゾラ・ニール・ハーストンは当時の黒人文学の主流であった、「黒人を差別する白人を糾弾する小説」を書かずに、「黒人の男に虐げられる黒人女性」を描いて、黒人社会から激しいバッシングを受けたという。ゾラが描いた主人公は男を倒す強い女だったが、ゾラ自身はバッシングが関係あったのかどうかはわからないが、最後は困窮して野垂れ死んだのだった。

- 作者: ゾラ・ニールハーストン,Zora Neale Hurston,松本昇
- 出版社/メーカー: 新宿書房
- 発売日: 1995/04
- メディア: 単行本
- クリック: 3回
- この商品を含むブログ (3件) を見る
子供時代、高校時代と過酷な思いを味わってきたシャロンだが――結末のネタバレになりますが――大人になってからの展開は非常に甘い。いや、それが悪いと言っているのではなく、まるで現実から遊離したおとぎ話のようで、切なく胸をうたれた。
施設に入っていると思われる母親がすっかり改心しているのも、現実ではなかなかあり得ないと思うが(依存症が改善されるのも、毒親がマトモになるのもまず聞かない)、涙を流すシャロンに素直に感情移入ができた。
そしてケヴィンとの再会。しかし、前に『キャロル』を読んだときも思ったが、いまの時代にロマンティックなラブ・ストーリーを描くのは、男と女では無理なんだろうか。異性愛と同性愛、どこが違うかというと、やはり異性愛は結婚や家族といった社会制度、つまり資本主義制度を支えるものであるから、「純粋な恋愛」というのが難しくなっている、ということだろうか。その点、同性愛なら、いまの時代でもやはり、社会から背を向けて、ふたりきりの世界を生きるという側面があるから、甘いラブ・ストーリーが成立するのだろうか。
あと、俳優たちの演技もよかった。メインキャストのシャロンとケヴィンを演じるそれぞれ三人は、そんなに有名俳優ではないようだが、すごくはまっていた。年齢ごとに役者が変わるのに、演出の力が大きいのだろうけど、違和感を感じることがなかった。とくにシャロンの子役は、演技未経験だったなんてまったく思えない。
一番の有名どころは、シャロンのドラッグ漬けの母親を迫力満点に演じたナオミ・ハリスだが、彼女はケンブリッジ大学出身のイギリス人女優で、酒やタバコはもちろん、コーヒーすら飲まない超クリーンな生活を送っているらしい…役者ってすごいですね。
女が強くなるとき――『ナオミとカナコ』(奥田英朗)
「あなたの親は、とうして離婚しないのですか?」朱美が不思議そうに聞く。
「さあ……」直美は首を傾げつつ、「たぶん、母に一人で生きて行く自信がないからだと思います」と答えた。
「日本の女の人、みんなやさし過ぎるのことですね。前にも言いましたが、上海の女の人はみんな気が強いです。我慢して結婚生活を続けるなんてことは絶対にありえません」
遅ればせながら、奥田英朗の『ナオミとカナコ』を読んだ。で、ここからはすべてネタバレになるかもしれませんが……
というか、少し前にドラマ化されたので、ストーリーはみんなご存じかと思いますが、大学時代からの親友同士の直美と加奈子が、加奈子に暴力をふるうDV夫・達郎を殺す物語である。桐野夏生の『OUT』と似たテイストと言えるが、『OUT』ほど重くなく、軽やかなスリリングさと、奥田英朗らしい温かみとユーモアのある人物描写で一気に楽しく読めた。
AMAZONのレビューでも指摘されているように、たしかにふたりの犯罪はあまりに素人臭い。いや、それゆえに足がついて、どんどんと追いつめられるサスペンスなのだが、それにしても、足がつくきっかけとなった防犯カメラのこともまったく考慮していないし、共犯者であるふたりが、どこかしらには履歴の残るメールでしょっちゅうやりとりしたり、犯行後も頻繁に会って、なんと直後にお祝いの温泉旅行に行ったり、加奈子はさっさと再就職して働き、マットレスやシーツもすぐに新調し、しかも部屋のインテリアも速攻変え、とそりゃ達郎の実家から疑われても仕方がない。
でも、こんな甘ちゃんのふたりだからこそ(どこまで作者が意図したのかはわからないが)、達郎を殺す計画を立てるワクワク感(死体を埋める場所を下見するところなんか、まるでピクニックのようだった。最後にはやはり日帰り温泉に行くし)と、計画通り殺したあとの純粋な喜びや解放感が素直に伝わってきた。
私もウザい夫がいたら殺したい!と思った。幸か不幸かおらんけど。
また、これも指摘されていたことだが、直美が自分の人生も破滅するのに、友人の夫を殺そうとするのもちょっと納得しがたいものはあった。一応、自分の父親も母親に暴力をふるっていたという背景は用意されているのだが、それでもさしたる躊躇もなく、というかわりとすぐに、殺したる!って思いこむのはあり得ない気もするが、それゆえにすごくスピーディーに物語が進むので、そんなにはひっかからない。
いや、傑作『最悪』や『邪魔』のように、じわじわと登場人物の心情と追いつめられていくさまを描いた小説ももちろんいいのだけれど、いまの時代には、これくらいスピーディーなものが求められているのかもしれない。ただ、直美の動機は少々強引なところがあるが、直美がデパートでの仕事を通じて、犯罪すれすれの中国人実業家・李朱美と知りあったことにより、強くなっていく過程は説得力があった。
そう、この小説の一番の読みごたえは、「ナオミとカナコ」のふたりが、どんどんと強くなり、たくましくなっていくところだった。直美は李朱美との丁々発止のやりとりで、殺人すらも怖くないほど強くなるのだが、直美に引っ張られる形だった加奈子は、夫を排除したことにより決定的に強くなる。
警察も会社も失踪と片付けようとした事件をひとりで調査した、達郎の妹である陽子と対峙しても、警察に取り調べをうけても、ひるむことはない。
達郎を殺さなければ、殺されていた。あるいは一生、奴隷のように扱われた。仕方がないじゃない――。……
わたしは捕まらない――。
そういえば『OUT』も主人公雅子がどんどんと、おそろしいほど強くなっていった。やはり夫を殺したら(雅子が夫を殺したわけではないが)強くなれるのか――いや、夫がいなくてよかった。危ないところでした。
ところで、ドラマ版では、たしかこのDV夫を佐藤隆太が演じたんでしたっけ。ドラマは見てなかったけど、佐藤隆太のDV夫ってイメージ違うなとは思っていたのですが、どうだったんだろう。ちなみに陽子は、吉田羊が演じていたらしい。ということは、姉に改変していたのでしょう。犯人を追いつめる吉田羊は、逆にイメージに妙にはまってて、それはそれで怖い。
人生も半ばを過ぎて――『いつか春の日のどっかの町へ』(『FOK46』改題)大槻ケンヂ
高野秀行さんがツイッターでオススメしていたので、私もひさびさに大槻ケンヂことオーケンのエッセイを読んでみた。

FOK46 突如40代でギター弾き語りを始めたらばの記 (単行本)
- 作者: 大槻ケンヂ
- 出版社/メーカー: KADOKAWA/角川書店
- 発売日: 2014/03/28
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (5件) を見る
最近この文庫本が出たけれど、もとの単行本の方を読みました。単行本のタイトルは『FOK46』だけど、アイドルユニットを組んだわけではなく、題にも書かれているように「突如40代でギター弾き語りを始めたらばの記」。
オーケンの本業がミュージシャンであることは、みなさんご存じかと思いますが、実はなんと、これまで楽器などこれっぽっちも弾けなかったのだった。と言っても、ボーカリストなので、別にギターを弾くふりをしていたなどの経歴詐称?ではないけれど。とは言え、ギターを練習しはじめたオーケンが楽器店に行くと、案の定、
「大槻さんですよね。今日はギターをお探しですか?」
と、まさか有名ミュージシャンがずぶの初心者とは夢にも思っていない店員がにこやかに声をかけてくる……
と書くと、いつものおもしろおかしいエッセイなのかなとお思いでしょうが、この本は単におもしろおかしいだけではない。
まず最初に、筋肉少女帯の日本武道館での復活ライブが終わって楽屋にいたオーケンに、スタッフが声をかける。小学生のときの同級生「ウラッコ」が亡くなったと。
日本武道館ワンマンライブの翌日に、僕は僕に初めてロックを教えてくれた小学校の同級生の通夜に出かけた。
そこで、一人のミュージシャンと再会する。
彼もまた数年後に天に召されるなどとは、その時には夢にも思っていなかった。
この本の背景には、スクールカースト(当時はこんな言葉なかったでしょうが)の底辺にいた文科系小学生男子だったオーケンにロックを教えてくれた、早熟の同級生ふたりの早すぎる死がある。
ウラッコは天才的に上手い絵を描き、小学生高学年にして、プログレッシブ・ロックの名盤のジャケットを見せる。そしてもうひとり、転校生の「ハバくん」は、キッスについて語っていたオーケンとウラッコにシンセサイザーで作曲していると語り、井上陽水の歌詞のすばらしさについて語る。小学五年生で。(しかしふと思ったが、これは公立の小学校の話だけど、やはり東京だからあり得るのかなという気はする)
きっとこんな才能豊かな友人たちは、音楽などの表現活動で早々に世に出るのだろうな、とオーケンは子供なりにぼんやり考える。ところが、ふたりの友人たちもそれぞれクリエイティブな仕事についていたが、表現者として一番有名になったのはオーケンであり、結局、生き残ったのもオーケンだけとなった。ほんとうに人生って不思議なものだ。オーケンは考える。
何かの表現を人が新しく試みようと考えた時、成功に必要なことが明確に三つだけあると思うのだ。
才能と運と継続である。
これは、表現者のはしくれたる僕の40代現在の結論だ。
このあとに書いているように、となると、本人でどうにかできることは継続だけである。「継続だけを命綱に、しつこく食らいついて」いくしかないのだ。続けるだけならだれにでもできるように思えるが、実際はこれがなかなか難しい。
それに続けていったって、成功できるという保証はもちろんない。オーケンは「せいぜい二流の下」という書き方をしているが、まあもっとわかりやすく言うと、食べていけたら御の字で、実際はいくら好きなことを続けても、食べていくことが苦しくなり、結局それで継続不可能になるのだろう。
この本には、亡くなった友人たち以外にも、自分たちのやりかたで表現活動を続けている人たちとの交流が描かれている。エンケン(遠藤賢司)、「たまのランニング」でおなじみの石川浩司、なかでも、元いんぐりもんぐりの永島さんとのエピソードがしみじみした。(いや、さすがに私も筋肉少女帯は聞いていたが、いんぐりもんぐりとなると名前を聞いたことある程度なので、どんな音楽なのかは知らないけれど。。。)
後半では、友人たちだけではなく、海で行方不明になった実の兄の死も書かれている。その日もやはりライブであったオーケンは、「いつも通りのライブをしよう」と心に決めて、ラストには『生きてあげようかな』を歌う。さすが、ミュージシャンの鑑だ。
それからもオーケンは歌い続ける。「池の上陽水」こと、亡くなったハバちゃんが遺した歌を、習いはじめたギターで弾き語る。
眠りなさい 眠っていなさい
起きてても 今日はいい事はない
『そうかなあ、俺らまだ人生の半分過ぎたばかりだぜ。意外にいいこともあると思うよ』
と歌い終わって故人にあえてそう語りかけた。
そして半分以上過ぎた人生の夢として、「ちょっとだけしゃべるギターを背負って」、「長い、遠くまで行く弾き語りの旅」に出ることを考える。
「一人はさみしい、人といるのはわずらわしい」と感じるオーケンにとって、他愛のない会話ができるギターというのが最高の相棒なのだ。この気持ちはわかるような気がする。
ギター以外は、あまり荷物は持っていかない。
「不便じゃないかい?」
季節は春だといいなと思う。
あまり寒くない頃がいい。
「ん? いや、それが、あんまりいるものって無かった」
春の夜はなんだか怖い? BOOKMARK 7号と『真昼なのに昏い部屋』(江國香織)
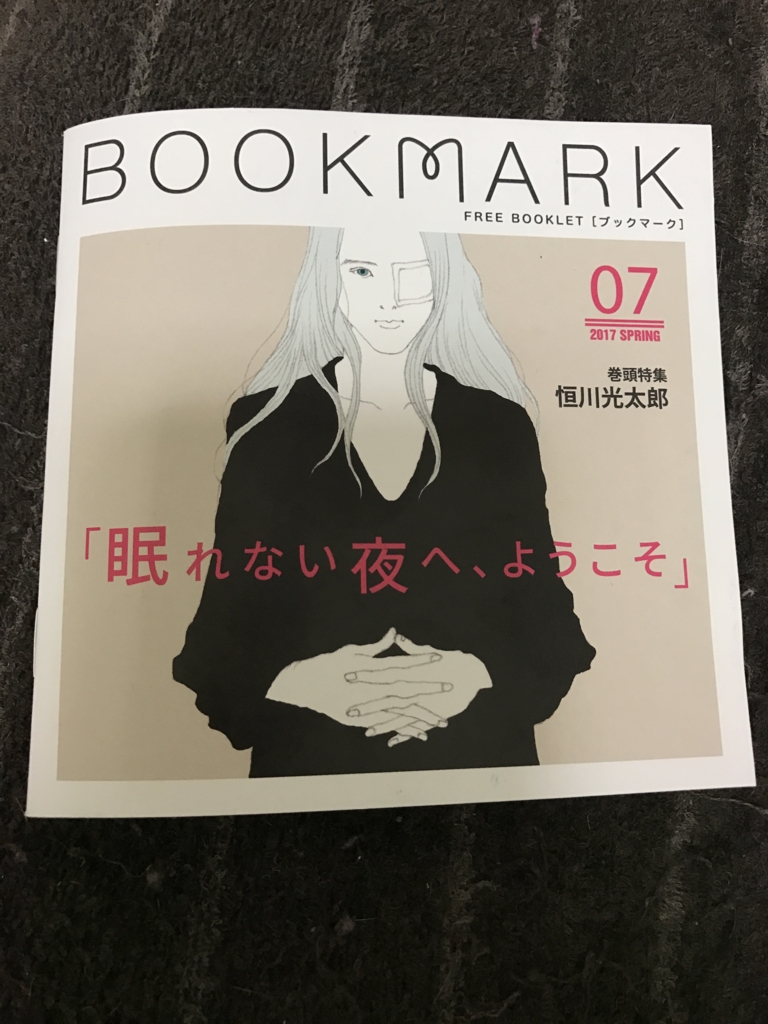
さて、今回のBOOKMARKは「眠れない夜へ、ようこそ」。ホラー特集。といっても、ホラーというと四谷怪談くらいしか思いつかなかったので、いったいどんな本が取り上げられるのか想像つかなかったが、ホラー仕立てのミステリーなどおもしろそうな作品がいっぱい紹介されていた。
まずはおなじみシーラッハの『犯罪』。たしかにこの短編集を読んだときの不条理感というか、突き放される感じは強烈だった。いまのところ、私の中では、やはりシーラッハはこの『犯罪』と『罪悪』が一番かも。
『高慢と偏見とゾンビ』は、『高慢と偏見、そして殺人』の読書会に参加したときに、あわせてちょっと読んでみたけれど、換骨奪胎とはまさにこのことかと、ほんと感心するくらいうまいこと原作にゾンビが紛れこんでいて、怖いというより笑えた記憶がある。しかし、向こうの人ってほんとゾンビ好きだな。
- 作者: ジェイン・オースティン,セス・グレアム=スミス,安原和見
- 出版社/メーカー: 二見書房
- 発売日: 2010/01/20
- メディア: ペーパーバック
- 購入: 6人 クリック: 218回
- この商品を含むブログ (81件) を見る
あと『ずっとお城で暮らしてる』や『くじ』を以前に読んだシャーリイ・ジャクスンの『丘の屋敷』と『鳥の巣』も紹介されていた。先の二作は、設定が奇抜過ぎるせいか、身に迫って怖いとは思わなかったが、ここの二作は「地味で内気」に生きている大人の女性が主人公のようなので、共感できるかも、、、
ほかもどれも読んでみたい作品ばかりだけど、『バイバイ、サマータイム』はヤングアダルトで、一見ホラーとはまったく思えないので、とくに気になった。内向的な少年ダニエルが、離婚にやさぐれた父親とリゾート地で過ごす休暇中に(楽しくなさそうだ)、不思議な少女と出会い……という話らしい。どうやら、この少女が現実の人間ではないという話のようだけど、「会うたびに、身体の傷が増えている」って、生きた人間でも(というか、生きていたらなおさら)絶対近づいたらあかんやつやから!
ちなみに、最近読んでぞわっとしたのは、江國香織の『真昼なのに昏い部屋』。
まあ、一言でいうと、真面目で貞淑な主婦だった美弥子さんが、近所に住むアメリカ人のジョーンズさんと不倫する話なのですが。正直、ふたりがいつも一緒にいるので、当然ながら近所で噂になっても、「やましいことなんてなにもないのに、どうして?」と無邪気に言う美弥子さんがカマトト女のようで、途中ちょっとイライラしたが、最後の怒涛の展開に溜飲が下がるというか、下がり過ぎてこわかった。奥泉光が解説しているように、「です」「ます」と語る、三人称多元の語り口がいっそう不気味な印象を与える。
しかし、ジョーンズさん、悪い男やなー。私の思う「おまえが一番悪者なんちゃうか」リストには、『ノルウェイの森』のワタナベくんや、アガサ・クリスティーの『春にして君を離れ』の夫などが入っているのですが、ジョーンズさんも見事ランクインしそうだ。そうそう、『春にして君を離れ』も、今回のBOOKMARKに載ってもいいような話ですね。
で、BOOKMARKを置いといたら、うちのBOOKではないMarkが上に乗ってきました、、、
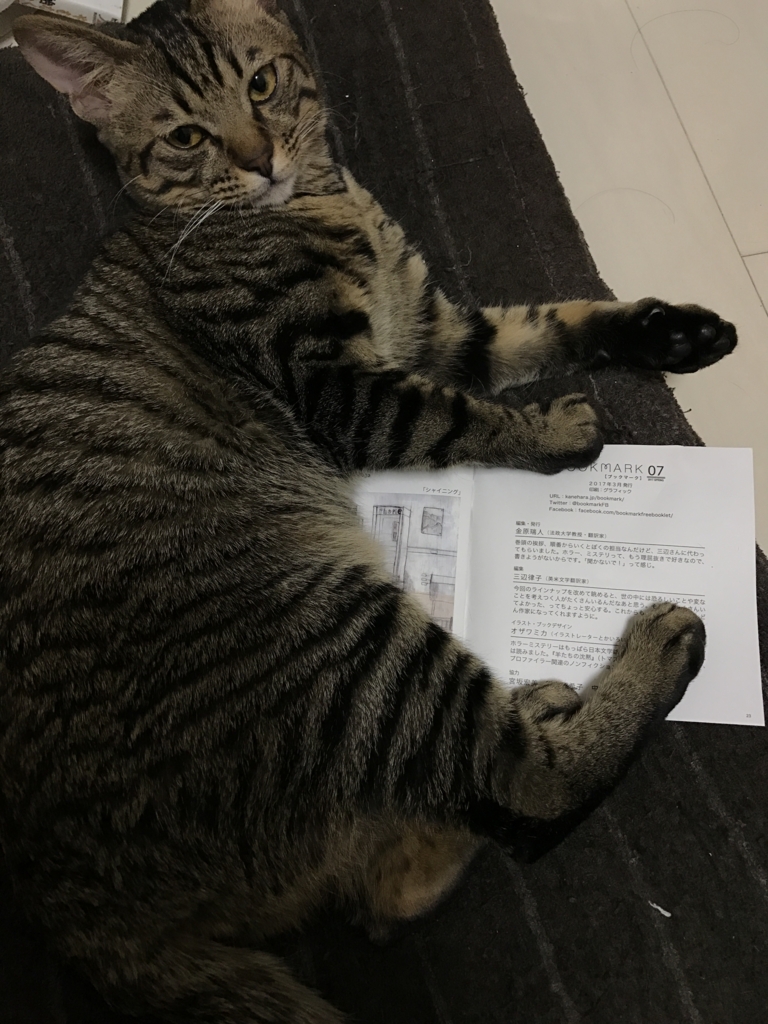
女と女は化かしあい? それとも――『荊の城』(サラ・ウォーターズ 中村有希訳)/ 映画『お嬢さん』(パク・チャヌク監督)
モードは何よりも華奢だった。母ちゃんとは違う。母ちゃんとは全然違う。子供のようだ。まだ少し震えているモードがまばたきすると、睫毛が羽のようにあたしの咽喉をなでる。しばらくすると、震えは止まり、もう一度、睫毛が咽喉をこすって、静かになった。モードは重たく、温かくなった。
「いい子だね」そっと囁いた。起こさないように。
いい子だね、ってどうしても岩合さんを思い出してしまうのですが、それはともかく、サラ・ウォーターズの『荊の城』を読み、映画『お嬢さん』を見てきました。
いや、原作を読んでいったので、どういう話か心づもりをしていたのですが、それにしても映画の予想をはるかに上回る変態ぶりに度肝ぬかれました。
小説『荊の城』は、ヴィクトリア朝のイギリスが舞台であり、ディケンズの小説に出てくるようなスラム街の浮浪児「あたし」は(冒頭から『オリヴァー・トゥイスト』が出てきたりと、作者もかなりディケンズを意識しているようです)、育ての親である「母ちゃん」と泥棒仲間と一緒に暮らしていたが、ある日詐欺師の「紳士」があらわれて、お金持ちのお嬢さまを騙す計画への協力を持ちかけてくる。
その計画とは、伯父に幽閉されている世間知らずのお嬢さんと駆け落ちして結婚し、まんまと財産を奪ったら、お嬢さんを精神病院にぶちこむというものだ。「あたし」はそのお嬢さんの侍女となって身辺を警護し、「紳士」との結婚をそそのかす役目である。「母ちゃん」の了承のもと、「あたし」はその邸宅に向かい、世間知らずのお嬢さまであるモードと知りあうが…
かなりいろいろ仕掛けのある小説(映画も)なので、これ以上なにを言ってもネタバレにつながりそうなので、ここから先はネタバレOKの人だけ進んでください。
この小説は、「このミス」の一位にも輝いたが、殺人事件が発生するわけではなく、ふたりの女性の数奇な運命の交錯が謎となっているので、ケイト・モートンの『秘密』を思い出した。
その最大の仕掛けがあらわになる一部の終わりのどんでん返しが、最高にスリリングであり、二部で語られるその真実の姿の答え合わせがおもしろかった。
上下巻あるこの小説の下巻、第三部以降は、精神病院の描写などはかなりキレキレで読み応えがあるが、さらなる謎が待ち受けているわけではないので、いや、ミステリの公式として、この一連の事件の犯人(黒幕)が解き明かされるのですが、それは読んでいて想像のつく結果なので、少しテンションが落ちるように感じたが、映画ではなんとここでガラッと話を変えていて、これがまたおもしろかった。
そう、映画の方は、日本統治時代の韓国(朝鮮)が舞台になっていて、基本的な設定は原作と同じで、日本人のお嬢さんである秀子のもとに、詐欺師にそそのかされた韓国人侍女スッキがやって来るという話である。
伯父がド変態なのも基本的に原作と同じだが、映画ではその変態ぶりの描写が半端なく、完全に笑えるレベルでした。いや、すべてにおいて、原作ではそこまであからさまに描写していないところも、映画はこれでもかと見せつけていて、エロいというより、ある意味爽快でした。
原作の方は、ストーリー全体として女の戦いというか、女と女の化かしあいといった要素が強く、本編とは関係のない精神病院の看護婦たちの描写でも女の恐ろしさみたいなものを感じたけれど、映画は、女と女が手を取りあって男と戦う物語になっており、原作者のサラ・ウォーターズは女で、映画監督のパク・チャヌクは男だからかな、なんてつい考えてしまった。けれどそれは浅はかな考えだろう。そうすると、サラ・ウォーターズがレズビアンであることも考慮しないといけなくなるし(ゆえにこういう物語を書いたのだと、つい言いたくなるが)、やはり作品と作者は切り離して考えよう。
あと、ジェンダーは原作と映画に共通するテーマだが、この映画で強く打ち出されているテーマは、支配と抑圧である。
先に書いたように、日本統治時代の朝鮮が舞台であり、秀子の伯父は日本人になろうとする韓国(朝鮮)人であり、詐欺師もほんとうは済州島出身なのに、藤原伯爵という日本人をかたる。この映画の表向きの会話の多くは日本語で交わされ、その裏で内面を打ち明ける会話は韓国語で交わされる。(しかし、主要キャストは韓国人俳優なので、こんなに日本語のセリフが多いとたいへんだったのではなかろうか)
↑の監督のインタビューでも「抑圧された状況で戦う女性たちを描きたい」と語っているが、秀子とスッキは伯父や詐欺師といった男たちから抑圧されているが、伯父や詐欺師たちといった男たち、いや当時の韓国(朝鮮)全体が、日本に抑圧されているのである。抑圧されたまま生きているのは死んでいるのと同じである。スッキと出会う前の秀子がそうだったように。
ここで最後の最後のネタバレをすると
秀子とスッキは韓国(朝鮮)から逃げ、男たちと戦い、そして日本からも脱出する。嘘っぱちの日本語で話すこともやめて、自分たちの言葉でほんとうの気持ちを伝える。支配から解放されて堂々と愛しあう。たとえ現代が舞台だとしても、ここまでの解放はなかなか見られない。エロい夢物語のようでしたが、解放とはなにか、ほんとうの自分として生きるとはなにか、考えさせられました。、
大人になるっていうこと 『ペーパーボーイ』(ヴィンス・ウォーター著 原田勝訳)
そういえば、前回の 『MONKEY』の「あの時はあぶなかったなあ」ですが、砂田麻美さんの飼い犬、柴犬のポン吉の話もおもしろかった。手羽先がそんなに犬にとって危険だったとは、、、しかし、「所詮、犬は畜生やよ」ってなんだか深い。
ところでこの砂田麻美さん、映画監督として有名ですが、小説も書いていることを『本の雑誌』で知った。この『一瞬の雲の切れ間に』が『本の雑誌』の恒例の年間ベスト企画でかなりの高評価だったので、読んでみたくなりました。
しかし、『MONKEY』の柴田さんによるあとがきを読むと、レアード・ハントが柴田さんの経験談を気に入ってくれたので、ヤクザに殴られそうになった話がデンヴァ―大学から出ている文芸誌に載るとのことですが、きっとレアード・ハントも「電車のなかで音読?? Really?」と仰天したにちがいない。
で、その柴田さんも審査員を務める日本翻訳大賞。二次選考に残った本を読んでいこうと、まずはヤングアダルト/児童書ではじめて二次選考に進んだ(たぶん)『ペーパーボーイ』から。
タイトルから想像できるように、12歳の主人公「ぼく」が夏休みのあいだ親友にかわって郵便配達を務める話。スヌーピーのマンガを読んでいても、チャーリー・ブラウンやルーシーがいろいろお店を開いたりしますが、ほんとアメリカって、子供の頃からこうやって新聞配達させたり、レモネードを売ったりして、社会に出る訓練をさせるんだなと感心する。
しかも、なんといってもこの「ぼく」は、吃音持ちなのである。自分の名前すら満足に発音できない。けれど、ひねこびたり拗ねたりすることなく、新聞を配るのみならず、頑張って集金にまで行くところにますます感心した。いや、もちろん「感心」と本のおもしろさとは別物であり、「感心した」なんていうと、道徳的で説教くさい話かとかえって敬遠されるかもしれないが、それでもやはり、「……ssss」と息を吐きながら(そうしないと言葉がスムーズに出てこないので、というか、そうしてもスムーズには出ないのだが)、必死で世界とつながろうとする「ぼく」の姿には、感心せずにはいられなかった。
初めての金曜の夜の集金にはいつもの半ズボンじゃなくて長ズボンをはいていくことにした。玄関に出てきた人の前でどもってしまったら脚がむきだしになってないほうが少しは大人に見えるんじゃないかと思ったのだ。
なぜかぼくにとっては自分の名前を声に出して言うことがなによりむずかしい。「B」や「P」で始まるわけじゃないのに「やさしい息」をどれだけ出しても声は喉に引っかかったきり外に出てきてくれない。さらに悪いことに苗字も名前も同じ音で始まっている。ぼくにはこの世で自分の名前を全部言おうとすることほどきらいなことはなかった。点を打つことよりきらいだ。
翻訳の工夫として感じたのは、上記の引用を見てもわかるように、「、」が一切ない。というのは、引用の最後にも書いているように、しゃべろうとするとすぐに息継ぎしてしまう「ぼく」は、書き言葉では点を一切打ちたくないのだ。文章のリズムを整えようとすると、どうしても「、」を打ちたくなるかと思うけれど、まったく点を打たずに翻訳し、それでいてスムーズにストレスフリーに読めるので、一見さらっと読めるこの本ですが、翻訳はかなり苦労したのではないでしょうか。
ストーリーは、おもに「ぼく」が新聞配達をして出会う人たち、両親、そしてメイドのマームとの関わりであり、そのなかでもとくに、マームと廃品を集めて生活するR・Tのふたりの黒人の姿が印象深い。ちなみに、この小説の舞台は1959年で、まだ公民権運動の前夜である。
正直なところ、黒人のひとが、この心優しいメイドのマームと、すさんだ生活をしているR・Tの描かれ方(ある意味どちらもステレオタイプとも言える)についてどう思うのかは微妙かもしれないと少し感じた。(作者の良心はよくわかるけど)
続編では、「ぼく」の両親の謎や、親友だけど結局ほとんど不在だったラット、そして「ぼく」の導き手となるスピロさんについて、もっと突っこんで描いてほしい。訳者あとがきで、「自分もスピロさんのようにありたい」と書かれていますが、ほんと同感です。若い頃は、集団で騒いでいる子供を見たりすると呪詛の念を送ったりしていましたが、こんなことを思うのも、歳をとった証でしょうか、、、
「ともだちがいない!」 『MONKEY vol. 11』(柴田元幸ほか)
盛りあがってますね。小沢健二くんの『流動体について』。
私ももちろんMステ見ました。去年のツアーは行き損ねたので、はじめて現在進行形の曲を聞いたのですが、ほんといい曲でよかった。いまのルックスについては、春風亭昇太とか泉麻人とかネットでいろいろ言われていますが、なんかこう、年相応の自然体でいいんじゃないでしょうか。
さて、小沢くんの先生でもある柴田元幸さんの(つなげてみた)『MONKEY』買いました。

- 作者: 柴田元幸,チャールズ・ブコウスキー,村上春樹,村田沙耶香,伊藤比呂美,谷川俊太郎,くどうなおこ,松本大洋
- 出版社/メーカー: スイッチパブリッシング
- 発売日: 2017/02/15
- メディア: 雑誌
- この商品を含むブログ (1件) を見る
今号の特集は「ともだちがいない!」。おもしろそうだなと思ったら、やはり充実の号でした。
最初の谷川俊太郎の書き下ろしの詩からして、さすがだな~と感じる。息するように詩が出てくるのでしょうか。
友だち?欲しいけどめんどくさい
なんか気を遣わなきゃいけないでしょ
ときどきプレゼントも考えなきゃいけないし
手は仰向けになった猫のお腹を撫でている
という「石」という詩が一番気に入りました。ところで詩というと、つい最近まで、最果タヒと最上もががごっちゃになっていたのは、私だけだろうか?
あと、「よくあるたぐいのアダルト・ブックストア」を舞台にした、チャールズ・ブコウスキーの『アダルト・ブックストア店員の一日』もブコウスキーの世界らしく読みごたえがあったが、ブコウスキーの詩もよかった。好きな作家だったらしい、カーソン・マッカラーズについて書いたものなど。やはり詩人なんだな。
今回二編の短編が収録されたエミリー・ミッチェルは、「奇想系」の作家と言えるのだろうが、これまで紹介されてきた奇想系の作家よりは、設定のリアリズム度が高く(この二編を読んだ限りでは)、奇想系の作家をあまり読まない人にとっても、とっつきやすいのではないかと思う。村田紗耶香がエミリー・ミッチェルについて語っていたが、たしかに、せちがらい現実を非現実を織り交ぜて描くさまが似ているのかもしれない。
とくにおもしろかったのは、パジェット・パウエルの『ジョプリンとディケンズ』で、タイトルのとおり、九歳のジャニス・ジョプリンとチャーリー・ディケンズがクラスメートという設定の物語。
「他人の上に乗る夢想にふける」「普通の女の子じゃない」ジャニスと、どえらい美文調で話す、同じく普通じゃないブキミなチャーリー。チャーリーは九歳にしてこんな風に話すのだ。
「容赦なき11月の天候。水がこの地上から引き始めて未だ間もない時代であるかの様に街路には泥は満ち、象の如き蜥蜴といった趣でメガロザウルスがホルボーン・ヒルをとぼとぼ進んでゆくのを見掛けても不思議はあるまい――」
そしてこのクラスの教師ミズ・ターナーは「生物学への夢に挫折した、ひっそり一人でいるのを好む女性」であり、中学校の運動部のコーチからのアプローチに困っている。そしてジャニスとチャーリーがどんなふうに交流を深めるのかというと、、、ほかの作品も読んでみたくなった。
しかしなんといってもおどろいたのは、今号のインタビューテーマは「あの時はあぶなかったなあ」なんですが、柴田さんは英語の本を読むときは声に出して読むことが多いとのこと。
ふむふむ。やはり音読って大事なんだな。私もやってみよう。うん? 京浜東北線で音読していたらって、電車のなかでも音読しているってこと?? 京浜東北線でコンラッドを音読しているとは! 柴田先生でもそれくらい常に英語の勉強しているなら、私なんてお風呂入ってるときも、ゴハン食べているときも音読したって、とうてい追いつかない。
でも、チンケな私は電車のなかは無理だ、、、1メートルばかり離れて立っている奥さんの気持ちはよくわかる。
いや、少々(かなり)おどろきましたが、この号、ほかにも村上春樹のスピーチやアンデルセンの翻訳、岸本佐知子さんのエッセイもおもしろかったし、かなりお買い得の号でした。







![荊[いばら]の城 上 (創元推理文庫) 荊[いばら]の城 上 (創元推理文庫)](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51FHERQE2DL._SL160_.jpg)



