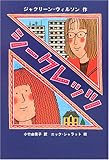ギムレットには早すぎる? 虚構の仕掛けが施された短編集『一人称単数』(村上春樹)
村上春樹の最新短編集『一人称単数』の読書会に参加しました。光文社古典新訳文庫の元編集長である駒井稔さんを迎えて開催され、参加者も春樹マニアと言えるくらいに読みこまれている方が多く、たいへん刺激的な会でした。
前の短編集『女のいない男たち』は、「ドライブ・マイ・カー」や「木野」のように三人称を用いた小説が多かったのに比べて、今作においては、「石のまくらに」は四ツ谷でアルバイトをする大学生の「僕」が主人公であり、「クリーム」や「ウィズ・ザ・ビートルズ」では神戸の高校に通う「ぼく」または「僕」が描かれ、さらに「ヤクルト・スワローズ詩集」の主人公は明確に「村上春樹」であり、千駄ヶ谷に住んでいて頻繁に神宮球場に通ったという、多くの読者が知っているエピソードが綴られている。
エッセイと小説のあいだ、虚構と現実のあいだを描くという意味において、初期の短編集『回転木馬のデッドヒート』の「はじめに」で述べられている「スケッチ」という表現を思い出した。そこで作者は、スケッチとして事実をなるべく事実のままで書きとめていくうちに、「話してもらいたがっている」ことが浮かんでくると書いている。
僕の中に小説には使いきれない "おり" のようなものがたまってくる。僕がスケッチに使っていたのは、その"おり"のようなものだったのだ。そしてその"おり"は僕の意識の底で、何かしらの形を借りて語られる機会が来るのをじっと待ちつづけていたのである。
しかし、『一人称単数』が『回転木馬のデッドヒート』と異なる点は、事実、つまり現実から生まれてくる "おり" を使いながらも、さらに一歩進んで、虚構の仕掛けを施して現実を塗りかえているところだと感じた。現実というのは生と死であるが、エッセイのように軽妙に綴られたこれらの作品をよく読むと、死の影が濃厚に漂っていることに気づく。
「チャーリー・パーカー・プレイズ・ボサノヴァ」が、もっともわかりやすいだろう。主人公の「僕」が学生時代に「チャーリー・パーカー・プレイズ・ボサノヴァ」という実際には存在しないレコードをでっちあげて作品評を発表したら、その15年後、仕事で訪れたニューヨークでそのレコードを見つけるというストーリーである。そしてチャーリー・パーカーは「僕」にこう語りかける。
君は私に今一度の生命を与えてくれた。そして私にボサノヴァ音楽を演奏させてくれた。
虚構、つまり書かれた言葉が現実になることによって、34歳で死んでしまったチャーリー・パーカーが再び生を得て、新たな音楽を演奏することが可能になる。
この短編集の最初に収録されている「石のまくらに」も、一度だけ寝た女の子についての話であり、それだけなら過去の小説にも似たようなエピソードがあったが、この作品は彼女が詠んでいた短歌が、彼女自身よりも爪痕を深く刻んでいる。
彼女の名前も知らず、顔も覚えていない「僕」の手元に残っているのは、「ちほ」という筆名で綴った歌集だけだ。「僕」は彼女がもう生きていないのではないかと考える。すべてが消えてしまってもこの変色した歌集だけは残った、と。
この作品は読書会でも話題になったけれど、村上春樹の文体のなかに短歌が出てくることがそぐわないというか、不思議な印象を受ける。これらの短歌は作者が作った(といっても、もちろん作中の彼女の短歌として作ったのだが)のかと思うとさらに謎が深まるが、『猫を棄てる』で書かれていたように、父親が俳人だったということも関係しているのかもしれない。(読書会でも、父親の名前は「千秋」だという指摘があった)
「ウィズ・ザ・ビートルズ」も高校生の時のガールフレンドと、彼女の家に遊びに行ったときに遭遇した一風変わった兄についての物語であり、ここでは芥川龍之介の『歯車』が鍵になっている。「僕」は兄のリクエストに応えて、やむなく『歯車』の「飛行機」を朗読する。『歯車』は芥川が自殺する直前に書かれた文章である。
〈僕はもうこの先を書きつづける力を持っていない。こう云う気もちの中に生きているのは何とも言われない苦痛である。誰か僕の眠っているうちにそっと絞め殺してくれるものはないか?〉――『歯車』より
『歯車』はこの物語の展開を暗示している。また、『女のいない男たち』を再読して気づいたが、この「ウィズ・ザ・ビートルズ」は「女のいない男たち」とも通底しているようだ。どちらも映画『避暑地の出来事』から生まれたヒット曲『夏の日の恋』が不器用な恋を彩り、のちに「僕」は失われたものに思いを馳せる。
駒井さんはこの小説について(さらにこの本全体も)、人間の不可解さや心の闇を見事に描いていると評価されていた。たしかに、「ウィズ・ザ・ビートルズ」「女のいない男たち」どちらも、作品で切り取られた心の闇と、晴れわたった空のように健全な『夏の日の恋』との対照が心に残る。
「クリーム」では、知り合いの女の子に騙されて(さだかではないが)、神戸の山に迷いこんだ高校生の「ぼく」は、キリスト教の宣教車が「人はみな死にます」と告げているのを耳にする。
ぼくはそのキリスト教の宣教車が目の前の道路に姿を見せ、死後の裁きについて更に詳しく語ってくれるのを待ち受けた。なんでもいい、力強くきっぱりした口調で語られる言葉を
けれども宣教車は消え去り、見捨てられたような気持ちになった「ぼく」の前へ老人があらわれる。老人は唐突に「中心がいくつもあり、しかも外周を持たない円」の話をはじめる。この円について、私は「ぼく」同様になんのことやらと思っていたのだけど、読書会で聞いたところ、仏教学者であった鈴木大拙の思想らしい。
ここでまた、寺の息子として生まれて仏教系の学校で勉強を修め、のちに京大文学部へ進んだ作者の父親の姿と結びつけるのはあまりに安易かもしれないが、どうしても頭に浮かぶ。
どうしてこの作品がいつもの「僕」ではなく、「ぼく」なのかということも気になっていたが、この「ぼく」は作者だけではなく、神戸の名門私立校で教師をしていた父親に教えられた生徒たちも重ね合わされているように思えてくる。「へなへなと怠けてたらあかんぞ。今が大事なときなんや。脳味噌と心が固められ、つくられていく時期やからな」と生徒に日々教えていたのかもしれない。
そして一見、気楽なエッセイの延長のような「ヤクルト・スワローズ詩集」では、唐突に父親の葬儀のあとのエピソードが語られる。そこから「素敵な思い出」として、父親と甲子園球場に日米親善試合を見に行ったときに、サイン・ボールが膝の上に落ちてきた話が続く。
それは少年時代の僕の身に起こった、おそらくは最も輝かしい出来事のひとつだったと思う。最も祝福された出来事と言っていいかもしれない。僕が野球場という場を愛するようになったのも、そのせいもあるのだろうか?
『猫を棄てる』では父親について語ると銘打ちながらも、結局肝心なところは語られていないように思えて、少し物足りなかったけれど、小説という形式をとったこの本では、思いのほか雄弁に語っている。フィクションという虚構を通じてしか語ることのできないものがあるのかもしれない。
こうやって見ていくと、この本の前半に収録されているエッセイのような作品群にも、さまざまな仕掛けが仕組まれていることがわかる。それによって、現実の生と死が塗りかえられて新たな生が立ちのぼり、しまいこまれていた感情が浮かびあがってくる。
後半の「謝肉祭」「品川猿の告白」は前半の作品群よりも物語色が強まり、ある種の寓話のようだ。「品川猿の告白」はタイトルからもわかるとおり、『東京奇譚集』所収の「品川猿」の語り直しヴァージョンであり、名前を盗む猿が再び登場する。
ここでは愛する人の名前を盗むことが「究極の恋愛」であり、同時に「究極の孤独」だと語られる。「石のまくらに」でも、短歌を詠む女の子は「僕」と性交しているあいだ、愛する男の名前を叫ぼうとする。名前とはいったいなんなのか? ということについても考えさせられるが、その一方で、〈I ♥ NY〉とプリントアウトされた長袖シャツを着た猿が、群馬の鄙びた温泉宿で働いているという単純なおもしろさも楽しい。
『謝肉祭』はインパクトの強い一文からはじまる。
彼女は、これまで僕が知り合った中でもっとも醜い女性だった。
はじめのうち「僕」は、頭もよく趣味も洗練されている彼女に対して、「もう少しましな容貌であれば」魅力的だったであろうにと考えるが、その考えが薄っぺらい皮相的なものであったことを思い知らされる。
彼女はその特異な容貌を意識的に行使し、ダイナミックな存在感で「僕」や周囲の人々を圧倒する。彼女が辿る人生の数奇さと陳腐さは、まさに先にも書いた「人間の不可解さ」を具現化したもののように思える。
それにしても、その彼女のことを醜い女性呼ばわりしたり、「石のまくらに」の彼女を「美人と呼ぶには確かにいくらか無理が」あると書いたり、「ウィズ・ザ・ビートルズ」では、「僕」はもてたことは一度もないが、興味を持って近づいてくる女性はいつもどこかにいたと言ってのけたり、いい気なものだ……という批判に応えるために書いたのだろうかとすら思えるのが、最後に収められた書き下ろし「一人称単数」だ。
ここでは、「私」が珍しくポール・スミスのスーツを着てバーに行き、ウォッカ・ギムレットを飲んでいると、美人ではないが若いときは人目を惹いたであろう女性に突然話しかけられる。これまでに会った記憶はない。ギムレットなんか飲んでと絡んでくる女性に対して、(よせばいいのに)「ギムレットじゃなくて、ウォッカ・ギムレット」と訂正する。
「なんだっていいけど、そういうのが素敵だと思っているわけ? 都会的で、スマートだとか思っているわけ?」
見知らぬ女からまったく身に覚えのない謗りを受けるという不条理さから、夏目漱石の「夢十夜」や内田百閒の短編を思い出した。
また一方で、ギムレットというと忘れてはならないのが、『ロング・グッドバイ』である。「僕」ではなく「私」という一人称であり、謎の女にわけのわからない因縁をつけられているというのに、「大義の見えない争いは好むところではない」なんて悠然と語り、好奇心から話を聞いてしまうあたりもフィリップ・マーロウめいている。
「ギムレットには早すぎる」とテリー・レノックスはマーロウに語るが、まだギムレットを飲む頃合いではないと、作者も語っているのかもしれない。
短編集の最後に、村上春樹ブランドに異議を申し立てるようなこんな作品を持ってきたことが興味深い。『猫を棄てる』のときも書いたけれど、70歳を過ぎてもなおも守りに入らず、新たな領域を開拓しようとしているように感じられる短編集だった。
壊れた世界を救うのはだれか? 『壊れた世界の者たちよ』(ドン・ウィンズロウ著 田口俊樹訳)
『壊れた世界の者たちよ』の読書会に参加しました。はじめてのオンライン読書会のうえに、訳者の田口俊樹さんや担当編集の方もご参加されたので、なんだか緊張しました。
作者ドン・ウィンズロウは、ニューヨークの少年探偵ニール・ケアリーを主人公とした『ストリート・キッズ』でデビューし、繊細で心優しいニールやニールを父親のように見守るグレアムといったキャラクターが、当時のハードボイルド小説に新しい風を吹きこみ、ウィットに富んだ軽妙な語りで一躍人気作家となった。
しかし、のちに発表した『犬の力』以降の作品では、人気の基盤となっていた軽妙さや愛すべきキャラクターたちをいったん脇に置き、西海岸を舞台に「血で血を洗う」という言葉がふさわしい麻薬抗争を骨太に描いて、さらなる人気と評価を確立した。
そしてこの『壊れた世界の者たちよ』は、ウィンズロウがその歩みのすべてを詰めこんで総括し、新しい道へ一歩踏み出した中編集だと言える。
表題作であり最初に収録されている「壊れた世界の者たちよ」では、警察の麻薬取締班に所属するジミー・マクナブと麻薬犯罪組織との容赦のない抗争が描かれている。
悪の底が抜けた世界、まさに「壊れた世界」で生きる人間の戦いである。
あきらかに『犬の力』以降の筆致であり、やられたら絶対にやり返す、地の果てまでも追いかける、たとえ地獄に堕ちようとも――という凄惨な描写によって、読んでいる側にも問いが突きつけられる。
この壊れた世界に正義はあるのか? いったい何が正義なのか? と。
人は自らが壊された場所で強くなる。
その世界にいかに生を受けようと、人は壊れてその世界を出ていくのだ。
けれども、そのあとに続く「犯罪心得一の一」「サンディエゴ動物園」「サンセット」「パラダイス」は、もともとのウィンズロウの世界が――主人公と仲間たちによる気の利いた会話の応酬、美しい音楽、打ち寄せる波と波乗りたち、心ときめく出会いと切ない別れ、そこでは犯罪者すらもまぬけで憎めない――くり広げられている。
このなかで私が好きな「サンディエゴ動物園」は、どういうわけだか拳銃を手に入れたチンパンジーを巡査クリス・シェイが捕えようとする場面からはじまる。
クリスが拳銃の出処を突きとめようとすると、世にもまぬけな悪党たちに次々に遭遇し、そして動物園に勤務するキャロリンとのロマンスも生まれる……と、愉快なウィンズロウ節全開の作品であり、憎めない悪党たちを描いたら天下一品のエルモア・レナードに捧げられている。
この「サンディエゴ動物園」を読んだとき、訳者の田口さんが以前エッセイで紹介されていた、スティーヴン・キングがレナードを評した言葉を思い出した。
キングはレナードの文章を「雪のひとひら」に例え、「ひらひらと舞ってどこに着地するかわからない。そこが魅力だ」と評しているとのことで、そこで田口さんはレナードのストーリー展開についても「どこに着地するかわからない」ところが魅力であり、「よくある話なのに、さきが読めない」というのがエンタメ小説において重要な点ではないかと分析されていた。この「よくある話なのに、さきが読めない」という美点は、ウィンズロウの本作にもまさにあてはまるのではないだろうか。
(と、読書会でも感想として申し上げたところ、レナードはほんとうに先を決めずに書いていたらしいと教えていただきました。ウィンズロウもそんなに細かい点まで詰めていないのか、ところどころで矛盾が見つかり、いろいろ調整されたそうです)
そのほか、スティーヴ・マックイーンに捧げられた「犯罪心得一の一」では、この中編集の主役のひとりルー・ルーベスニック(ホンダシビックを愛する寝取られ刑事)と、頭の切れる悪党デーヴィスとの心理戦に目が離せない。
さらに、65歳になったニール・ケアリーが登場する「サンセット」はレイモンド・チャンドラーに捧げられていて、伝説のサーファー“テリー・マダックス”を 『夜明けのパトロール』のブーンが追いかける。
ハワイのカウアイ島を舞台にした『パラダイス』は、『野蛮なやつら』の「友好的三角関係」であるベンとチョンとOを筆頭として、おなじみのキャラクターが続々登場する。楽園での優雅な休暇を描いているのかと思いきや、案の定、麻薬抗争が勃発して……という展開で、楽園を追放された者たちが新たな楽園を作りあげる物語である。
と、従来のファンにとっては懐かしく、今回はじめて読んだ人はきっと過去作も読みたくなるにちがいない名品揃いなのだが、読書会の感想では、65歳のニール・ケアリーには微妙な感慨を抱いた方も多かったようだった。
たしかに私も、ニールのキャラや口調が若いときと変わっていないのに少し違和感があった、とはいえ、いきなり年寄りくさくなっていたら、もっと違和感を抱いたのはまちがいないので、キャラクターに歳を取らせるのは難しいものだなとあらためて感じた。(しかし、『ただの眠りを』の72歳のフィリップ・マーロウには、私はそんなに違和感を持たなかったのだが……読書会が再開されたら、みなさんの意見も伺いたい)
そして最後の「ラスト・ライド」は、また趣きががらりと変わり、いまアメリカで刻々と起きている社会問題をシリアスに切り取った作品である。
テキサスで生まれ育った主人公キャルは国境警備隊員として、「くそメキシコ人」が入ってこないよう有刺鉄線の張られたフェンスを日々パトロールしている。しかも、連れられて不法入国した子どもたちを、親から引き離して檻に入れている。
好きでやっているわけではない。父から受け継いだ牧場からはじゅうぶんな食い扶持が得られず、カウボーイの仕事も減る一方だからだ。ニューヨークタイムズやCNNといったリベラル系のメディアからは、自分たちが極悪人のように報道されているのも知っている。実際、先の選挙では「あいつ」に投票した。あの女に投票するわけにはいかなかったからだ。
おれは弱者に心を痛めるリベラルな左派じゃない。ああ選挙じゃ今の大統領に投票したよ。それでも、国が今やってるようなことに投票したわけじゃない。それだけは言っておく。
そんなキャルが檻の中にいるひとりの少女を助けようとする。自分でもなぜなのか、どうしてその子だったのかはわからない。そんなことをしたら職は言うまでもなく、これからの未来も、何もかも失ってしまう。ひとりを助けても意味がないと同僚女性のトワイラに言われる。それでも、キャルは少女を檻から連れ出し、愛馬ライリーとともに母親のもとへ返そうとする。
たいていの人間は大きな犠牲を払わずにすむなら、正しいことをするものだ。だけど、大きな犠牲が必要なときに正しいことができる者はきわめて少ない。
キャルは少女を救えるのか? というのが物語の主眼だが、キャルが救おうとしているのは少女だけではなく、この「壊れた世界」であり、つまりはアメリカそのものだと感じた。また自分自身への救いでもあり、閉ざされた心とイラクで負った傷を抱えるトワイラにとっても救いになるにちがいない。救うことができれば。この物語の顛末と落とし前を、読む側はどう受けとめたらいいのか考えさせられた。
「壊れた世界」を描いているという点で、冒頭の「壊れた世界の者たちよ」とつながる作品であり、中編集の最初と最後にこの二作を置いた構成の巧みさに、読書会でも感心の声があがった。そして「壊れた世界」をどう乗り越えていくのか、次の作品への指針として最後に置かれているように感じられた。
現在ドン・ウィンズロウは大統領選挙に向け、SNSなどで反トランプキャンペーンを熱心に展開している。その一方で、先の選挙でトランプに票を入れざるを得なかった市井の人々の気持ちを、見事に汲み取っている。そういう人たちこそが「正しいこと」を行う存在として描いている。
訳者の田口さんは、きれいごとばかり言って何ひとつ自らの手を汚そうとしない、西海岸や東海岸のリベラルなインテリ(当然、民主党を支持する面々)に向けた痛烈な批判だとこの作品を語っていた。
そういえば、同じく田口さんが訳されているボストン・テランも、『その犬の歩むところ』や『ひとり旅立つ少年よ』で、アメリカを総括して描こうとしている印象を受けたけれど、アメリカの作家にとっては、〈アメリカ〉そのものが永遠のテーマなのかもしれない。
読書会では、参加者全員がこの本でもっとも好きな作品を挙げていった。(短・中編集で読書会をすると、これで盛りあがれるのがいいところですね)
私は「ラスト・ライド」に票を投じたものの、一番楽しい「サンディエゴ動物園」に人気が集中するのではないかと思っていたが、意外にもどの作品も満遍なく人気があった。シリアスなものでもコミカルなものでも、質の高い作品に仕上げる作者の技量の高さのあらわれだろう。
さて、前代未聞のコロナ禍に直面し、こうやって読書会もオンラインに移行しつつある今日この頃、私たち大阪読書会も前へ進まないといけません。たとえ世界が壊れてしまっても読書のよろこびだけは壊さぬように、オンライン読書会の準備を進めようと思いますので、再始動の暁には、みなさまぜひともご参加ください。
憎しみにうち勝つために 『ザ・ヘイト・ユー・ギヴ あなたがくれた憎しみ』(アンジー・トーマス著 服部理佳訳)
カリルの体は、見世物みたいに通りにさらされていた。パトカーと救急車が、続々とカーネーション通りに到着する。路肩には人だかりができていた。みんな、のびあがるようにして、こっちをうかがっている。
『ザ・ヘイト・ユー・ギヴ あなたがくれた憎しみ』は、アメリカの青春ドラマでよく見かける光景 からはじまる。
仲間たちとの華やかなパーティー。音楽が大音量でかかり、アルコール片手に踊り、友達同士でおめあての相手やライバルについての噂をこそこそ語る。そんなありふれた場面がいきなりの銃声で一変する。
黒人街(ゲットー)の地元ガーデン・ハイツのパーティーにしぶしぶやってきた主人公スターは、そんな発砲騒ぎのなか、幼なじみのカリルに連れ出されて無事に脱出する。カリルの車に乗って一息つくが、初恋の相手でもあるカリルがどうやらドラッグを売っているらしいと気づき、胸に不安がよぎる。
そのとき、悲劇がおきる。警官に車を止められる。
スターは12歳になったとき、父親から大事な教えを聞かされていた。警官に呼びとめられたときは、とにかく言われた通りにしろ、と。手は見えるところに出しておけ。カリルもその教えを聞いたことがあるのだろうか?
警官はカリルの身体を調べるが、何も出てこない。何も問題はない。ところが、スターの身を案じたカリルは、やってはいけないことをしてしまった。警官が背を向けているあいだに動いたのだ。警官が銃を撃つ。スターの目の前でカリルは血を流して死ぬ。
唯一の目撃者であるスターは、警察から事情聴取を受ける。カリルは無抵抗だったのに警官が発砲した事実を伝えようとするが、警察はカリルがドラッグを売っていたことに固執する。案の定、ドラッグの売人であった不審な黒人男性を警官が射殺したと報道される。このままでは撃った警官が罪に問われることなく終わってしまう。
ガーデン・ハイツでは抗議活動がおきる。事件を目撃したトラウマと注目されることの恐怖から名乗り出ることができなかったスターも、もう黙ってはいられないと立ちあがる……
非常にリアルな小説だった。つい最近も、ミネアポリスで黒人男性ジョージ・フロイドが殺され、警官の処分をめぐる抗議活動が、Black Lives Matterというスローガンとともに全米に波及した。まるでこの小説が予言していたかのようにも思えるが、実のところは、以前から何度も何度もこんなことがくり返されてきたのだろう。
しかし、この小説が持つリアルさは、単に現実で頻繁におきている事件をテーマにしているからではなく、スターをはじめとする登場人物が持つ複雑な背景や心情が、ありがちな型にはめられることなく、複雑なままていねいに描かれているからだと感じた。
スターは異母兄のセブンとともに、両親(とくに母親)の意向で、裕福な白人が多く通うウィリアムソン高校に通っている。地元ガーデン・ハイツを愛していながらも、ここから脱出しないといけないという両親の複雑な思いを、セブンとスターも理解している。
だから、冒頭の舞台である地元ガーデン・ハイツのパーティーでは、居心地の悪い思いを味わっている。その一方で、ウィリアムソンではのびのびとふるまうことができない。どちらにも所属できない。常に自分を抑えて過ごしている。
ウィリアムソンのスターはスラングを使わない。ラッパーが使っても、白人の友達が使っても、絶対に使わない。ラッパーが口にすれば格好いいけど、ふつうの黒人が使ったら、ゲットー育ちに見えるだけだ。ウィリアムソンのスターは、腹が立つことがあっても、ぐっと我慢する。怒りっぽい黒人の少女だと思われたりしないように。
スターはこうやってガーデン・ハイツにいる自分と、ウィリアムソンにいる自分を使い分けて、学校生活をやり過ごしていた。しかし、カリルの事件が起きてからは、それが変わっていく。
カリルの事件に対する抗議活動を口実にして、学校で暴れて授業をボイコットしようとするクラスメートに違和感を覚える。差別的な冗談を口にする白人の友達ヘイリーに我慢できなくなる。自分を抑えつけていた枠が外れていくのがわかる。白人のボーイフレンドであるクリスとも、このままつきあい続けることができるのだろうか……?
セブンの場合はもっと複雑だ。
スターの父親とギャングのボスの愛人アイーシャとの子であるセブンは、スターのように白人社会とガーデン・ハイツのあいだで引き裂かれているだけではなく、ガーデン・ハイツのなかでも、スターの家と実母が生きるギャングの世界のあいだで引き裂かれている。
スター一家とともにガーデン・ハイツから脱出したいと願いつつも、実母や妹たちを見捨てることができないセブンの葛藤は、読んでいるこちらも胸が苦しくなる。
スターやセブンだけではない。
元ギャングであるスターの父親、一度はドロップアウトしかけたものの、スターをお腹に宿したまま大学に通い、看護師となったスターの母親、そして父親のように面倒をみてくれる、母親の兄であるカルロスおじさん……といった登場人物たちは、だれもがみな自分たちが生きてきた社会と、その外側の社会とのあいだで引き裂かれている。
スターの両親はガーデン・ハイツから去るべきかどうか悩み、警官であるカルロスおじさんは、カリルを射殺したことを正当化しようとする警察組織に所属していることに苦しむ。それぞれ異なる立場から、この事件を通じて、あらためて外側の社会に向きあい、一歩ずつ前へ進んでいくさまに希望を読み取ることができる。
といっても、現実においても、小説においても、差別や貧困をめぐる問題がそう簡単に解決するとは思えない。この小説では、ゲットーでドラッグや暴力がもたらす悲劇も赤裸々に描かれている。それでも希望が感じられるのは、人間は過ちを犯すものであるが、そこから立ち直ることもできるという信条が貫かれているからだろう。
印象に残った場面のひとつに、何度も過ちを犯した父親をどうして許したのか、スターが母親に尋ねるくだりがある。
「正直、わたしだったら絶対別れてるな。悪いけど」と。(私もそう思った)
そこで母親は、人は過ちを犯すものであり、犯した過ちより、その人に対する愛のほうが大きいかどうかで、決めるしかないと語る。
この小説のタイトルは、2パックの言葉 "The Hate U Give Little Infants, Fuck Everybody" から取られている。憎しみをぶつけられ続けた子どもが社会に牙をむく、という意味だ。
憎しみにうち勝つのは愛だ、なんていうと甘いのかもしれないし、クサ過ぎる気もする。それにもちろん、憎しみをぶつけてくる相手を愛することなんてできない。けれども、なにより怖いのは、憎しみをぶつけられることによって、自分のなかの愛が失われることではないだろうか。
この小説の登場人物たちのように、まわりの人間に対する愛があれば、厳しい状況であっても希望を失わず生きているのかもしれない、と感じた。なかなか難しいけれど。
女に世界を変えることはできるのか? 『あの本は読まれているか』(ラーラ・プレスコット著 吉澤康子訳)
『ドクトル・ジバコ』をご存じでしょうか?
アメリカを筆頭とする資本主義国陣営と、ソ連が率いる共産主義国陣営とのあいだに冷戦がくり広げられていた1950年代、ソ連の作家ボリス・パステルナークによって書かれた恋愛小説であり、ソ連では発禁扱いとされた。しかし、海外で出版されて大きな支持を集め、1958年にボリスはノーベル文学賞を受賞した。
そしてこの『あの本は読まれているか』は、『ドクトル・ジバコ』が出版に至るまでの複雑な経緯を、歴史上の事実をふまえてフィクションとして見事に作りあげた小説である。
物語は西側と東側から描かれる。西側は、『ドクトル・ジバコ』出版をもくろんだCIAが舞台となっている。といっても、ジェームズ・ボンドのような男のスパイが颯爽と活躍するわけではない。主人公となるのは、CIAで勤務していたタイピストたちだ。
わたしたちはラドクリフ、ヴァッサー、スミスといった一流大学を出てCIAに就職しており、だれもが一族で最初の大卒の娘だった。中国語を話せる者も、飛行機を操縦できる者もいたし、ジョン・ウェインよりも巧みにコルト1873を扱える者もいた。けれど、面接のときに聞かれたのは、「きみ、タイプはできる?」だけだった。
とあるように、せっかく大学を卒業して就職しても、CIAで与えられる仕事は男たちの会話をひたすらタイプするだけ。1950年代の話だから……と思う一方で、2020年になっても実はそんなに大きく変わっていない気もする。もう70年も経っているのに。
たまにバックグラウンドや素質を買われ、スパイらしい仕事に回される者もいるが、単なる運び屋だったり、女という武器を利用して相手側から情報を入手させられたりと、結局は男の「駒」に過ぎない。
イリーナとサリーもそうだった。
イリーナの両親は、まだイリーナが母親のおなかにいるときにソ連から脱出を試みた。だが、船に乗る直前に父親が捕まってしまう。母親は身重の身体で、ひとりアメリカへ渡る。そしてイリーナが8歳のとき、父親はソ連の収容所で心臓発作を起こして亡くなったと知らされる。
大学を卒業してから仕事を探していたイリーナは、知り合いからCIAでタイピストを募集していると聞いて応募する。タイプの腕に自信はなかったが、無事採用される。ところが、イリーナを待ち受けていたのはタイプライターではなく、サリーによるスパイの手ほどきだった。
華やかな容姿に恵まれたサリーは、第二次世界大戦中、諜報機関の一員として活躍していた。どんな立場の女にも見事になりきり、疑われることなく相手の男の懐に入ることを得意としていた。
しかし、戦争が終わり、諜報隊員たちはそれぞれの生活へ戻っていった。ひとつの場所に居つくのは性に合わない。けれども、これ以上男たちを渡り歩くのも、堅気の仕事につくのも気が進まない。なんといってももう30半ばなのだから。そこへ昔の仲間から電話があり、迷うことなく仕事を請けた。
こうしてイリーナとサリーは、CIAによる『ドクトル・ジバコ』出版作戦に関わるようになる。しかし、サリーにはだれにも言えない秘密があった……
東側では、『ドクトル・ジバコ』の作者ボリスと、公私にわたってボリスを支えた愛人オリガ・イヴァンスカヤが描かれる。ボリスはもちろん、オリガも実在の人物であり、東側の物語はおおむね史実に基づいているようだ。
第一章のタイトルが「ミューズ」となっているように、オリガはまさにボリスのミューズであり、実際に『ドクトル・ジバコ』のヒロインであるラーラのモデルになっているらしい。
けれどもオリガの人生は、芸術家のミューズという言葉から想像されるような優雅なものではまったくない。
第一章「ミューズ」は、黒い背広姿の男たちが家にやってくる場面からはじまる。泣きわめく子どもたちの声を聞きながら、オリガは男たちに連行される。オリガは矯正収容所に送られ、「反体制的見解を持つ作家パステルナークの作品を褒めそやしてきた」という罪で、懲役5年の刑を言い渡され、シベリアで過酷な労働に従事させられる。
わたしはセミョーノフが聞きたがっていることを話さなかった。小説はロシア革命に批判的で、ボリスは社会主義リアリズムを拒絶しており、国家の影響を受けずに心のまま生きて愛した登場人物を支持していると、教えはしなかった。
前回紹介した『チャイルド44』と同様に、この時代のソ連では、スターリン体制を支持しない者は、「反体制」と見做されて収容所に送られる。
ソヴィエト連邦は完璧に正しく幸せな社会であり、貧困や犯罪といった資本主義国に特有の悪は存在しない。それなのに、ボリスはロシア革命に翻弄される人々の姿を書いた。到底許すことができない。しかし、世界的にも高名な作家であるボリスには、そう簡単に手出しできないので、ボリスへ圧力をかけるためにオリガを捕まえたのだ。
だが、ソ連にとって最大の事件が起きる。スターリンが死んだのだ。5年の刑期が3年に縮小され、解放されたオリガは愛するボリスのもとへ向かう。
ボリスは自分のことを待っていてくれるのだろうか? 収容所に送られる前から、ボリスは何度も別れ話を口にしていた。妻ジナイダとオリガのあいだで板挟みになっていることに苦しんでいたのだ。そもそもボリスはオリガが捕まっているあいだ、いったい何を考えていたのか……?
ここから『ドクトル・ジバコ』がまず海外で出版され、そしてCIAの手引きによってソ連にこっそり逆輸入されていく展開が、イリーナやサリーといったタイピストたち、そしてオリガの視点から語られていく。
こういった女たちは、それまでの物語では男の添え物のように扱われていた存在だ。
スパイ小説に出てくる脇役の女たち。タイピストであろうが、諜報活動の紅一点であろうが、男を助けようが、あるいは男の邪魔をしたり裏切ったりしようが、世界を動かす主役はあくまで男であった。ミューズにインスピレーションを与えられて創作し、世界に感動と驚きを伝えるのも男であった。
けれどもこの小説では、女たちが自ら考え、主体的に行動し、陰謀が渦巻く世界をたくましく生き抜いていくさまが描かれている。
この小説の大きなテーマのひとつは、「一冊の小説で世界を変えることができるか?」であるが、もうひとつのテーマは「女に世界を変えることができるか?」だと感じた。
さて、先日この小説についてオンライン読書会が行われました。こちらのサイトで見ることができます(無料で)。
この読書会でも、やはり「女たちの物語」というところに焦点がおかれ、西側の章の語り手となる「わたしたち」とはだれか? など、いくつもの興味深い問題について語られました。
登場人物一覧と照合してみても「わたしたち」を特定することはできず、この物語の主人公は、イリーナでもサリーでもオリガでもなく、女たちのすべて、あるいはその連帯なのだということが印象に残りました。
そのほか、ボリスはダメ男か? という疑問や(案の定、ダメ男説を主張する人が優勢でした)、世界を変えるのに文学は有効なのか? などなど さまざまな観点からこの小説を読み解いています。
また、邦題が決まるまでの経緯(原題は“The Secrets We Kept”で、内容に即したいい題なのですが、そのまま訳すと、ありがちなタイトルになってしまいかねないのも事実ですね)や、本を届けるためにはテーマを絞る、などといった担当編集者の方のお話も勉強になりました。読み終えた方はぜひともご覧ください。
連続殺人事件を通じてソヴィエト連邦の「不都合な真実」を描く 『チャイルド44』(トム・ロブ・スミス著 田口俊樹訳)
この社会に犯罪は存在しないという基盤を。
国家保安省捜査官の義務として――義務と言えば、人民すべての義務だが――レオはレーニンの著作を学習し、社会の不行跡である犯罪は貧困と欠乏がなくなれば消滅することを知っていた。
遅ればせながら、『チャイルド44』を読みました。
2008年に新人作家トム・ロブ・スミスのデビュー作として出版され、その年のCWA賞最優秀スパイ・冒険・スリラー賞を受賞し、日本でもすぐに翻訳出版され、『このミステリーがすごい! 2009年版』海外編の第1位となった人気作です。また2015年には、リドリー・スコット監督によって映画化もされました。
1933年、当時ソヴィエト連邦の支配下にあったウクライナは大飢饉に襲われていた(ちなみに、小説では多く語られていないが、ウィキペディアにこの大飢饉(ホロドモール)についての項目がある)。どの家の食糧も底をつき、家畜や木の根や草などもことごとく食べ尽くし、人々は瀕死の状態に陥っていた。
そんなとき、パーヴェル少年は森で猫を見かける。生きている猫がまだ存在していたとはすぐには信じられず、幻ではないかと自分の目を疑う。10歳にして一家の命運を背負ったパーヴェルは、猫を捕まえようと幼い弟アンドレイを連れて森へ入る。これで母さんも弟も生き長らえることができるのだ。ところが、不慮の事態が起きる……
物語の舞台は1953年のモスクワに移る。先の戦争の華々しい英雄として、前途有望な国家保安省捜査官となったレオは、幼い息子を亡くした部下フョードルの家へ向かっていた。フョードルを慰めるためではない。
なんということか、フョードルは息子が殺されたと考えているらしいのだ。
殺人は資本主義の病だ。よって祖国ソヴィエトには、そんな犯罪など存在しない。それなのに、よりにもよって国家保安省に勤める者がそんな疑いを抱いているなんて、到底あってはならないことだ。そこで、悲しみのあまりに度を失いつつあるフョードルを正しい道に戻すため、レオが動いたのだった。
案の定、フョードルとフョードルの母親は、口の中に泥をつめこまれ、裸で発見された息子が列車に轢かれて死んだはずがないと主張する。しかし、息子を連れていた怪しい男を見たと語った女が、国家保安省が出てきたことによって証言を翻したので、レオはフョードル一家の言い分を封じ込めることに成功する。国家の秩序が保たれたことに安堵した。
ところが、フョードル一家に手をわずらわされているあいだに、監視していたスパイ容疑の男に逃亡されてしまう。部下たちを率いて捜索に出るが、副官ワシーリーがレオの言うことに従わず、捜索隊の足並みが揃わない。ワシーリーはレオの地位を奪おうとしていたが、あてが外れたため暴走し、残虐な行為におよぶ。捜索隊の前でレオに叱責され、ワシーリーは復讐を誓う。
そうしてまたレオのもとに、新たに調査すべきスパイ容疑者の情報が届く。その容疑者とは――レオの最愛の妻ライーサであった。
ワシーリーの陰謀だろうか? レオはそう疑いつつ、ライーサを心の底から信じることができない自分に気づく。
スパイ容疑をかけられたライーサとレオはモスクワを離れ、辺鄙な村へ追いやられる。そこでレオは、口に泥をつめこまれてむごたらしく死んだ少女の話を聞く。以前、自分が葬り去ったフョードルの息子の事件を思い出す。もしかしたら、自分はとんでもない過ちを犯したのだろうか……?
この物語で描かれる「祖国」ことソヴィエト連邦の姿は、まるでディストピア小説の世界のようだ。
殺人や貧困といった資本主義の病は存在しない。存在を認めることは、前進している社会を大きく逆戻りさせてしまうことになる。よって、連続殺人が起きていても、そのことを一切認めようとせずに葬り去る。もしくは、知的障碍者や同性愛者といった、ソヴィエト社会の一員ではない者、「共産主義や政治の埒外にいる人間」のせいにする。
一方で、「政治犯」は存在する。いや、実際に存在するかどうかは問題ではない。「政治犯」と見做されてしまえば、存在することになるのだ。
「政治犯」とは、資本主義国と通じたスパイや、破壊活動を行う革命家だけを指しているわけではない。「ソヴィエトの権力を覆そうとしたり、打ち倒そうとしたり、弱めようとした者」すべてがあてはまり、体制に疑問を抱いただけでも、「政治犯」とレッテルを貼られかねない。自らの保身や出世のため、平気で他人を陥れる者もいる。噂と密告がはびこる、恐怖に支配された社会。
恐怖というものは必要悪だ。恐怖が革命を守っている側面を見落としてはならない。
先にディストピア小説のようと書いたけれど、言うまでもなく、ソヴィエト連邦は実際に存在した国である。
この事件も、ソヴィエト連邦で実際に起きた連続殺人事件をモチーフにしている。 1978年から90年に渡り、アンドレイ・チカチーロという男が52人もの若い男女を凌辱し、殺害した事件である。ソヴィエト連邦では殺人は存在しないという信念があったため、これほどまでの長期間にわたり、殺人者が捕まることなく野放しにされていたのだ。
さらに、物語の冒頭で描かれたウクライナの大飢饉についても、当時のソヴィエト連邦は、五か年計画の成功を喧伝していたため、飢饉の存在を認めようとせず、他国からの援助を受け入れようともしなかった。結果として、死者の数は数百万人から一千万人以上とも言われ、現在ではジェネサイド(大量虐殺)として考えられている。
連続殺人事件の舞台を1950年代に変え、ウクライナの大飢饉と結びつけたことによって、国家がかりでついた嘘と、その犠牲になった登場人物たちの運命がいっそう劇的なものになり、真実に目覚めたレオと、命の危険を冒してレオに協力する人々の姿が強く印象に残る。また、この物語の舞台となった1953年は、スターリンの死によってソヴィエト連邦の終わりがはじまった象徴的な年でもある。
きみたちのことを一番愛しているのは誰ですか。正解――スターリン。
きみたちは誰を一番愛していますか。正解――同上(誤答は記録される)。
なにより、この小説で一番考えさせられるのは、レオの覚醒である。
優秀な官僚として、国家の欺瞞に薄々気づきながらも、深く考えようとせず目をつぶり、国家に忠誠を誓っていたレオが策略にはめられ、すべてを失ったことによって、ひた隠しにされていた真実の存在に目を向けるようになる。
国家に対する姿勢と同様に、最愛の妻ライーサとも心の底から通じ合えていないこと、相手の忠誠を完全には信じられないことに薄々気づきながらも、正面から対峙することなく目を背けていた。しかし、ライーサにスパイ容疑がかけられたことをきっかけに、ライーサの本心、その真の姿に遅まきながらも気づきはじめる。
レオはソヴィエト連邦という大帝国のエリートであるが、この点については、現在の日本に生きるふつうのサラリーマンにも共感できる要素があるかもしれない。
自分の仕事や会社に疑問を抱きつつも深く考えないようにしたり、妻や家族との意思疎通に困難が生じていても、正面から対峙することなく目を背けたりする人は少なくないのではないだろうか?
不都合な真実、というのは、あらゆるところで使われがちな言葉であるけれど、そういうものから目を背け続けていると、国家レベルにおいても、個人レベルにおいても、破綻が必ず訪れるということを感じ入った小説だった。
娘のような母と母のような娘の切れない絆 『タトゥーママ』(ジャクリーン・ウィルソン著 小竹由美子訳)
「いいの。だって、マリゴールドがわたしのお母さんなんだもん。」
喜ばせようと思ってこういったのに、マリゴールドはまた泣きだした。
「あたしったら、なんてバカな母親なのかしら。どうしようもないね。」
「この世でいちばんのお母さんだよ。おねがいだからもう泣かないで。目がまっ赤になっちゃう。」
ジャクリーン・ウィルソンによるヤングアダルト小説、『タトゥーママ』(小竹由美子訳)を読みました。
主人公のドル(ドルフィン)は、母親のマリゴールドと姉のスターと暮らす10歳の女の子。
マリゴールドはきれいでスタイルもよく、絵の才能があり、自分がデザインしたカラフルなタトゥーを全身に入れている。ドルはそんなマリゴールドを、「世界じゅうで、いちばん魅力的」なママだと思っている。
けれども、マリゴールドは時々おかしくなる。昔の恋人であり、スターの父親でもあるミッキーを忘れられないのだ。仕事もせず、ふさぎこんで泣いてばかりいたかと思うと、急にハイテンションになる。お酒を飲みに行って、一晩中娘たちをほったらかしたりもする。
ママに似た美人でしっかり者のスターは、これまでずっとマリゴールドとドルの面倒をみてきたけれど、八年生(中学生)になり、マリゴールドにすっかり愛想をつかしてしまう。
そんなある日、ロックバンドのエメラルドシティーが再結成コンサートを開く。ミッキーが大好きだったバンドだ。そこに行けばミッキーを見つけられるはずだと、マリゴールドはいそいそと出かける。なんと思惑通りに再会し、娘のスターの存在をはじめて知ったミッキーは感激する。
これでミッキーと一緒に暮らすことができると信じるマリゴールドだが、ミッキーはスターだけを引き取ろうとする。またもミッキーに捨てられたマリゴールドは、ますますおかしくなり、残されたドルは必死にマリゴールドを支えようとするが……
胸が苦しくなる物語だった。
いびつな愛し方しかできないマリゴールドに胸が痛くなった。
十年以上も昔、ほんの2、3週間付き合っただけのミッキーを運命の人と思いこみ、いつまでも慕い続ける。それからどんな男と付き合っても、ミッキーのかわりにはならない。
娘たちへの愛情もコントロールできない。「あたしって駄目な母親」と言って泣きだしたかと思うと、ぶかっこうなクッキーや生焼けのケーキを食べ切れないほど大量に作る。転校をくり返してきたせいで、ドルに友達がいないと知ると、学校に押しかけて、ドルの友達になってくれるようクラスメートに頼む。愛情過多で、そしてだれよりも愛情に飢えている。
そんなマリゴールドを受けとめ、支えようとする健気なドルの姿がなにより切なかった。マリゴールドの関心が完全にミッキーとスターに向いていても、マリゴールドを見捨てたりはしない。スターもそんなマリゴールドにあきれ、いったんは父親のミッキーのもとに行くけれど、やはりマリゴールドとドルを見捨てることはできない。
「あんな人、大っきらい。」スターは小声でいった。まるではきだすように。
「そんなことないでしょ。」わたしはあわてていった。
「ううん、きらいだよ。」
「大好きなんでしょ。」
「あの人はどうしようもない役立たずの母親よ。」とスター。
「そんなことない。わたしたちのこと、愛してるんだよ。……
ジャクリーン・ウィルソンはイギリスで人気の児童文学作家だが、どの作品においても、大人の愚かさや、子どもを取り囲む現実の厳しさを容赦なく突きつける。
「どんな親でも無条件に子どもを愛するもの」という建前を描いたりはしない。
『ダストビン・ベイビー』のエイプリルは、生まれてすぐにゴミ箱に捨てられる(だから「ダストビン・ベイビー」)。
『シークレッツ』のトレジャーは、義理の父親に革のベルトで殴られ、実の母親も義理の父親の味方をする。トレジャーの親友となるインディアの母親は有名なファッション・デザイナーであるが、太っている娘をみっともなく思い、関心を持とうとしない。
だからこそ、マリゴールドの純粋な愛情がいっそう胸を打つ。でも、母親として上手に愛することができない。一方、娘たちは、「マリゴールドファンクラブのナンバーワン」とスターに言われるドルはもちろん、マリゴールドに批判的なスターも、やっぱり母親のことが「大好き」で離れることができない。
主語を大きくするのは乱暴な言い方かもしれないけれど、女性ならだれでも、何があっても切ることのできない母と娘の絆に強く感じるものがあるのではないだろうか。
互いに愛情を持っているのに、それゆえにがんじがらめになり、身動きがとれなくなることは、どの親子間にも起こりうる。家庭というのは閉ざされた空間なので、外部の人間が介入しないと窒息する場合もある。
この物語においても、そういう外部からの救いの手がうまく用意されている。子どもは外部の人間と接し、自分の家以外の場所を知ることで成長する。
マリゴールドとスターにしか心を開くことができなかったドルも、新しい友達や信頼できる大人と出会い、自分の世界を広げていく。
マリゴールドは成長することができるのだろうか? 「まとも」な母親になることができるのだろうか?
それはわからない。でも物語の最後、冒頭と変わらず「あたしって駄目な母親」と泣き崩れるマリゴールドが、かつての自分がなりたくなかった母親像と自分もまったく同じなのではないかと気づく瞬間、何かが少し成長したのかもしれない。
「まとも」な母親にはなれないかもしれない。でもそれでいい。ドルもスターも「まとも」じゃないママを愛しているから。
ところで、大人の都合に翻弄される健気な子ども――子どもみたいな大人と大人みたいな子ども――を描いた物語として、まずは『じゃりン子チエ』が頭に浮かぶ。
ストーリーは紹介するまでもないだろうけど、小学生のチエちゃんが大人より賢く、そして小鉄やアントニオといった猫が人間より賢い、というのがこのマンガのおもしろさだ。
あと、岡崎京子の『ハッピィ・ハウス』も思い出した。13歳にしてヘビースモーカーのるみこは、パパとお兄ちゃんが出ていった家にさっそく男をひっぱりこむママを追い出して、たったひとりで、いや、ぬいぐるみのうさことふたりで、「本当の家」での生活をはじめる。
そして、昔の恋を忘れられない母親を描いた物語として、江國香織の『神様のボート』も胸に残る一冊である。
現実と妄執のあわいをさまよう母親とともに各地を転々とする娘。成長する娘は、否応なしに現実に目を向けるようになる。現実を生きていない母親に違和感を抱きはじめる。
現実と向きあって生きていくのが大人のあるべき姿なのだろう。けれども、そんなふうに生きることのできない大人もいる。そんな大人であっても、子どもにとっては切っても切れない親であり――親子関係とは難しいなとあらためて感じる。
べつの言葉によって自らを変容させていく試み 『べつの言葉で』(ジュンパ・ラヒリ著 中嶋浩郎 訳)
人は誰かに恋をすると、永遠に生きたいと思う。自分の味わう感動や歓喜が長続きすることを切望する。イタリア語で読んでいるとき、わたしには同じような思いがわき起こる。わたしは死にたくない。死ぬことは言葉の発見の終わりを意味するわけだから。
『停電の夜に』『その名にちなんで』など、日本でも高い人気を誇るインド系アメリカ人作家ジュンパ・ラヒリは、イタリア語を愛するあまりに「イタリア語と結びつくために」、40歳を過ぎてアメリカから家族とともにイタリアに移住する。イタリア語の本だけを読むというのはアメリカにいたときからすでにはじめていたが、移住してからはイタリア語だけで生活し、ついには作品すらもイタリア語で書きはじめる。
冒頭の引用では、イタリア語との関係を恋になぞらえているが、たしかにラヒリのイタリア語へののめりこみぶりは、恋愛に耽溺するのによく似ているように感じられる。この『べつの言葉で』の前半部分では、そのあまりの傾倒ぶりに当惑すら覚えてしまうが、読み進めていくうちに、ラヒリがイタリア語を求めた理由があきらかになっていく。
インド人の両親を持つラヒリが最初に身につけた言葉は、両親が話していたベンガル語であった。しかし本を読みはじめ、学校にも通うようになると、ラヒリの中でベンガル語は後退し、かわりに英語と一体化していった。英語はアメリカで生きていくうえで欠かせない言葉でもあった。
けれども、両親は娘が英語を使うことを快く思っていなかった。一方、娘は友達の前でベンガル語を話すのが恥ずかしかった。アメリカの店では、訛りのある英語を話す両親を無視して、自分に問いかけてくる店員に腹が立った。そしてまた、間違った英語を話す両親にもいらいらした。
わたしのこの二つの言語は仲が悪かった。相容れない敵同士でどちらも相手のことががまんできないようだった。その二つが共有しているものはわたし以外に何もないと思ったから、わたし自身も名辞矛盾なのだと感じていた。
イタリア語を勉強するのは、わたしの人生における英語とベンガル語の長い対立から逃れることだと思う。母も継母も拒否すること。自立した道だ。
こうして、ジュンパ・ラヒリは第三の言語としてイタリア語を学びはじめ、ついにはイタリア語で生きていくことを選択した。しかし、イタリアに行ったからといって、アメリカで感じた呪縛から完全に逃れることができたわけではない。
イタリアの店に行くと、店員はラヒリに「どこからおいでですか?」と尋ねる。しかし、自分よりずっとイタリア語が下手な夫には何も聞かない。顔かたちと名前(アルベルト)のせいで、「ご主人はイタリア人でしょう」と決めつけられる。さらには、「イタリア語はご主人から習ったのか」とまで言われる。そんなときは打ちのめされた気持ちになる。
(話は逸れるが、「主人」という言葉をめぐる問題があるけれど、こういう台詞を吐く人が使う言葉は「夫」ではなく、絶対に「ご主人」なのだろうなとつくづく思う)
アメリカのボストンに居た頃、町ですれちがった男に「くそったれ、英語が話せねえのか」と怒鳴られたことや、あるいは、両親の故郷であるインドのコルカタでは、アメリカ育ちだからベンガル語なんてわかるわけないと決めつけられ、英語で話しかけられた思い出が蘇る。どこへ行っても自分の言葉を話すと驚かれる。どこへ行っても所属できない気持ち。
生まれ育った国で「外国人」とみなされる親を持つ子どもは、どこにも所属できない気持ち、余所者であるかのような一種の疎外感を抱えてしまうのかもしれない。
ブレイディみかこの『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』というタイトルは、息子のちょっとした落書きがもとになっていて、タイトルからもその心情がうまくあらわれている。
イギリス人である夫と日本人である作者を親に持つ息子は、イギリスの労働者階級の町にある中学校ではたったひとりの東洋系として人目をひき、日本に来ると「ガイジン」としてじろじろ見られる。ときには「日本語話せないのか」とおっさんにからまれたりもする。息子はこうつぶやく。
「日本に行けば『ガイジン』って言われるし、こっちでは『チンク』とか言われるから、僕はどっちにも属さない。だから、僕のほうでもどこかに属している気持ちになれない」
『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』の最終章で、息子はギターを手にしてロックを鳴らすことで、「ブルー」を変えていこうとする。
『べつの言葉で』のラヒリはイタリアで暮らし、いまだ確固とした隔たりを感じる不完全なイタリア語で作品を書くことによって、自らを変化させて自由になろうと試みる。
別の人間になりたいと願う翻訳家の女がいた。はっきりした理由があってのことではない。ずっとそうだったのだ。
というのが、ラヒリがイタリア語で書いた最初の掌編小説「取り違え」の冒頭である。べつの言葉によって別の人間になりたいと願う女。オウィディウスの『変身物語』を愛するラヒリの強い思いが投影されている。
「ずっとそうだったのだ」と書いているように、この願いはイタリア語に傾倒するようになってから芽生えたわけではない。
英語で書かれたラヒリの作品を翻訳してきた小川高義による『翻訳の秘密』を読むと、初期作品から一貫してラヒリは「わからないこと」に身を浸し、それを「解釈」することで自らを「変容」させてきたことに気づかされる。
ラヒリのデビュー短編集『停電の夜に』の原題は、 短編のタイトル ”Interpreter of Maladies” が採用されており、interpretは単なる「通訳」という意味ではなく、異なるものやわからないものを解釈しようとする試みだ、と小川さんは考察している。
さらに、ラヒリがネット上で発表したエッセイの結びの言葉 ”I translate, therefore I am” に焦点をあて、translationは「翻訳」というより「変容」のニュアンスが強く、ときには「場所の移動」を含むことさえあると指摘し、「わからないものを解釈しようとして、みずからの変化も生じる」ことが、まさに「ラヒリのテーマそのもの」としている。2007年の文章だが、まさに現在のラヒリを予言した読解だと思った。深く読むことによって、作者が進んでいく方向も見えてくるようになるのだろう。
先の掌編小説「取り違え」は、翻訳家の女が黒いセーターを取り違えられる物語である。彼女は自分のセーターを取り戻すことができたのか? 別の人間になることができたのだろうか?