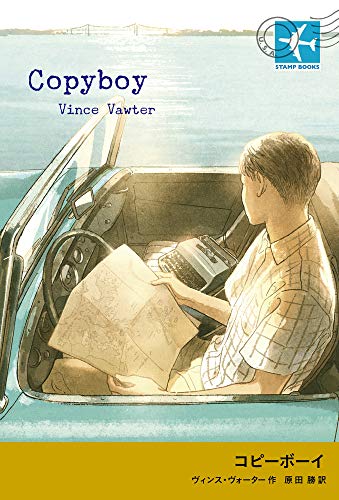差別する側の「誤った決断や行動、事後の後悔」を描いた 『兄の名は、ジェシカ』(ジョン・ボイン著 原田勝訳)
ジョン・ボイン『兄の名は、ジェシカ』を読みました。
以前に紹介した二作『縞模様のパジャマの少年』『ヒトラーと暮らした少年』は、どちらもナチスドイツの支配下にあったヨーロッパを描いていたが、今作は現代のイギリスが舞台となっている。
主人公である語り手の「ぼく」は14歳で、4歳年上の兄ジェイソン、政治家の母親、母親の秘書を務める父親と暮らしている。
難読症のため読み書きが苦手なうえに、スポーツも得意ではない「ぼく」と異なり、ジェイソンはプロを目指すようスカウトされるほどサッカーが得意な学校の人気者で、忙しい両親に変わってずっと「ぼく」の面倒をみてくれていた。ジェイソンはヒーローそのものだった。
ところが、最近ジェイソンのようすがおかしい。「ぼく」や両親と距離を置くようになり、部屋にこもる時間が増えた。一度、部屋をのぞくと泣いているときがあった。しかも、どういうわけかブロンドの髪を伸ばしはじめ、変な段カットにしている……
そしてある日、家族全員に話があるとジェイソンが切り出す。
不安を感じた「ぼく」は、「ジェイソンは世界で一番の兄さんなんだから、ね」と口にして、わざと子どもっぽく甘えてみせる。ジェイソンは黙りこんだあと、おまえの兄さんじゃないと否定する。
ぼくはとまどったまま、ジェイソンの顔をじっと見ながら、ききかえした。「どういう意味?」
「言ったとおりさ。おまえの兄さんじゃない。ほんとうは、姉さんなんだと思う」
ジェイソンの性自認は女性であり、つまり、トランスジェンダーだと家族に告白する。
現代はゲイやレズビアン、トランスジェンダーをカミングアウトしている人も多く、昔にくらべると偏見も少なくなっていると思う。
けれども、いざ自分の血縁者に告白されると戸惑ってしまう人が大半ではないだろうか。「ぼく」や両親も例にもれず、一家の星であったジェイソンの告白を受けとめられない。聞かなかったことにしてしまいたい。母親は二度とそんなことを口にするなと言い、父親は電気ショック療法で治るのではないかと考える。
しかし、ジェイソンの見かけはどんどんと女らしくなり、「ぼく」は学校で散々笑い者にされ、“宿敵”のいじめっ子たちからは変態野郎という罵声を浴びせられる。それもこれもぜんぶジェイソンのせいだと恨むようになり、ある行動に出る……
この本を読み終えて、あらためてジョン・ボインが描く登場人物の設定や配置の絶妙さに感心した。
『縞模様のパジャマの少年』の主人公である少年の父親はナチスの高官であり、少年はフェンスで囲まれた建物(収容所)にはどんな人たちが入っているのか、内部で何が行われているのか、まったく知らない。その無知と鈍感さに読んでいる側はもどかしい思いを抱く。
『ヒトラーと暮らした少年』では、主人公の少年の悲しい生い立ちに同情した読者も、そのあと少年がヒトラーにすっかり感化されていくさまに困惑と苛立ち、そして悲しみを覚える。
この『兄の名は、ジェシカ』においても、ジェイソンを受けとめて応援する人が周囲にあらわれても、なかなかジェイソンの選択を認めようとしない「ぼく」や両親の無理解ぶりに胸が痛くなる。
先日、訳者の原田勝さんによるセミナー「訳した本がジャンルを作る──海外児童文学・YA文学に描かれる戦争と差別」で、下記の視点が挙げられていた。
視点(2)文学による疑似体験
*侵略される側・差別される側の「痛み」
*侵略する側・差別する側の「誤った決断や行動、事後の後悔」
*全体の枠組みや環境の中で、冷静に問題を考える機会を提供
*単なる情報ではなく、物語として提示する意義や力(まず文学として質が高いこと)
*基本的に一人で行なう営みである読書を通じて、問題を深く認識する可能性。それをサポートするための、翻訳の工夫(読みやすさ、訳注、解説)
ジョン・ボインの一連の作品は、〈侵略する側・差別する側の「誤った決断や行動、事後の後悔」〉を描くことで、〈侵略される側・差別される側の「痛み」〉が読者に強く伝わり、当事者であるというのはどういうことか、じっくりと考えさせられる構成になっている。
また、最後に添えられた作者あとがきで、ジョン・ボインは「トランスジェンダーであることがどういうことか、わたしは身をもって知っているわけではありません」と断りつつ、自らがゲイだと意識しはじめたときの気持ちを綴り、まわりの人とちがうということがどれだけ恐ろしいか、切実に語っている。
迫害されている人たちのために立ち上がらなければ、結局それは、わたしたちが迫害する側に回ることになります。いじめられている人たちによりそわなければ、わたしたちはいじめの共犯者です。
この小説は両親の描写もかなり興味深い。母親は首相の座を狙えるほどの政治家であり、そのサポート役を父親が務めているが、両親が抱いている価値観は古臭く、ジェイソンを認めようとしない。
日本でも、自らは旧姓で働きながら選択的夫婦別姓に反対する保守的な女性政治家が存在するし、イギリスにはなんといってもサッチャーという偉大なる先達がいたことを思い出すと、この人物造形にも説得力を感じる。
母親に向かって「EU離脱に尽力くだすってありがとう」と声をかける年輩の女性が、「わかってちょうだい、わたしくらい偏見のない人間はいないわ。車には、エルトン・ジョンのヒット曲集のCDだって積んでるし」と言ってのける場面など、至るところでミュージシャンをネタにしたジョークが出てくるのには笑えた。
「ぼく」が一時はまっていたエド・シーランが再三ネタになっていたり、両親がジェイソンを連れていく精神科医がコールドプレイのクリス・マーティンそっくりだったり、そしてなんといっても、「三十五歳を過ぎたら絶対にやっちゃいけない十のこと」のひとつに、「オアシスみたいな、もう何年も前にはやったバンドの話をすること」があるのには、いつの間に見られていたのか? と思った。
(けど、こんなことを言うセンスは14歳の「ぼく」のものではなく、作者ジョン・ボインの感覚だと思うが)
そう、LGBTや性自認を取り扱いつつも、筆致は軽妙で笑える要素も多いので、差別や社会問題を描いた作品は深刻で難しそう……という印象を持っている方や、『縞模様のパジャマの少年』がつらかったという方も、この作品ならすっと物語に入りこめると思います。
ここからジョン・ボインのほかの作品や、吃音に悩む少年を描いた『ペーパーボーイ』、その続編にあたる『コピーボーイ』など、原田勝さんが訳されたほかの作品を読み進めていくのはどうでしょうか?