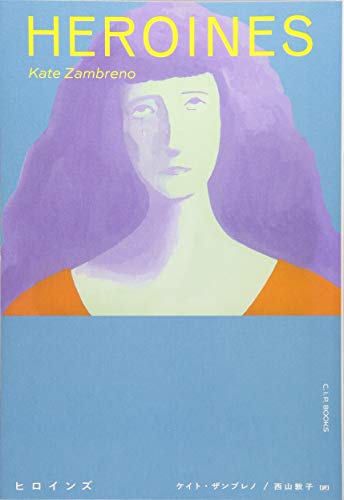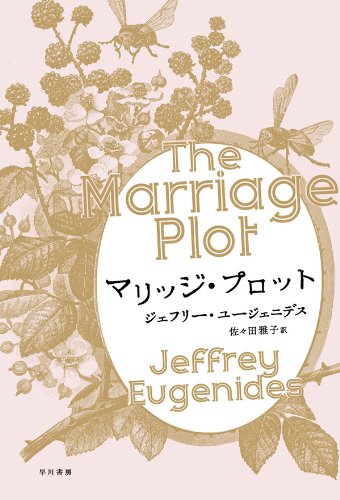移民の娘、そしてエリート女子として、「わたし」のこじれたアイデンティティ――ウェイク・ワン『ケミストリー』(小竹由美子訳)
ウェイク・ワン『ケミストリー』(小竹由美子訳)を読みました。
中国系アメリカ人として生まれた「わたし」は、両親の期待を背負って博士課程へ進学した。そこでエリックと出会って一緒に暮らしはじめ、ついにはプロポーズされる。
けれども、エリックについていく決心もできず、かといって勉学に集中することもできない。両親は娘である自分が輝かしい業績をあげることを願っているが、両親のことを考えれば考えるほど、目の前に立ちはだかる現実に足がすくむ…………
こうやって要約すると、博士課程というエリートコースに進み、さらにエリートであるうえに心優しく、自分を愛してくれるボーイフレンドまで手に入れた主人公に共感できる要素なんて皆無のように思える。それなのに、なぜだか主人公の葛藤や不安が自分のことのように感じられた。
「親の呪縛」というのはもう散々使い古された表現だが、前に踏み出せない「わたし」を見ていると、どうしても「親の呪縛」という言葉が頭に浮かぶ。
「わたし」の父親は一念発起して中国からアメリカに渡り、学業と仕事にひたすら励んで身を立てた。母親は薬剤師というキャリアを捨てて父親についていくが、言葉の壁のため、アメリカで自らのキャリアを再び築くことはかなわず、父親と娘を支えることに専念した。
というと美談のようだが、自分のことで頭がいっぱいの父親と、慣れない国で鬱屈を抱えた母親とのあいだには激しい言い争いが絶えなかったというのも事実だった。
そんな家庭で育った「わたし」が、アメリカのホームドラマに出てくるような仲良し家庭で育ち(というのは、もちろん「わたし」からの視点に過ぎないのだが)、家族や周囲の人たちに素直に愛情を示すことができるエリックに対して劣等感を抱き、どうしても距離を感じてしまうくだりには胸をうたれた。
善意に満ちた屈託のない(ように見える)人とのあいだに感じる、絶対に埋められない溝。「わかりみが深い」という最近の言い回しは、こういうときに使うのかと気づいた。(合ってる?)
就職して田舎に行くエリックについていくか悩む「わたし」の胸には、父親についてアメリカに渡った結果、自らのキャリアや中国での家族や友人たちといったすべてを犠牲にした母親の存在がある。言葉もわからず、友人もいない国で苦労をし続け、不平不満をしょっちゅう口にしていた母親の声が、たとえ離れていても「わたし」の耳に常に響いている。
この場面では、以前に読んだケイト・ザンブレノ『ヒロインズ』(西山敦子訳)で、夫の転勤にともなってオハイオにやってきた主人公(書き手)の姿も思い出した。田舎に閉じこめられた「私」は「彼の妻」としか見られなくなり、ゼルダやヴィヴィアン(エリオットの妻)にのめりこむようになる。
だんだんわかってきた、相手のために住む土地を変えることに同意した時点で、もう妻になってしまう。いかに当人どうしが平等なパートナーシップを目指して努力しても。
いつまでたっても英語が上手にならない母親と、そんな母親を下に見るネイティヴの英語話者について主人公が抱く複雑な心情は、ケン・リュウ『紙の動物園』(古沢嘉通訳)や、ジュンパ・ラヒリ『べつの言葉で』(中嶋浩郎訳)でも詳細に描かれていた。「紙の動物園」ではこんなやりとりがある。
母さんは手を伸ばして、熱を測ろうと、ぼくの額に触れようとした。「ファンシャオ・ラ(熱があるの)?」
ぼくは母さんの手を払いのけた。「熱なんかない。英語を話せってば!」ぼくは怒鳴っていた。
また、「紙の動物園」では“ラヴ”と“愛”(中国語)のちがいについて「母さん」が語る場面があるが、『ケミストリー』でも「わたし」はさまざまな言葉について、アメリカと中国での概念や表現のちがいを考察し、エリックのような白人の家庭/社会と自分たちの属する中国系の家庭/社会に照らし合わせている。
ここまで中国系移民としての「わたし」の葛藤に焦点をあててきたが、『ケミストリー』にはだれでも青春時代に直面する普遍的な悩みも描かれている。
「わたし」は懸命に努力して博士課程に進学したが、研究とは努力だけで業績をあげられる世界ではないということがわかってきた。いわゆる天才的なひらめき、というようなものが必要となる。
自分にそんな能力があるのだろうか? 能力がないのなら、いったいどうしたらいいのか? 両親も自分もドクターになるものだと思って生きてきたのに、何者にもなれなかったら、自分という存在の意義はあるのだろうか?
学問と恋愛に悩み、そのふたつと密接に結びついたアイデンティティが揺らぐ「わたし」の姿から、かなり以前に読んだ、ジェフリー・ユージェニデス『マリッジ・プロット』(佐々田雅子訳)も思い出した。
この小説は、アメリカの大学を舞台に、英文学を専攻する主人公マデリンが、レナードとミッチェルという対照的なふたりの男性との三角関係に陥るというストーリーで、鬱で苦しんだり、宗教に救いを求めたりする登場人物たちの「自分探し」と、ジェイン・オースティンの結婚小説を組み合わせた意図がおもしろかったけれど、同作者の『ヘビトンボの季節に自殺した五人姉妹』ほどは話題にならず、少し残念だった。
また、移民としての悩みを抱え、学問にも挫折しかける「わたし」というと、重苦しい小説のように思えるかもしれないが、まったくそうではなく、そんな自分を俯瞰して見つめる主人公のユーモラスで淡々とした語り口も、この小説の大きな魅力となっている。
原書は読んでいないけれど、翻訳文というとどうしても原文より固くなりがちだったりするのに、どんな状況でもけっして深刻ぶらない、飄々とした文体が貫かれていることにも感じ入った。
ビートルズ好きのエリックが、「わたし」に“ディア・プルーデンス”を聞かせるくだりがとくに心に残った。
エリートコースの人生で得たものをいったん捨て、傍から見ると八方ふさがりのような境遇に自ら飛びこむ「わたし」を見ていると、一緒に“ディア・プルーデンス”に耳を傾けたくなった。
Dear Prudence, open up your eyes
Dear Prudence, see the sunny skies
The wind is low, the birds will sing
That you are part of everything……