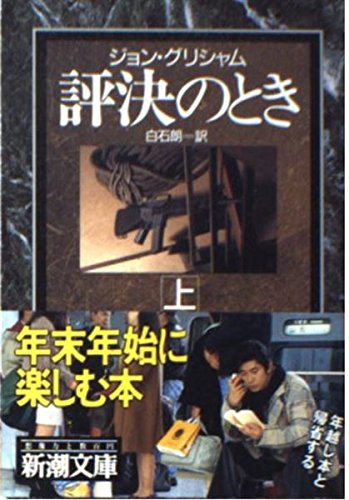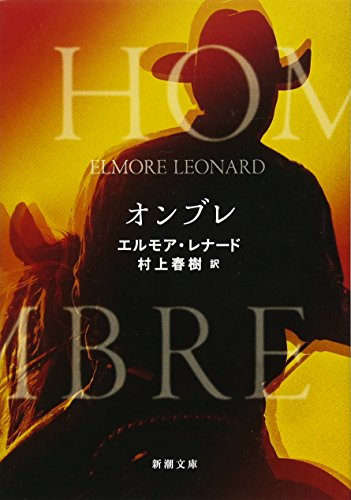なぜ村上春樹はこの作品を訳したのか? ジョン・グリシャム『「グレート・ギャツビー」を追え』(村上春樹訳)
彼が注意深く箱を開けると、図書館が入れた目録ページがあり、そこには「F・スコット・フィッツジェラルド著『美しく呪われしもの』オリジナル原稿直筆」と書かれていた。
「やったぜ」とデニーが静かに言った。彼は同じ形をしたボックスを二つ、五つ目の抽斗から取り出し、細長いテーブルの上にそっと置いた。中には『夜はやさし』と『ラスト・タイクーン』のオリジナル原稿が収められていた。
ジョン・グリシャム『「グレート・ギャツビー」を追え』(村上春樹訳)を課題書として、大阪翻訳ミステリー読書会を開催しました。
なぜアメリカのベストセラー作家であるグリシャム作品を村上春樹が翻訳したのか? グリシャムといえばリーガル・サスペンスの名手なのに、弁護士が出てこないってどういうこと? と話題を呼んだ小説です。
プリンストン大学の図書館に厳重に保存されていた、時価2500万ドルものフィッツジェラルドの直筆原稿を窃盗団が奪い、FBIが原稿の行方を追いかけると、意外な人物が浮上する……というストーリー。
物語の冒頭から窃盗団がプリンストン大学に忍びこみ、見事なチームプレーで強奪に成功する。ページ数でいうと、たったの30ページ。
こんなに簡単に盗めるものなのだと感心していると、たったひとつ、ほんの些細な証拠からあっという間に窃盗団のひとりの身元が判明する。やはり世の中はそんなに甘くなかった。FBIは窃盗団を追いつめて主要メンバーを捕まえるが、性急に事を進め過ぎてしまったのか、残りのメンバーが原稿を持って姿をくらましてしまう――
そんなこんなで第三章になってようやく、この物語の主人公であるマーサー・マンが登場する。マーサー・マンは将来を嘱望された新進気鋭の女性作家であり――いや、「であった」と言った方が正確かもしれない。
現在31歳のマーサーは、24歳のときに長編小説と短編小説集を一冊ずつ出版した。どちらも高い評価を受けたものの、とうに絶版になり、執筆と両立するはずだった教職は契約が打ち切られ、肝心の執筆もまったく進んでいなかった。
つまり、金もなく、仕事もなく、さらに住む場所も失ってしまった。しかも、学資ローンの借金はまだ残っている。小説で得たわずかな印税を学資ローンの利息の支払いにあてたが、元金を返せる額ではなかった。
そんな彼女の前に、イレインという謎の女があらわれる。
奪われたフィッツジェラルドの原稿を取り戻すために、フロリダのカミーノ・アイランドにある書店を偵察してほしいとマーサーに依頼する。その書店は稀覯本も扱っており、ときに盗まれた書籍の取引にも手を染めているらしい。
作家であるマーサーなら、疑われることなく書店の店主と仲良くなり、内部に忍びこめるはずだというのだ。しかも、その店主は若い女性作家にはとりわけ親切なので、いろんな面で交流できるのではないかとほのめかす。
もちろん、マーサーはそんな怪しい依頼を即座に断ろうとするが、マーサーが置かれている苦境も調べ抜いていたイレインは、高額の報酬をちらつかせる。学資ローンという長年の悪夢から解放される。そう考えただけで圧倒されたマーサーは、ついに依頼を引き受けてしまう。
イレインがマーサーに目をつけた理由は、金に困っているからだけではなかった。カミーノ・アイランドには祖母テッサが住んでいて、幼い頃、マーサーはそこでテッサとともに夏を過ごしていた。けれど、テッサが海で事故死してからは遠ざかっていた。依頼を引き受けたものの、テッサとの思い出が色濃く残る島に戻って、そんなスパイまがいの任務を果たせるのか、どうしようもなく不安に陥るマーサーだった……
奪われた原稿を追いかけるという筋立てから、FBIと窃盗団のだまし合いといったハラハラするサスペンスかと思うかもしれないが(読書会では、ジェフリー・アーチャー『百万ドルをとり返せ!』みたいな話かと思っていたら、全然ちがったという声もあった)、サスペンス要素は控えめで、それよりも書店ベイ・ブックスの店主ブルース・ケーブルを中心としたカミーノ・アイランドの人間模様が、この小説の読みどころである。
先のあらすじ紹介ではあえて省いたが、ブルースがベイ・ブックスを立ちあげて、最近流行りの「独立系書店」として成功をおさめるくだりは、本や書店に興味がある人や、自分でも店やビジネスをやってみたい人にとっては、非常に興味深い。
また、ブルースの人となりも捻りがきいている。フロリダの陽光に焼けた肌にクールなスーツをまとい、絶対に靴下をはかない男(昔の石田純一をどうしても思い出すが)というと、気取ったいけすかないやつに思えるが、一方で、だれよりも勤勉で心から書物を愛する人間でもある。
ブルースをとりまくカミーノ・アイランドの作家たち――純文学を書いていたがまったく売れず、やけくそでロマンス小説を書いたら大当たりしたマイラとリー、ヴァンパイア小説で売れっ子になったエミリー、商業的には成功していないが(していない故に?)一目置かれている詩人のジェイ、警部物で人気作家となったがアルコールの問題を抱えているアンディー、連邦刑務所に入った自らの経験を基に産業スパイ小説を書くボブ……
と小説好きの読者であれば、それぞれモデルがいるのかな? なんて考えながら、この面々のやりとりを読んでいるだけでも楽しめる。
さらにこの物語は、フィッツジェラルド作品のみならず、40作近くもの小説について言及している。
稀覯本として高値がついている作品(ジェームズ・リー・バーク『受刑囚』やコーマック・マッカーシー『ブラッド・メリディアン』など)や、「亡くなった白人男性作家」の作品を避けているマーサーが最近読んだ三冊(さて、なんでしょう?)も、本についてのトリビアを得られるうえに、登場人物の心情やキャラクターを知る手掛かりとなる。
なかでも、私が一番心をうたれたのは、エミリー・ディッキンソン『名詩撰』の使われ方だった。本筋とは関係ない場面だが、そういった細部の描き方が物語の豊かさを左右するのだとあらためて感じた。
冒頭の疑問に戻ると、リーガル・サスペンスの名手であるグリシャムが、どうしてこういう小説を書いたのか? と考えながら、グリシャムのデビュー作『評決のとき』を読んでみた。
『「グレート・ギャツビー」を追え』と同様に、『評決のとき』も犯行現場からはじまる。もたもたせずに一気に読者をつかむ、というのはグリシャムの小説技法のひとつなのかもしれない(ちなみに、『「グレート・ギャツビー」を追え』では、「いかにして小説を書くか、ブルースの十箇条」が披露される)。
しかし、凄惨さはまったく異なる。黒人の幼い少女をふたりの白人の男がレイプして痛めつける冒頭は、汚い表現だが「胸糞悪い」というのがぴったりだ。
犯人に復讐した被害者家族をめぐるこの法廷劇を読み、ものすごく今さらなのかもしれないが、リーガル・サスペンスとは人間ドラマなのだなと腑に落ちた。
正義は必ず悪にうち勝つといった単純な話ではなく、さまざまな思惑や駆け引きが絡みあう。弁護士や検事といった登場人物も曲者ぞろいで、完全な善人や悪人は存在しない(レイプ犯は悪人と言えると思うが)。
そのあたりが、『「グレート・ギャツビー」を追え』での個性の強い作家たちの人間模様や、善人か悪人か一概に言い切れないブルースのキャラクターと重なった。
次に、なぜ村上春樹がこの本を訳したのか? という疑問だが、この物語のストーリーは『グレート・ギャツビー』とは関係がない。よって、フィッツジェラルド作品を読んだことがなくとも、この小説をじゅうぶん楽しめる。
読後感としては、村上春樹訳の作品の中では『グレート・ギャツビー』より、エルモア・レナード『オンブレ』に近いものを感じた。
村上春樹が好きな小説と語っている、レナードの『ラブラバ』も同様であるが、知恵と胆力に恵まれた者が相手を出し抜き、危険な状況に陥っても見事にその場を制するさまが痛快に描かれた小説、と言えばいいだろうか。主人公は「正義の人」とは言いきれないが、自らの中に倫理を抱いている。チャンドラーのフィリップ・マーロウにも共通しているかもしれない。そういった系統にある作品として、この小説を訳したのだろうと考えた。
この小説には続編〝Camino Winds〟も出版されていて、訳者あとがきによると、カミーノ・アイランド在住の作家が殺害され、ブルースが捜査に乗り出すというミステリーらしく、こちらも翻訳刊行が決まっているとのこと。いったいだれが殺されるのか、次の邦題も春樹氏の訳書名がフィーチャーされるのではないかなど、読書会ではあれこれ勝手に妄想して盛りあがりました。
↓の紹介を見ると、〝bestselling author Mercer Mann〟 という意外な事態になっているらしいのも気になる。
さて、次回の読書会は春以降になる予定で、おそらくオンライン開催になると思いますので、全国のどこからでもご参加できます。ご興味のある方は下記のサイトをチェック頂き、お気軽にご連絡ください。