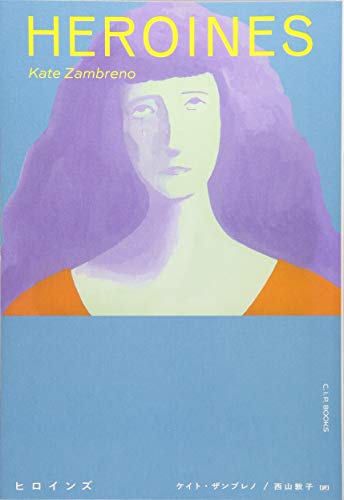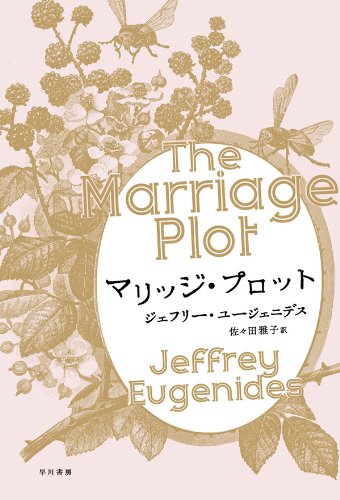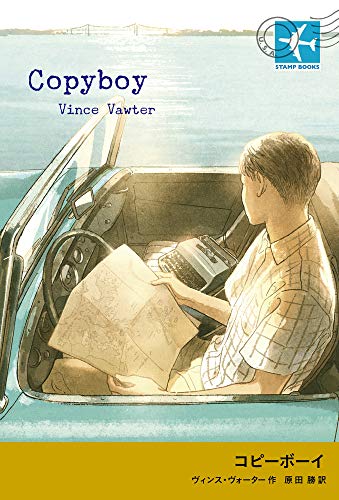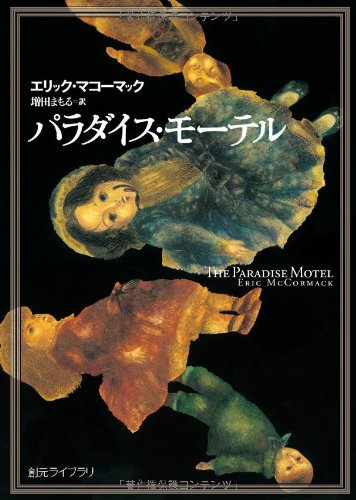【800字書評に挑戦】「健康」な恋愛への「不健康」なためらい――尾崎翠「第七官界彷徨」
さて、先日とある講座を受けたところ、800字の書評を書くという課題を出されました。
800字というと、400字詰め原稿用紙2枚。短いので、なんとかなるかな……と思いきや、短い字数であらすじをまとめ、さらに考察も入れるとはなんとも難しいとつくづく感じた。
しかも課題書は、尾崎翠「第七官界彷徨」。
大学のときにはじめて読んでから、ずっと大好きな物語ではあるのだけれど、読んだことのある方はおわかりでしょうが、その魅力を語るのはきわめて困難だ。
「第七官界彷徨」の第七官界とは、人間の感覚である五官、さらに霊感とも言われる第六感の次の感覚を指していて、主人公である小野町子が「人間の第七官にひびくような詩を書いてやりましょう」という思いを心に抱くところから取られている。この小説自体が第七官界にひびくものであり、感覚の極北で綴られた物語とも言える。
私が持っている筑摩書房版の解説で、矢川澄子は尾崎翠のドッペルゲンガーへのこだわりをひいて(「第七官界彷徨」では『ドッペル何とか』と書かれている)、「尾崎翠はもしかして二人いたのではなかろうか」と書き、こんなふうに続けている。
ひとは彼女の語りの「異常なまでの明るさ」に目をみはり、その文章の「悲痛な軽やかさ」に心打たれる。
「異常なまでの明るさ」と「悲痛な軽やかさ」とはまさに言いえて妙で、尾崎翠の魅力について語ろうとしても、白夜のような明るさに私たちは目がくらみ、蘚(コケ)の花粉のような軽やかさは私たちの手をすり抜けてしまう。
悲痛というのは、文学の志を抱いて鳥取から上京し、昭和初期のモダニズムの時代に斬新な文章で注目を集め、同じく新人作家であった林芙美子に敬慕されるほどの才気を発揮したにもかかわらず、さまざまな事情が重なって地元へ戻り、そのまま文壇から忘れ去られてしまったという尾崎翠の生涯を重ね合わせているのかもしれないが、たしかに、彼女の愛したチャップリンのような物悲しさが物語の片隅に漂っている。
こんなふうに考えていくと、やはり800字で書くなんて無理だと思ったりもしたけれど、とりあえず提出したので、「第七官界彷徨」の冒頭に続けて載せておきます。(なお、800字と言ってますが、課題は800字から1000字のあいだという指定でした)
よほど遠い過去のこと、秋から冬にかけての短い期間を、私は、変な家庭の一員としてすごした。そしてそのあいだに私はひとつの恋をしたようである。
************************************
題:「健康」な恋愛への「不健康」なためらい
『第七官界彷徨』では、蘚の恋愛と人間の恋愛が並行して語られる。
「我ハ曾ツテ一人ノ殊に可憐ナル少女に眷恋シタルコトアリ」と論文の冒頭に綴る小野二助は、失恋したことをきっかけに植物の恋愛の研究に没頭するようになる。蘚の恋愛はこやしによって触発されるため、物語の主人公である町子が兄の一助と二助、そして従兄の三五郎とともに暮らす家には常にこやしの匂いが漂い、恋情をそそられて花をひらけた蘚の花粉が舞い散っている。「植物の恋愛がかえって人間を啓発してくれる」と三五郎が町子に言うとおり、蘚の花粉を吸いこんだ住人たちもそれぞれ恋に落ちる。
ところが、蘚とくらべると人間の恋愛はどうにもあやふやだ。二助が恋した少女には、二助のほかに「深ク想エル人間」がいた。病院に勤務する精神科医の一助は入院患者に恋をするが、もうひとりの医者との三角関係に悩まされる。音楽を勉強する受験生である三五郎は、町子を慈しんでいたにもかかわらず、隣の家の少女も気にかかる。そんな三五郎を見て泪を流していた町子も、束の間の恋に落ちる。どういうわけだか人間は、蘚のように「健康な、一途な恋愛」をすることができず、一助の言うところの「分裂心理」に陥ってしまう。恋心はあてもなく空回り、「誰を恋愛しているのか」すらも解らなくなる。
どうして蘚のように「健康な、一途な恋愛」ができないのだろう? 蘚はあんこのように煮たてた熱いこやしを養分として、大量の花粉を放出し、再生産へ邁進する。一方、一助や三五郎は浜納豆やすっぱい蜜柑をつまんで、三角関係に悩む。町子は短い恋の相手の家で塩せんべいとどら焼きを食べて、睡気を覚える。二助は蘚が開花せずにためらっているのに気づき、「分裂病ニ陥レルニ非ズヤ」と心配する。結局それはこやしが中温度であったからだと判明するのだが、焦った二助は栗とチョコレートを取り違える。
生命力にあふれた「健康」な蘚と比べると、栄養分に乏しい食物ばかり口にして、「分裂心理」に陥る人間の「不健康」さが際立つ。蘚の花粉によって恋心を刺激されても、住人たちは足踏みをするばかりで、恋の成就に向けて踏み出すことができない。再生産にはほど遠い。その「不健康」なためらいこそが、現在においてもこの作品がまったく古びず、共感を得る理由なのだと思う。
なぜ村上春樹はこの作品を訳したのか? ジョン・グリシャム『「グレート・ギャツビー」を追え』(村上春樹訳)
彼が注意深く箱を開けると、図書館が入れた目録ページがあり、そこには「F・スコット・フィッツジェラルド著『美しく呪われしもの』オリジナル原稿直筆」と書かれていた。
「やったぜ」とデニーが静かに言った。彼は同じ形をしたボックスを二つ、五つ目の抽斗から取り出し、細長いテーブルの上にそっと置いた。中には『夜はやさし』と『ラスト・タイクーン』のオリジナル原稿が収められていた。
ジョン・グリシャム『「グレート・ギャツビー」を追え』(村上春樹訳)を課題書として、大阪翻訳ミステリー読書会を開催しました。
なぜアメリカのベストセラー作家であるグリシャム作品を村上春樹が翻訳したのか? グリシャムといえばリーガル・サスペンスの名手なのに、弁護士が出てこないってどういうこと? と話題を呼んだ小説です。
プリンストン大学の図書館に厳重に保存されていた、時価2500万ドルものフィッツジェラルドの直筆原稿を窃盗団が奪い、FBIが原稿の行方を追いかけると、意外な人物が浮上する……というストーリー。
物語の冒頭から窃盗団がプリンストン大学に忍びこみ、見事なチームプレーで強奪に成功する。ページ数でいうと、たったの30ページ。
こんなに簡単に盗めるものなのだと感心していると、たったひとつ、ほんの些細な証拠からあっという間に窃盗団のひとりの身元が判明する。やはり世の中はそんなに甘くなかった。FBIは窃盗団を追いつめて主要メンバーを捕まえるが、性急に事を進め過ぎてしまったのか、残りのメンバーが原稿を持って姿をくらましてしまう――
そんなこんなで第三章になってようやく、この物語の主人公であるマーサー・マンが登場する。マーサー・マンは将来を嘱望された新進気鋭の女性作家であり――いや、「であった」と言った方が正確かもしれない。
現在31歳のマーサーは、24歳のときに長編小説と短編小説集を一冊ずつ出版した。どちらも高い評価を受けたものの、とうに絶版になり、執筆と両立するはずだった教職は契約が打ち切られ、肝心の執筆もまったく進んでいなかった。
つまり、金もなく、仕事もなく、さらに住む場所も失ってしまった。しかも、学資ローンの借金はまだ残っている。小説で得たわずかな印税を学資ローンの利息の支払いにあてたが、元金を返せる額ではなかった。
そんな彼女の前に、イレインという謎の女があらわれる。
奪われたフィッツジェラルドの原稿を取り戻すために、フロリダのカミーノ・アイランドにある書店を偵察してほしいとマーサーに依頼する。その書店は稀覯本も扱っており、ときに盗まれた書籍の取引にも手を染めているらしい。
作家であるマーサーなら、疑われることなく書店の店主と仲良くなり、内部に忍びこめるはずだというのだ。しかも、その店主は若い女性作家にはとりわけ親切なので、いろんな面で交流できるのではないかとほのめかす。
もちろん、マーサーはそんな怪しい依頼を即座に断ろうとするが、マーサーが置かれている苦境も調べ抜いていたイレインは、高額の報酬をちらつかせる。学資ローンという長年の悪夢から解放される。そう考えただけで圧倒されたマーサーは、ついに依頼を引き受けてしまう。
イレインがマーサーに目をつけた理由は、金に困っているからだけではなかった。カミーノ・アイランドには祖母テッサが住んでいて、幼い頃、マーサーはそこでテッサとともに夏を過ごしていた。けれど、テッサが海で事故死してからは遠ざかっていた。依頼を引き受けたものの、テッサとの思い出が色濃く残る島に戻って、そんなスパイまがいの任務を果たせるのか、どうしようもなく不安に陥るマーサーだった……
奪われた原稿を追いかけるという筋立てから、FBIと窃盗団のだまし合いといったハラハラするサスペンスかと思うかもしれないが(読書会では、ジェフリー・アーチャー『百万ドルをとり返せ!』みたいな話かと思っていたら、全然ちがったという声もあった)、サスペンス要素は控えめで、それよりも書店ベイ・ブックスの店主ブルース・ケーブルを中心としたカミーノ・アイランドの人間模様が、この小説の読みどころである。
先のあらすじ紹介ではあえて省いたが、ブルースがベイ・ブックスを立ちあげて、最近流行りの「独立系書店」として成功をおさめるくだりは、本や書店に興味がある人や、自分でも店やビジネスをやってみたい人にとっては、非常に興味深い。
また、ブルースの人となりも捻りがきいている。フロリダの陽光に焼けた肌にクールなスーツをまとい、絶対に靴下をはかない男(昔の石田純一をどうしても思い出すが)というと、気取ったいけすかないやつに思えるが、一方で、だれよりも勤勉で心から書物を愛する人間でもある。
ブルースをとりまくカミーノ・アイランドの作家たち――純文学を書いていたがまったく売れず、やけくそでロマンス小説を書いたら大当たりしたマイラとリー、ヴァンパイア小説で売れっ子になったエミリー、商業的には成功していないが(していない故に?)一目置かれている詩人のジェイ、警部物で人気作家となったがアルコールの問題を抱えているアンディー、連邦刑務所に入った自らの経験を基に産業スパイ小説を書くボブ……
と小説好きの読者であれば、それぞれモデルがいるのかな? なんて考えながら、この面々のやりとりを読んでいるだけでも楽しめる。
さらにこの物語は、フィッツジェラルド作品のみならず、40作近くもの小説について言及している。
稀覯本として高値がついている作品(ジェームズ・リー・バーク『受刑囚』やコーマック・マッカーシー『ブラッド・メリディアン』など)や、「亡くなった白人男性作家」の作品を避けているマーサーが最近読んだ三冊(さて、なんでしょう?)も、本についてのトリビアを得られるうえに、登場人物の心情やキャラクターを知る手掛かりとなる。
なかでも、私が一番心をうたれたのは、エミリー・ディッキンソン『名詩撰』の使われ方だった。本筋とは関係ない場面だが、そういった細部の描き方が物語の豊かさを左右するのだとあらためて感じた。
冒頭の疑問に戻ると、リーガル・サスペンスの名手であるグリシャムが、どうしてこういう小説を書いたのか? と考えながら、グリシャムのデビュー作『評決のとき』を読んでみた。
『「グレート・ギャツビー」を追え』と同様に、『評決のとき』も犯行現場からはじまる。もたもたせずに一気に読者をつかむ、というのはグリシャムの小説技法のひとつなのかもしれない(ちなみに、『「グレート・ギャツビー」を追え』では、「いかにして小説を書くか、ブルースの十箇条」が披露される)。
しかし、凄惨さはまったく異なる。黒人の幼い少女をふたりの白人の男がレイプして痛めつける冒頭は、汚い表現だが「胸糞悪い」というのがぴったりだ。
犯人に復讐した被害者家族をめぐるこの法廷劇を読み、ものすごく今さらなのかもしれないが、リーガル・サスペンスとは人間ドラマなのだなと腑に落ちた。
正義は必ず悪にうち勝つといった単純な話ではなく、さまざまな思惑や駆け引きが絡みあう。弁護士や検事といった登場人物も曲者ぞろいで、完全な善人や悪人は存在しない(レイプ犯は悪人と言えると思うが)。
そのあたりが、『「グレート・ギャツビー」を追え』での個性の強い作家たちの人間模様や、善人か悪人か一概に言い切れないブルースのキャラクターと重なった。
次に、なぜ村上春樹がこの本を訳したのか? という疑問だが、この物語のストーリーは『グレート・ギャツビー』とは関係がない。よって、フィッツジェラルド作品を読んだことがなくとも、この小説をじゅうぶん楽しめる。
読後感としては、村上春樹訳の作品の中では『グレート・ギャツビー』より、エルモア・レナード『オンブレ』に近いものを感じた。
村上春樹が好きな小説と語っている、レナードの『ラブラバ』も同様であるが、知恵と胆力に恵まれた者が相手を出し抜き、危険な状況に陥っても見事にその場を制するさまが痛快に描かれた小説、と言えばいいだろうか。主人公は「正義の人」とは言いきれないが、自らの中に倫理を抱いている。チャンドラーのフィリップ・マーロウにも共通しているかもしれない。そういった系統にある作品として、この小説を訳したのだろうと考えた。
この小説には続編〝Camino Winds〟も出版されていて、訳者あとがきによると、カミーノ・アイランド在住の作家が殺害され、ブルースが捜査に乗り出すというミステリーらしく、こちらも翻訳刊行が決まっているとのこと。いったいだれが殺されるのか、次の邦題も春樹氏の訳書名がフィーチャーされるのではないかなど、読書会ではあれこれ勝手に妄想して盛りあがりました。
↓の紹介を見ると、〝bestselling author Mercer Mann〟 という意外な事態になっているらしいのも気になる。
さて、次回の読書会は春以降になる予定で、おそらくオンライン開催になると思いますので、全国のどこからでもご参加できます。ご興味のある方は下記のサイトをチェック頂き、お気軽にご連絡ください。
立派な実験動物として生きるために 『韓国フェミニズム作品集 ヒョンナムオッパへ』(チョ・ナムジュほか著 斎藤真理子訳)
『韓国フェミニズム作品集 ヒョンナムオッパへ』を読みました。
タイトルからもわかるように、「フェミニズム」をテーマに韓国の女性作家七人が書き下ろした短編集……というコピーから思い浮かぶ枠をはるかに超えて、リアリズム小説からノワールやSFまで多彩な物語が収められている。
表題作の「ヒョンナムオッパへ」は、ベストセラーとなった『82年生まれ、キム・ジヨン』のチョ・ナムジュによる作品である。
「オッパ」とは韓国語で「兄」という意味を持ち、恋人など親しい年上の男性への呼びかけに使用される言葉とのことで、「ダーリン」みたいなニュアンスなのかもしれない。
「キム・ジヨン」と同様に、ここで描かれるヒョンナムオッパの姿に女性読者はあるある!と眩暈がするくらいの既視感を覚えるにちがいない。
自分がヒョンナムオッパみたいな男と絶対につきあうことはなく、関わることすら避けて生きてきたとしても、かならずと言っていいほど、この手の男は友達の彼氏や夫の中にひとりは存在する。
女同士で遊びや旅行に行く計画を立てているときに、「彼氏を置いて遊びに行くと機嫌が悪くなる」とか、「夜出かけるときには、ごはんを用意しておかないといけない」とか耳にして、(お留守番もできへんの? 夫は小学生なん? いや、小学生でもコンビニでおにぎりくらい買えるで)と苛立った経験がある女性は少なくないのではないだろうか。そういうタイプの女性は、物語内のジウンのように、オッパに毛嫌いされるのだろうが。
しかもこのオッパは日常生活のみならず、将来の進路まで平気で指図するので驚かされるが、オッパがうざければうざいほど、目覚めた主人公が手に入れた解放感が際立ち、最後の「ケジャシガ」(本文では日本語ですが)という罵倒語が痛快に響く。
しかしその一方で、こんなことも思う。
どうして主人公はこのヒョンナムオッパのような男に魅かれてしまったのか? どうして私たちはときにつまらない男を好きになってしまうのか? 好きになった相手をすぐに断ち切ることができるのか? 自分より強く見える男に守ってもらいたいという気持ちを完全に捨て去ることができるのか?
この狭間でぐるぐるする「フェミニズム小説」は成立するのだろうか?
次の「あなたの平和」(チェ・ウニュン)と、「更年」(キム・イソル)も同様に、日常生活に潜む抑圧を描いている。
「あなたの平和」は、息子の結婚相手ソニョンを迎える母親ジョンスンの姿を、娘ユジンの視点から描いた作品である。
苦労して育ち、母を喜ばせるために安定した家に嫁いだジョンスンの長年の葛藤が、息子の結婚によって顕在化される。結婚相手のソニョンは早くに両親を失い、家だけが遺されたため、息子がソニョンの家に入ることになる。
つまり、息子夫婦はジョンスンとまったく正反対の生き方を選んだのだ。嫁ぎ先で義理の母と夫にひたすら尽くして生きてきたジョンスンは、どうしてもそのことが受け入れられない。そんなジョンスンに娘ユジンはこんな言葉を投げかける。
「おばあちゃんがお母さんにやったことを、ソニョンさんにやろうとしないでよ……誰にもそんなふうに、ほかの人を苦しめる資格はないんだから」
「両親もいない子を受け入れてやったのに」……
「そんなふうだと、お母さんのそばには誰もいなくなるよ。そんな醜い考え方する人、顔も見たくないし、話もしたくない、帰るわよ」
ユジンが幼いころ、ジョンスンが倒れて救急車で運ばれても、ユジンの祖母や父親は気にも留めなかった。家にとって、嫁のジョンスンは取るに足らない存在だったのだ。やせ細った身体でキムチを漬けるジョンスンを、ユジンは子どもながらに少しでも助けようとした。
そんなユジンが上記の台詞をジョンスンに言わなければならなかったとき、どれほどつらかったかを想像すると、こちらまで胸が引き裂かれそうになる。
「更年」も息子を持つ母親が主人公であり、同様に息子の行いによって、自分の人生はいったいなんだったのか? と、これまでの選択を振り返る物語である。
この小説では、世界を放浪する妹ジナが主人公とまったく反対の生き方を選択する存在として登場し、ジナと連絡をとった娘がアイドルの話題で盛りあがる場面で風穴があき、爽快な空気が流れる。
結婚しなければ寂しいだろうと、なぜあんなにうっかり信じ込んでしまったのか。多数が選ばない別の生き方もあるということをなぜ、認められなかったのか。結局、私もジナも同じだ。それぞれ、自分が考えて選択した人生なのだし、その選択の責任を負って生きているだけだ
というのは、この物語内ではなく作家ノートで書かれている文章だが(推敲時に本文から消したとのこと)、この小説全体を貫く思想だと感じられた。
「すべてを元の位置へ」(チェ・ジョンファ)からの短編は、先の三篇とは異なり、いわゆる「フェミニズム小説」というより、新しい角度から切り取ったジャンル小説としての趣きが強い。
「すべてを元の位置へ」の主人公は、L市に建ち並ぶ廃墟や廃屋に入って内部の映像を撮影する仕事をはじめる。題から連想される、Radioheadの“Everything In Its Right Place”に似つかわしいシチュエーションだ。(といっても、韓国語の原題はわからないけれど)
解説によると、ソウルの大規模都市再開発による立ち退きが背景となっているらしく、追い出された人が残したスカートを拾った「私」はどうしたのか、そして「私」の身に何が起きたのか……と、ある種の寓話として描かれている。
「異邦人」(ソン・ボミ)は、警察の捜査局から追い出されて身を隠していた「彼女」のもとを、後輩の「彼」が足繁く通って捜査復帰を懇願するところからはじまる。人工の雨が降る近未来を舞台とした、ノワール風のハードボイルドだ。
ヴァーチャル自殺が流行る世の中で、「死人は傷ついた心より重い」とフィリップ・マーロウの台詞を口にしていた「彼女」だが、物語が進むにつれて、はたして死人と傷ついた心のどちらが重いのか? と問いかける。男と女という軸、現実とヴァーチャルという軸を入れ替えた試みが興味深い作品だった。
「ハルピュイアと祭りの夜」(ク・ビョンモ)では、とある島で開かれた女装コンテストに、友人ハンの代わりに出場したピョがとんでもないことに巻きこまれる。
女装コンテストで賞金五千万ウォン? そんなことあるのか? ピョが訝りつつも、ハンが提示した謝礼三百万ウォンにつられて引き受けるくだりはユーモラスだが、島に着いてからは血も凍るような陰惨な事態がくり広げられていく。
女性が男性を罰するという勧善懲悪を描いた作品とも言えるが、三百万ウォンで身代わりとなったピョの不条理な運命を考えると、現実の事件においても痛い目に遭うのは末端の小悪党で、巨悪は他人を身代わりに送りこみ、永遠に罰せられることがないという皮肉もこめられているのかもしれない。
最後の「火星の子」(キム・ソンジュン)は、宇宙船で打ちあげられた「私」が語り手となる。
宇宙船の中で眠りから覚めた「私」は、右腕と左腕、さらに二本の足を動かしているところから人間らしい形状をしていると思われるが、人間ではない。無数の実験動物のデータを集めて作ったクローンだ。
そんな「私」を待ち受けていたのは、一匹のシベリアンハスキーだった。私の名前はライカだよ、と英語で自己紹介をする。
そう、あのスプートニク二号に乗せられたライカ犬だった。宇宙の藻屑となったあと、星から星へと永遠にさまよい歩く存在となったのだ。ペットのノミに宇宙飛行士の名前をつけ、デヴィッド・ボウイの「スペイス・オデッセイ」を口ずさみ、ときにはダンテの煉獄を引用したりと恐ろしく博識で、無知な人間に容赦のないライカ。
軽々しくふれられることを嫌いながらも、「私」に抱きしめられるとすぐに「私」が妊娠していることに気づく。記憶を消された「私」は、実験によって妊娠させられたこともすっかり忘れていたのに。
ライカは妊娠した私を、自分の娘にでもなったみたいに世話してくれる。火星の空のような、本音のわからない犬だったけど、あれ以来ライカが私に注いでくれたまごころを思うと、誰かが私のために送り込んでくれた存在ではないかとも思えた。
ライカと探査ロボットたちに見守られ、「私」は夢を見る。
夢の中では、枯れはてた赤い惑星であるはずの火星に白い波が打ち寄せ、生まれたばかりの子どもが魚のように泳ぐ。目を覚まして夢だと気づく。そこにある火星はやはり水のない乾いた惑星だけど、ライカとロボットは臨月の「私」を見守っている……
解説にもあるとおり、「ほのかな希望」が漂う作品であり、また一方で、実験動物となって宇宙の果てまで行かないと、安らぎの空間は得られないのだろうか? なんて考えさせられたが、この短編集で一番心に残った。
ライカは「実験動物になるための二つの必須条件」として、「賢くて健康なこと、主人がいないこと」を挙げている。
このふたつの条件は、自立して生きていくための必須条件ではないだろうか?
新しい生き方を模索することは、つまり「実験動物」として生きることなのかもしれない。なんとかこの条件をクリアして、立派な実験動物として生きていきたいものだと年頭から心に誓った。
2020年心に残った本(『ボッティチェリ 疫病の時代の寓話』『ワイルドサイドをほっつき歩け』『ディスタンクシオン』)
先日、翻訳ミステリー読書会のスピンオフとして雑談会を開き、「今年心に残った本」について語り合いました。いつものように思いつきでテーマを発表してから、なんやろ~と考えてみたのですが、案外迷うことなくすんなりと下の3冊に決まりました。
1:バリー・ユアグロー『ボッティチェリ 疫病の時代の寓話』(柴田元幸訳)
今年を象徴するものというと、認めたくないけれどやはりあれしかない。名前は口にしたくないけれど、そいつのせいで私たちは日常生活を営むことすら困難になり、愛する人たちの姿を見ることもかなわなくなった。
禍々しい突発事態によって、予期せざる期間わがささやかな住まいに閉じ込められたいま、閉じこもりの停滞と不安を打破しようと、この四つの壁の内部の旅行記兼回想録を書こうと私は思い立つ。
禍々しい突発事態が起きてしまった。世界でもっとも大きな被害を受けた都市のひとつ、ニューヨークに住むバリー・ユアグローは、「書く」――引用した掌編のタイトルでもあるが――ことによって正気を保とうとした。
この小さな冊子に収められた掌編はどれも現実と非現実の狭間を漂っている。
現実が非現実に近づきつつあるさなか、非現実を描くことによって現実を取り戻そうとした試みと言えるのかもしれない。また一方、作者は以前から奇想あふれる非現実を描いてきたが、現実が非現実に近づいたことによって、作者の描く非現実が現実そのものの感触を得るに至ったようにも思える。
つまりは、現実と非現実が渾然一体となったこの掌編集は、とてつもない想像力に満ちあふれていて、とてつもなくリアルに感じられた。
この掌編集は今年の4月から5月に書かれたもので、日付順で収められている。
4月初めに書かれた冒頭の「ボッティチェリ」では病によって美しくなるという倒錯が綴られたり、「鯨」では鯨が救急車の代わりをしたりと、切羽詰まった状況ながらも微かな情緒や遊び心がほの見える。
しかし5月に書かれた「夢」では、自分の夢にアクセスできなくなった主人公が、「毎日毎日、生活のなかのもっとも陳腐な行為を営むだけでも、心を蝕む不安がまた新たにもたらされているんです」と怒りをたぎらせ、最後の「書く」も、闖入者によって「書く」ことができなくなった物語であり、日が進むにつれて不穏さが増していくのがわかる。私たちも3月くらいの頃は、1か月も自粛したらきっと落ち着くにちがいないと思っていた……なんて振り返ってしまう。
4月26日付の「影」では、影をなくした女の子にマスクを付けた「私」が声をかける。この一年、世界中のだれもが心の底から求めた言葉――「私」もまったく確信は抱いていないのだけれど。
「大丈夫だよ、きっと」と私は何度も、マスク越しに彼女に向かって呟く。「心配しなくていいよ、大丈夫だよ、きっと」
2:『ワイルドサイドをほっつき歩け』(ブレイディみかこ)
また、今年はBLMやアメリカ大統領選が注目を集め、赤と青で塗り分けられたアメリカの地図が象徴していたように、「社会の分断」が一層あらわになった印象がある。(コロナが加速させた側面もあるが……って名前を書いてしまった)
「社会の分断」が表面化してきた兆候のひとつに、イギリスがEU脱退を決めた2016年の国民投票を挙げることができるのではないだろうか。
『ワイルドサイドをほっつき歩け』は、ブレグジットをめぐって一組のカップルに亀裂が入るエピソードから始まっている。
英国なんかだと、とくに「けしからん」存在と見なされているのは、労働者階級のおっさんたちである。時代遅れで、排外的で、いまではPCに引っかかりまくりの問題発言を平気でし、EUが大嫌いな右翼っぽい愛国者たちということになっている。
と、「はじめに」に述べられているように、イギリスでもアメリカでも、いわゆる「白人の労働者階級」は黒人などのマイノリティや移民を排斥しようと旗を振り、EU離脱やトランプ再選に票を投じる「意識の低い」人たちだと見做される傾向がある。
しかし、作者が「おっさんたちだって一枚岩ではない」と書くように、労働者階級の人たちにもさまざまなタイプがいて、EU離脱に票を投じたのにもさまざまな理由や事情がある。
一見、作者の身辺雑記のようにも読めるこの本が、ユーモラスで淡々とした筆致でありながら強く印象に残るのは、白人の労働者階級に属する人たちを「意識が低い」と批判するのではなく、逆に労働者階級の本音こそ正義だ!と美化するわけでもない、フラットな視点で書かれているからだと思う。
周囲の労働者階級の人たちのなかには、NHS(国民保健サービス)を守ろうと奮闘し、レイシズムと戦う人たちもいる。
その一方で、ベトナムからやってきた妻に対して、金目当てじゃないのかと冷たい視線を向ける人たちもいる。作者自身もイギリス人男性と結婚したとき、「永住権を取得するために利用されるとか、就労ビザ欲しさの結婚だ」とか、夫の仲間たちが裏で言っていたのを覚えている。
けれども、そういう人たちを断罪するのではなく、「おっさんだって生きている」を合言葉として、さまざまな面を持つ人間そのものを受け入れる姿勢が、激しい主張が飛び交うこの時代において新鮮だった。ベストセラーとなった『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』が綺麗事のように感じられた人には、こちらを読んでもらいたい。
3:ブルデュー『ディスタンクシオン』NHK 100分 de 名著(岸政彦)
人間はさまざまな面を持ち、その行動の裏にもさまざまな事情がある。ということが、この本では「他者の合理性」という言葉で表されている。
すべての人の行為や判断には、たとえ私たちにとって簡単に理解できないもの、あるいはまったく受け入れられないようなものでさえ、そこにはその人なりの理由や動機や根拠がある。
作者は沖縄の生活史を専門とする社会学者であり、自身の考えとしては「沖縄に米軍基地を押しつけることに反対」であり、「沖縄の民衆的抵抗を信じている」と述べている。その一方で、「民衆」に幻想を抱いては駄目だと論じ、米軍基地に「反対しない人を愚かだとは決して言いません」と綴っている。
米軍基地と共存して生きることを選択する(あるいは選択せざるを得ない)人たちにとっては、その選択の合理性が必ず存在するので、それを理解しようとしないかぎりは何ひとつ前進しないというのがその理由だ。
どんな問題であっても、自分の正しさを主張するよりも、相手を理解するように努める方が問題解決に近づく、もしくはたとえ解決しなくとも、先へ進めるのだろうと感じた。
とはいえ、他者に対してけっして幻想を抱かずに、ただ理解しようとするというのは、かなり困難な作業だと思う。愛情や思い入れは、家族間でも友人間でも言えることだけれど、どうしても幻想とセットになってしまうし、けれども愛情や思い入れがなければ、相手のことを理解したいとは思わない。
来年、いや生きているうちに、この境地に達することができるのだろうか……
この『ディスタンクシオン』のメインテーマは階級であり、私たちが自らの選択で選び取っているつもりの趣味や嗜好も、実は深く階級と結びついていると語られている。『ワイルドサイドをほっつき歩け』でも、英国の世代と階級についての解説が巻末に書かれていた。
こういった階級論を読むと、「でも日本はヨーロッパほど階級社会じゃないし……」と思いたくなるが、「東大生の親の約六割が年収950万円以上」(全世帯のうち、所得が1000万以上はわずか12%)というニュースを聞くと、気づいていないだけで、日本もしっかり階級社会になっているのかもしれないと考えさせられる。
この二冊が参考として挙げている『ハマータウンの野郎ども』を読んで、勉強すべきなのかもしれない。
またも自分の感想で長くなってしまいましたが、参加者のみなさんが雑談会で挙げてくれた本も貼っておきます。
みなさんの今年心に残った本を紹介します。鼠さんの選書はこちら。このル・カレは読みやすいとのこと🧐
— Reiko Nobuto (@RNobuto) 2020年12月27日
『黒と白のはざま』 ロバート・ベイリー/吉野弘人(訳)
『スパイはいまも謀略の地に』ジョン・ル・カレ/加賀山卓朗 (訳)
『掃除婦のための手引き書』ルシア・ベルリン/岸本 佐知子 (訳)
牛さんの今年心に残った本はこちら。『追憶の…』は毎日新聞に若島正さんの書評が掲載されました
— Reiko Nobuto (@RNobuto) 2020年12月27日
『弁護士ダニエル・ローリンズ』ヴィクター・メソス /関 麻衣子 (訳)
『喪われた少女』 ラグナル・ヨナソン/吉田薫 (訳)
『追憶の東京 異国の時を旅する』アンナ・シャーマン /吉井 智津 (訳)
寅さんの今年心に残った本はこちら。『幻の女』は永遠の名作ですね。『最後の…』は「基礎英語2」で、ないとうふみこさんが紹介されていたのを読んで興味を持ったとのことでした🐲
— Reiko Nobuto (@RNobuto) 2020年12月27日
『幻の女』ウイリアム・アイリッシュ /黒原 敏行 (訳)
『最後のドラゴン』ガレット・ワイヤー /三辺 律子 (訳)
兎さんの今年心に残った本はこちら。そう、強い女たちがテーマです🙌カマラ・ハリスさんも今年の顔ですね。
— Reiko Nobuto (@RNobuto) 2020年12月27日
『あの本は読まれているか』ラーラ・プレスコット /吉澤 康子 (訳)
『戦場のアリス』ケイト・クイン /加藤 洋子 (訳)
『オルガ』 ベルンハルト・シュリンク /松永美穂 (訳)
竜さんの今年心に残った本はこちら。『ドクラ…』は、文豪メール https://t.co/BHOSDmAPa2 を活用して読んでいるとのこと。
— Reiko Nobuto (@RNobuto) 2020年12月27日
コロナ禍で楽器を始めた人が多いようなので、ノワール×音楽の『ヤクザ…』も、今年オススメしたい本ですね🎹
『ドグラ・マグラ』 夢野 久作
『ヤクザときどきピアノ』鈴木智彦
蛇さんの今年心に残った本はこちら。『翻訳目録』、翻訳のノウハウみたいな本かと思っていたのですが、絵本のようにヴィジュアルたっぷりの素敵な本でした😺
— Reiko Nobuto (@RNobuto) 2020年12月27日
『サキの忘れ物』 津村記久子
『翻訳目録』 阿部 大樹 /タダ ジュン (挿絵)
『内なる町から来た話』ショーン・タン/岸本佐知子 (訳)
馬さんの今年心に残った本はこちら。なんと『ナイル』に出てくるエジプト各地をすべて廻ったとのこと🙄
— Reiko Nobuto (@RNobuto) 2020年12月27日
『追憶の東京 異国の時を旅する』アンナ・シャーマン/吉井 智津 (訳)
『フォックス家の殺人』 エラリイ・クイーン/越前敏弥 (訳)
『ナイルに死す』アガサ・クリスティー/黒原 敏行 (訳)
さて、そんなこんなで2020年もあと半日。いろいろあったけれど、
♪どうか元気で~お気をつけて~と、みなさん無事に新しい年を迎えましょう。来年こそは……!
移民の娘、そしてエリート女子として、「わたし」のこじれたアイデンティティ――ウェイク・ワン『ケミストリー』(小竹由美子訳)
ウェイク・ワン『ケミストリー』(小竹由美子訳)を読みました。
中国系アメリカ人として生まれた「わたし」は、両親の期待を背負って博士課程へ進学した。そこでエリックと出会って一緒に暮らしはじめ、ついにはプロポーズされる。
けれども、エリックについていく決心もできず、かといって勉学に集中することもできない。両親は娘である自分が輝かしい業績をあげることを願っているが、両親のことを考えれば考えるほど、目の前に立ちはだかる現実に足がすくむ…………
こうやって要約すると、博士課程というエリートコースに進み、さらにエリートであるうえに心優しく、自分を愛してくれるボーイフレンドまで手に入れた主人公に共感できる要素なんて皆無のように思える。それなのに、なぜだか主人公の葛藤や不安が自分のことのように感じられた。
「親の呪縛」というのはもう散々使い古された表現だが、前に踏み出せない「わたし」を見ていると、どうしても「親の呪縛」という言葉が頭に浮かぶ。
「わたし」の父親は一念発起して中国からアメリカに渡り、学業と仕事にひたすら励んで身を立てた。母親は薬剤師というキャリアを捨てて父親についていくが、言葉の壁のため、アメリカで自らのキャリアを再び築くことはかなわず、父親と娘を支えることに専念した。
というと美談のようだが、自分のことで頭がいっぱいの父親と、慣れない国で鬱屈を抱えた母親とのあいだには激しい言い争いが絶えなかったというのも事実だった。
そんな家庭で育った「わたし」が、アメリカのホームドラマに出てくるような仲良し家庭で育ち(というのは、もちろん「わたし」からの視点に過ぎないのだが)、家族や周囲の人たちに素直に愛情を示すことができるエリックに対して劣等感を抱き、どうしても距離を感じてしまうくだりには胸をうたれた。
善意に満ちた屈託のない(ように見える)人とのあいだに感じる、絶対に埋められない溝。「わかりみが深い」という最近の言い回しは、こういうときに使うのかと気づいた。(合ってる?)
就職して田舎に行くエリックについていくか悩む「わたし」の胸には、父親についてアメリカに渡った結果、自らのキャリアや中国での家族や友人たちといったすべてを犠牲にした母親の存在がある。言葉もわからず、友人もいない国で苦労をし続け、不平不満をしょっちゅう口にしていた母親の声が、たとえ離れていても「わたし」の耳に常に響いている。
この場面では、以前に読んだケイト・ザンブレノ『ヒロインズ』(西山敦子訳)で、夫の転勤にともなってオハイオにやってきた主人公(書き手)の姿も思い出した。田舎に閉じこめられた「私」は「彼の妻」としか見られなくなり、ゼルダやヴィヴィアン(エリオットの妻)にのめりこむようになる。
だんだんわかってきた、相手のために住む土地を変えることに同意した時点で、もう妻になってしまう。いかに当人どうしが平等なパートナーシップを目指して努力しても。
いつまでたっても英語が上手にならない母親と、そんな母親を下に見るネイティヴの英語話者について主人公が抱く複雑な心情は、ケン・リュウ『紙の動物園』(古沢嘉通訳)や、ジュンパ・ラヒリ『べつの言葉で』(中嶋浩郎訳)でも詳細に描かれていた。「紙の動物園」ではこんなやりとりがある。
母さんは手を伸ばして、熱を測ろうと、ぼくの額に触れようとした。「ファンシャオ・ラ(熱があるの)?」
ぼくは母さんの手を払いのけた。「熱なんかない。英語を話せってば!」ぼくは怒鳴っていた。
また、「紙の動物園」では“ラヴ”と“愛”(中国語)のちがいについて「母さん」が語る場面があるが、『ケミストリー』でも「わたし」はさまざまな言葉について、アメリカと中国での概念や表現のちがいを考察し、エリックのような白人の家庭/社会と自分たちの属する中国系の家庭/社会に照らし合わせている。
ここまで中国系移民としての「わたし」の葛藤に焦点をあててきたが、『ケミストリー』にはだれでも青春時代に直面する普遍的な悩みも描かれている。
「わたし」は懸命に努力して博士課程に進学したが、研究とは努力だけで業績をあげられる世界ではないということがわかってきた。いわゆる天才的なひらめき、というようなものが必要となる。
自分にそんな能力があるのだろうか? 能力がないのなら、いったいどうしたらいいのか? 両親も自分もドクターになるものだと思って生きてきたのに、何者にもなれなかったら、自分という存在の意義はあるのだろうか?
学問と恋愛に悩み、そのふたつと密接に結びついたアイデンティティが揺らぐ「わたし」の姿から、かなり以前に読んだ、ジェフリー・ユージェニデス『マリッジ・プロット』(佐々田雅子訳)も思い出した。
この小説は、アメリカの大学を舞台に、英文学を専攻する主人公マデリンが、レナードとミッチェルという対照的なふたりの男性との三角関係に陥るというストーリーで、鬱で苦しんだり、宗教に救いを求めたりする登場人物たちの「自分探し」と、ジェイン・オースティンの結婚小説を組み合わせた意図がおもしろかったけれど、同作者の『ヘビトンボの季節に自殺した五人姉妹』ほどは話題にならず、少し残念だった。
また、移民としての悩みを抱え、学問にも挫折しかける「わたし」というと、重苦しい小説のように思えるかもしれないが、まったくそうではなく、そんな自分を俯瞰して見つめる主人公のユーモラスで淡々とした語り口も、この小説の大きな魅力となっている。
原書は読んでいないけれど、翻訳文というとどうしても原文より固くなりがちだったりするのに、どんな状況でもけっして深刻ぶらない、飄々とした文体が貫かれていることにも感じ入った。
ビートルズ好きのエリックが、「わたし」に“ディア・プルーデンス”を聞かせるくだりがとくに心に残った。
エリートコースの人生で得たものをいったん捨て、傍から見ると八方ふさがりのような境遇に自ら飛びこむ「わたし」を見ていると、一緒に“ディア・プルーデンス”に耳を傾けたくなった。
Dear Prudence, open up your eyes
Dear Prudence, see the sunny skies
The wind is low, the birds will sing
That you are part of everything……
差別する側の「誤った決断や行動、事後の後悔」を描いた 『兄の名は、ジェシカ』(ジョン・ボイン著 原田勝訳)
ジョン・ボイン『兄の名は、ジェシカ』を読みました。
以前に紹介した二作『縞模様のパジャマの少年』『ヒトラーと暮らした少年』は、どちらもナチスドイツの支配下にあったヨーロッパを描いていたが、今作は現代のイギリスが舞台となっている。
主人公である語り手の「ぼく」は14歳で、4歳年上の兄ジェイソン、政治家の母親、母親の秘書を務める父親と暮らしている。
難読症のため読み書きが苦手なうえに、スポーツも得意ではない「ぼく」と異なり、ジェイソンはプロを目指すようスカウトされるほどサッカーが得意な学校の人気者で、忙しい両親に変わってずっと「ぼく」の面倒をみてくれていた。ジェイソンはヒーローそのものだった。
ところが、最近ジェイソンのようすがおかしい。「ぼく」や両親と距離を置くようになり、部屋にこもる時間が増えた。一度、部屋をのぞくと泣いているときがあった。しかも、どういうわけかブロンドの髪を伸ばしはじめ、変な段カットにしている……
そしてある日、家族全員に話があるとジェイソンが切り出す。
不安を感じた「ぼく」は、「ジェイソンは世界で一番の兄さんなんだから、ね」と口にして、わざと子どもっぽく甘えてみせる。ジェイソンは黙りこんだあと、おまえの兄さんじゃないと否定する。
ぼくはとまどったまま、ジェイソンの顔をじっと見ながら、ききかえした。「どういう意味?」
「言ったとおりさ。おまえの兄さんじゃない。ほんとうは、姉さんなんだと思う」
ジェイソンの性自認は女性であり、つまり、トランスジェンダーだと家族に告白する。
現代はゲイやレズビアン、トランスジェンダーをカミングアウトしている人も多く、昔にくらべると偏見も少なくなっていると思う。
けれども、いざ自分の血縁者に告白されると戸惑ってしまう人が大半ではないだろうか。「ぼく」や両親も例にもれず、一家の星であったジェイソンの告白を受けとめられない。聞かなかったことにしてしまいたい。母親は二度とそんなことを口にするなと言い、父親は電気ショック療法で治るのではないかと考える。
しかし、ジェイソンの見かけはどんどんと女らしくなり、「ぼく」は学校で散々笑い者にされ、“宿敵”のいじめっ子たちからは変態野郎という罵声を浴びせられる。それもこれもぜんぶジェイソンのせいだと恨むようになり、ある行動に出る……
この本を読み終えて、あらためてジョン・ボインが描く登場人物の設定や配置の絶妙さに感心した。
『縞模様のパジャマの少年』の主人公である少年の父親はナチスの高官であり、少年はフェンスで囲まれた建物(収容所)にはどんな人たちが入っているのか、内部で何が行われているのか、まったく知らない。その無知と鈍感さに読んでいる側はもどかしい思いを抱く。
『ヒトラーと暮らした少年』では、主人公の少年の悲しい生い立ちに同情した読者も、そのあと少年がヒトラーにすっかり感化されていくさまに困惑と苛立ち、そして悲しみを覚える。
この『兄の名は、ジェシカ』においても、ジェイソンを受けとめて応援する人が周囲にあらわれても、なかなかジェイソンの選択を認めようとしない「ぼく」や両親の無理解ぶりに胸が痛くなる。
先日、訳者の原田勝さんによるセミナー「訳した本がジャンルを作る──海外児童文学・YA文学に描かれる戦争と差別」で、下記の視点が挙げられていた。
視点(2)文学による疑似体験
*侵略される側・差別される側の「痛み」
*侵略する側・差別する側の「誤った決断や行動、事後の後悔」
*全体の枠組みや環境の中で、冷静に問題を考える機会を提供
*単なる情報ではなく、物語として提示する意義や力(まず文学として質が高いこと)
*基本的に一人で行なう営みである読書を通じて、問題を深く認識する可能性。それをサポートするための、翻訳の工夫(読みやすさ、訳注、解説)
ジョン・ボインの一連の作品は、〈侵略する側・差別する側の「誤った決断や行動、事後の後悔」〉を描くことで、〈侵略される側・差別される側の「痛み」〉が読者に強く伝わり、当事者であるというのはどういうことか、じっくりと考えさせられる構成になっている。
また、最後に添えられた作者あとがきで、ジョン・ボインは「トランスジェンダーであることがどういうことか、わたしは身をもって知っているわけではありません」と断りつつ、自らがゲイだと意識しはじめたときの気持ちを綴り、まわりの人とちがうということがどれだけ恐ろしいか、切実に語っている。
迫害されている人たちのために立ち上がらなければ、結局それは、わたしたちが迫害する側に回ることになります。いじめられている人たちによりそわなければ、わたしたちはいじめの共犯者です。
この小説は両親の描写もかなり興味深い。母親は首相の座を狙えるほどの政治家であり、そのサポート役を父親が務めているが、両親が抱いている価値観は古臭く、ジェイソンを認めようとしない。
日本でも、自らは旧姓で働きながら選択的夫婦別姓に反対する保守的な女性政治家が存在するし、イギリスにはなんといってもサッチャーという偉大なる先達がいたことを思い出すと、この人物造形にも説得力を感じる。
母親に向かって「EU離脱に尽力くだすってありがとう」と声をかける年輩の女性が、「わかってちょうだい、わたしくらい偏見のない人間はいないわ。車には、エルトン・ジョンのヒット曲集のCDだって積んでるし」と言ってのける場面など、至るところでミュージシャンをネタにしたジョークが出てくるのには笑えた。
「ぼく」が一時はまっていたエド・シーランが再三ネタになっていたり、両親がジェイソンを連れていく精神科医がコールドプレイのクリス・マーティンそっくりだったり、そしてなんといっても、「三十五歳を過ぎたら絶対にやっちゃいけない十のこと」のひとつに、「オアシスみたいな、もう何年も前にはやったバンドの話をすること」があるのには、いつの間に見られていたのか? と思った。
(けど、こんなことを言うセンスは14歳の「ぼく」のものではなく、作者ジョン・ボインの感覚だと思うが)
そう、LGBTや性自認を取り扱いつつも、筆致は軽妙で笑える要素も多いので、差別や社会問題を描いた作品は深刻で難しそう……という印象を持っている方や、『縞模様のパジャマの少年』がつらかったという方も、この作品ならすっと物語に入りこめると思います。
ここからジョン・ボインのほかの作品や、吃音に悩む少年を描いた『ペーパーボーイ』、その続編にあたる『コピーボーイ』など、原田勝さんが訳されたほかの作品を読み進めていくのはどうでしょうか?
孤独な独学から生み出された怪物の正体は? 『フランケンシュタイン』(メアリー・シェリー著 田内志文訳)※訳書多数あり
“フランケンシュタイン”をご存じでしょうか?
と聞くと、知らないと答える人はほとんどいないだろう。しかし、『フランケンシュタイン』を実際に読んだことがある人は? と聞くと、その数は格段に減るのではないだろうか。そもそも、“フランケンシュタイン”が怪物を作った若き青年の名前であることを知らない人も多いのかもしれない。
というわけで、今回の読書会の課題書に選んでみました。
この小説は、ウォルトンなる人物が姉のマーガレットへ送った手紙からはじまる。怪物もフランケンシュタインもまったく出てこない。
何者? と思って読み進めると、どうやらこのウォルトンは北極探検に向かっているらしいと判明する。手紙の日付は17**年12月11日となっている。この時代、北極は未開の地であり、人類の大いなる一歩を刻むべく、決死の覚悟で探検に出発したのだ。
人跡未踏の世界の眺望にこの燃えあがる探究欲を満たされ、人として最初の足跡をその大地に刻むのです。
ところが、偉業を成し遂げようと意気揚々と探検に出たにもかかわらず、二通目の手紙では「これまで一度も叶えられずに来た念願がひとつあり」、つらくてたまらないと言い出す。いったい何かと思うと、こんな弱音を吐く。
マーガレット、僕には友がありません。こうしていくら成功への熱狂に身を焦がそうとも、その歓喜を分かち合う友がいないのです。
さっきまでの威勢はどうしたのか、未踏の地に「人として最初の足跡」を刻もうとしているのに、淋しいとか友だちがいないとか、中学生のようなことを言っている場合じゃないだろうと説教したくなる。けれども、ウォルトンは「友が欲しくてなりません」と言いつのり、さらに以下のように告白する。
しかしそれにも増して不幸なのは、僕が独学の徒であることです。
ウォルトンは叔父さんの書斎で本を読みふけって知識を身につけたため、28歳ではあるが15歳の生徒より無学だと告白する。そのため、自分は白日夢を大きく膨らませてきたが、全体像を把握する力はないと認識し、独学ゆえの視野狭窄に陥りつつある危険性を自覚している。
そうこうしているうちに四通目の手紙では、氷原をソリに乗って走る怪物めいた巨人の姿を見かけ、船員一同が驚愕したと綴られる。
翌日、またもソリに乗った謎の人影を発見したので船に乗せて救助したところ、ヨーロッパ人だと判明する。どうしてこんなところまでやってきたのか経緯を尋ねているうちに、ウォルトンはその男の聡明さや洗練された精神に心打たれ、これこそが求めていた友だ! と、孤独な人間にありがちな勢いで思いこみ、探検に対する自らの思いを熱弁する。だが、ヨーロッパ人は同意するどころか、たちまちのうちに顔を曇らせ、嗚咽を漏らす。
なんと哀れなお方だ! 私と同じ狂気をお持ちでいなさる! あなたもあの美酒に心を毒され、奪われてしまったというのか!
ヨーロッパ人は、「私をこのような身に貶めたのと同じ危険に身を晒している」あなたに何らかの教訓を授けることができればと述べて、自らの数奇な人生を語りはじめる……
つまり、このヨーロッパ人こそがヴィクター・フランケンシュタインであり、いかにして怪物を生み出し、どういう経緯で氷に閉ざされた世界まで来てしまったのか、ウォルトンに対して語るという構造になっている。
ヴィクターは「私のように幸福な少年時代を過ごした者など、他にはおよそ見当たらないことでしょう」と自ら言うように、両親の愛を一身に受け、従姉妹(血は繋がっていないが)のエリザベトにふたりの弟、さらに親友アンリ・クレルヴァルに囲まれて、何ひとつ不自由することのない少年時代を送る。成長するにつれて自然科学への傾倒を深め、まるで何かに取りつかれたかのように、尋常ならざる熱意で勉学にのめりこむようになる。
この物語の舞台となった18世紀は、ニュートンがさまざまな法則を発見した17世紀末に続いて自然科学が飛躍的に発展した時代であった。
しかし、ヴィクターが最初に魅了されたのは、かつて悪魔召喚や不老不死を追及した時代遅れの怪しげな科学であった。ヴィクターの目には、ニュートン以降の近代科学は味気ないものに映った。いつの時代も、科学的な根拠のないオカルトめいたものに若者は魅かれてしまうのかもしれない。
けれども幸運なことに、ヴィクターは尊敬できる指導者と巡りあった。大学で出会ったヴァルトマン教授はそれまでの周囲の人々とは異なり、ヴィクターが心酔する一昔前の科学者たちをペテン師だと無下に切り捨てずに、そういう人々の尽きせぬ情熱こそが近代科学が発展する礎となったと助言した。
こうして、ヴィクターは初心を失うことなく近代科学の研究に没頭し、ついには生命の神秘を解き明かし、無生物から生物を作り出すという人類の夢を叶えてみせたのだった。
と、ここまではすばらしい成功譚であるが、ご存じのように、ヴィクターが生み出したものは醜くおぞましい怪物であった。創造者であるヴィクターもあれほどの情熱を注いだにもかかわらず、「自ら生み出した怪物の姿に耐えかね」部屋を飛び出す始末であった。
ああ! あのおぞましい顔を見て平気な人間などこの世におりましょうか!
と叫ぶくだりに至っては、自分で作っといて何言うてんねんと呆れてしまう。
あとでヴィクターは飛び出した部屋に恐る恐る戻り、怪物の姿が消えているのを悟ると、それ以上深く考えようとせず、ああ僕ちゃん怖かったとばかりに寝付いてしまい、親友アンリに介抱させるのであった。
これがフランケンシュタイン一家の悲劇の幕開けであった
ヴィクターの部屋を出た怪物の身にふりかかった運命については、物語の中盤で怪物自らが語る。この物語は、ウォルトン、ヴィクター、怪物の三人がそれぞれ語り手になるという入れ子の構造をとっている。
そう言うと、あれ? 怪物が物語なんて語れるの? と疑問を感じるかもしれないが、さすが天才科学者ヴィクターから生み出されただけあって、怪物も驚異的な学習能力を有しているのであった。
怪物は森を彷徨い、雨風や飢えに散々悩まされながら、ひとつの小屋を見つける。その隣には、老人と若い男と娘からなる貧しい一家が住んでいた。
怪物がその小屋に住みついてしばらく経つと、隣の一家にアラビア人の娘が訪ねてくる。どうやら若い男の恋人のようだが、アラビア娘は一家と会話ができないため、この土地の言葉を学びはじめる。
怪物もその講義を盗み聞くことによって、言葉を習得する。それもカタコト言葉を覚えるといったレベルではなく、あっという間に怪物は『失楽園』や『プルターク英雄伝』『若きウェルテルの悩み』を読破するようになるのだった。
知識を得た怪物は自我に目覚め、自分はいったい何者なのかと考えるようになる。どうして森の片隅で孤独で惨めな暮らしを余儀なくされているのか? 自分は何のために生を受けたのか? と悩みはじめる。
貧しくとも愛し合っている隣の一家への羨望の念がつのる。自分も親切にされたい、愛されたいと胸を焦がす。ある日ついに意を決して、一家の老人に話しかけてみるが……
忌むべき、忌むべき創造主よ! なぜ俺は生き長らえたのだ? なぜあの瞬間、お前が気まぐれに与えた命の火を俺は消してしまわなかったのだ?
こうやって見ていくと、冒頭に出てきたウォルトンがヴィクターと怪物それぞれの葛藤をあわせ持っていたことに気づく。
未知の世界を追求する情熱、孤独に苛まれる心、独学の危うさ……信頼できる指導者に巡りあったヴィクターとちがい、独学で知識を得た怪物は、頭でっかちのまま道を踏み外して暴走する。同じく独学で世界を理解したウォルトンは、自らを正してくれる友を激しく求める。
なんとなく読んでいると、ウォルトンのパート要る? と感じてしまうが、この物語のテーマが冒頭で凝縮されている構造の巧みさに感心させられる。
そして、この怪物は作者メアリー・シェリー自身のようにも思えてくる。
メアリーの生涯は、映画『メアリーの総て』にわかりやすくまとめられているが、父親は自由主義を唱えたアナーキーな思想家ウィリアム・ゴドウィンであり、母親は急進的フェミニストのメアリー・ウルストンクラフトであった。母親はメアリーを産んですぐに亡くなり、父親と継母のもとで育てられる。
この当時の女性は正式な教育を得る場がなく、メアリーは父親の周囲で飛び交う議論を耳で聞いて学んだと考えられる。メアリーの運命を変えた男、詩人シェリーと出会ったのも父親のサロンであった。シェリーと駆け落ちしたあとは、シェリーと親友バイロンのあいだで交わされる文学談義が最大の教師となったのだろう。
当時の最先端の知識を耳から得たメアリーだが、女である自分はウォルトンのように、「15歳の生徒より無学だ」というコンプレックスがあったのだろうか。
失意と孤独のなかで自我と知識に目覚めた怪物が、フランケンシュタイン一家に復讐すべく悪行のかぎりを尽くすさまはおぞましいのはたしかだが、一方でどことなく痛快でもある。怪物である自分を生み出し、そしてうち捨てたヴィクターへの強烈な愛憎は、単なる怪奇話にはおさまらない凄みがある。
メアリーのなかでは、自分に生と知識を授けた父親ゴドウィンがヴィクターであり、どうして自分を見捨てたのかという怪物の呪詛は、妻子あるシェリーと出奔したメアリーを認めなかった父親に対する思いなのかもしれない。
あるいは、怪物が手に負えない厄介な存在だと知るやいなやあわてて逃げ出すヴィクターの姿に、妊娠中の前妻を捨て、彼女が自殺するまで放っておいたシェリーが投影されているのかもしれない。
お前がどれほど絶望しようと、俺の苦しみは遥かにそれを凌ぐのだ。悔恨の棘は延々と、死が永遠に閉ざすまで俺の傷を疼かせ続けて止まないのだからな。
物語の最後はまた船上のウォルトンの語りに戻り、この小説全体の大きなテーマ、自然科学や探検といった真理の追求と、それに伴う倫理の問題が再び問われる。
このまま北極へ向かうのならば、乗組員全員の命が危険にさらされるという状況に陥ったのだ。危険を冒してまでも突き進むべきか?
危険を冒して怪物を作ったヴィクターは「漢になりたまえ!」と、なんとしても北極を目指すよう乗組員たちに演説する。さて、ウォルトンの選択は?
読書会でこの最後の選択について意見を聞いたところ、引き返す派が多数だった。私自身も引き返す方を選んだ。やはり命あっての物種ではないか……と思ってしまう。
しかし、自分や周囲の人間の命を危険にさらして真理を追求した人物がいたからこそ、これまで科学や医学が発展を遂げてきたのは事実であり、科学と倫理の関係は永遠に答えの出ない問いのように感じられる。
関連書については、まずはH・G・ウェルズ『モロー博士の島』が挙がった。
『フランケンシュタイン』は、錬金術のような迷信めいた科学と近代科学との “あいのこ” とも言える作品であるが、ウェルズの諸作品はそれ以降の近代科学の発展を如実に反映している。
ウェルズの時代は、科学の発展によって世界がよくなるという希望的観測がまだ生きていたが、『フランケンシュタイン』が予言していたかのように、人類は核兵器という「手に負えない怪物」を作り出し、科学と倫理という問題がクローズアップされるようになる。
ここで頭に浮かぶのが、原子爆弾の開発者の一家が登場するカート・ヴォネガット『猫のゆりかご』である。
映画『2001年宇宙の旅』を想起した人も多く、フィクションのなかでもSFというジャンルは、人類をとりまく環境の変化にきわめて敏感に反応してきたが、現在のコロナ禍において、どういう物語が生まれるのだろうか? と全員で語り合った。
そのほか、 父親に殺された母親の体の一部を自らの身体に埋めこまれた子どもたちの人生を描いた、エリック・マコーマック『パラダイス・モーテル』も話題にのぼった。考えたら、船上での語りではじまるという構造も引き継がれている。
読書会では、ルッキズムという観点からも考察した。どうしてこれほど怪物が忌み嫌われるのかというと、ただひたすら醜いからである。
そこで、ジャック・ロンドンの“Moon-Face”や、サリンジャーの「笑い男」などの興味深い短編を参考図書として挙げてくれた方もいた。
だれもが名前を知っているものの、知名度のわりにはあまり読まれていない『フランケンシュタイン』。
今回あらためて読んでみると、現代にも通じる多くのテーマを含んだ物語であり、それらのテーマを効果的に伝える語りの構造にも工夫がされていることがわかった。
興味を持った方はぜひ一度読んでみて、ウォルトン、ヴィクター、怪物の三人の語りのなかで、どれに一番共感できるかを考えてみてはいかがでしょうか。
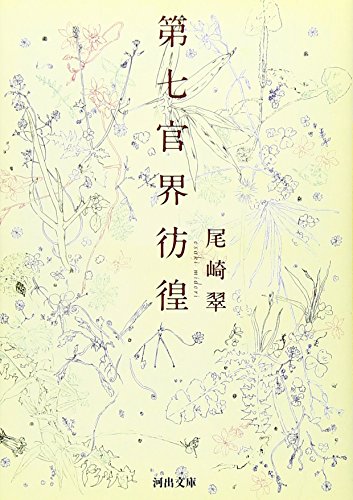

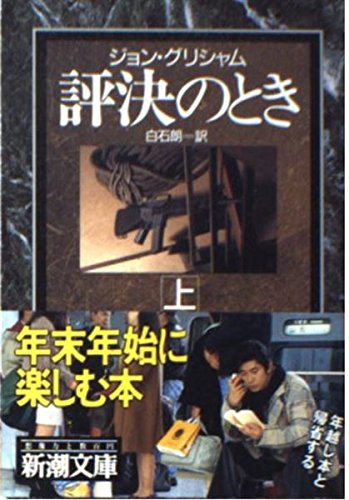
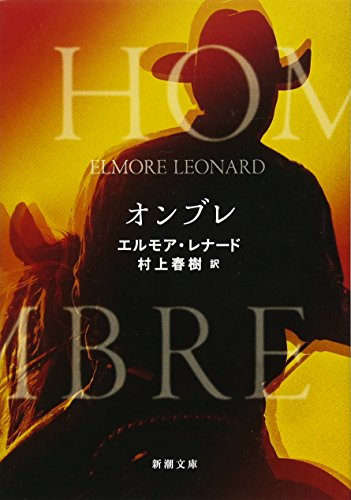


![NHK 100分 de 名著 ブルデュー『ディスタンクシオン』 2020年 12月 [雑誌] (NHKテキスト) NHK 100分 de 名著 ブルデュー『ディスタンクシオン』 2020年 12月 [雑誌] (NHKテキスト)](https://m.media-amazon.com/images/I/51uDD+IfjML.jpg)